Masakiです。
貯金が1000万円を超えると、一つの大きな節目を迎えたといえます。
実際、金融広報中央委員会の調査によれば、30代で貯蓄1000万円以上を持つ世帯は15%程度、50代でも約30%にとどまります。
多くの人にとって1000万円の貯蓄は大きな自信につながる金額ですが、その一方で「これだけあっても将来が不安」「どう運用すれば良いか分からない」という声も少なくありません。
ある調査では、貯金1000万円以上ある人でも老後に「それほど心配していない」と回答したのは約25%に過ぎず、大半の人は引き続き不安を感じていました。
では、貯金が1000万円を超えた場合に次に取るべき具体的な行動を見てみましょう。
貯金1000万円を超えたら次にどうする?
貯金1000万円を超えている人が検討したいポイント
負債の精算
住宅ローン以外の高金利の借入(カードローンやリボ払いなど)があれば、繰上返済や完済を優先しましょう(高金利の負債は利息負担が大きく、資産形成の障害となるためです)。
預け先の分散
1000万円を超える預金はペイオフ(預金保護制度)の保護対象外となり、万一金融機関が破綻した場合に保証されません。
生活防衛資金の確保
病気や失業など緊急時に備え、数ヶ月分の生活費に相当する現金は手元に残しておきましょう(全額を投資に回さず、いつでも引き出せる予備資金を確保しておくことで安心感につながります)。
近い将来必要な資金の区別
今後5年以内に使う予定の資金(住宅購入の頭金、教育資金など)があるなら、その分は安全な預金や個人向け国債など元本割れのない商品で運用し、大きな価格変動リスクにさらさないようにしましょう(必要な時期に確実に使えるようにしておくことが重要です)。
余剰資金の資産運用
上記を行ったうえで手元に残る余裕資金については、インフレによる目減りを防ぎつつ中長期的に増やすための資産運用を検討します。
運用に際してはリスク許容度に応じ、商品を選んで資産をバランスよく配分しましょう。
これらの対策を講じることで、大切な1000万円をしっかり守りつつ、さらに効率的に増やしていく土台が整います。
日本人の平均貯蓄額はどれくらい?貯金ゼロの人は何割いる?
「自分の貯金額は多い方なのか少ない方なのだろう」と気になる方も多いでしょう。
まず、日本人全体の平均的な貯蓄状況を押さえておきます。
金融広報中央委員会の調査(令和4年)によると、全世帯の平均貯蓄額は約1,150万円で、中央値は約280万円でした。
平均額が中央値よりも大きいのは、一部の富裕層が平均値を押し上げているためで、大半の世帯では平均より少ない貯蓄額しか持っていないことを意味します。
年代別の平均貯蓄額と中央値を以下にまとめます
| 年代 | 平均貯蓄額 | 貯蓄中央値 |
|---|---|---|
| 20代 | 185万円 | 20万円 |
| 30代 | 515万円 | 150万円 |
| 40代 | 785万円 | 200万円 |
| 50代 | 1,199万円 | 260万円 |
| 60代 | 1,689万円 | 552万円 |
| 70代 | 1,755万円 | 650万円 |
ご覧のとおり、どの年代でも平均値より中央値がかなり低く、特に若い世代ほど中央値が小さい傾向があります。
例えば20代では平均185万円に対し中央値はわずか20万円であり、30代でも中央値は150万円程度しかありません。
これは、多くの人がそれほど多くの貯金を持っていないことを示しています。
では、「貯金ゼロ」の人はどのくらいいるのでしょうか。
同じ調査によれば、全体で見た貯蓄ゼロ世帯の割合は、二人以上世帯で約25%、単身世帯では約36%にのぼります。
特に単身世帯では無貯蓄層の割合が高く、20代では約44%、30代でも約34%が貯金ゼロというデータがあります。
二人以上世帯でも、60代で約5世帯に1世帯(19~21%程度)が貯蓄を全く持っていない状況です。
言い換えれば、貯金がまったくない人も決して珍しくはないのです。
ただし、貯金ゼロのままでは将来の急な出費や老後に不安が残ります。
実際、単身世帯の20~50代では貯蓄残高の中央値が100万円以下であり、多くの人が「貯金がない」ことに悩んでいると考えられます。
まずは少額からでも貯蓄を始め、将来の安心につなげていくことが重要です。
次の章では、「30歳で貯金ゼロ」のケースを例に、貯金がない人が今からでも無理なく貯蓄を始める方法を見ていきましょう。
30歳で貯金ゼロ!今からでも遅くない貯蓄術
「気づけばもう30代なのに貯金がない…」と不安を感じている方もいるでしょう。
確かに30歳前後は仕事や家庭で大きな変化が訪れる時期で、お金が貯まりにくい状況にあるかもしれません。
実際、先ほど紹介したように30代で貯金ゼロの人は珍しくなく、約3割が該当します。
しかし、30代からでも決して遅すぎることはありません。
今から計画的に貯蓄を始めれば、将来の安心に十分間に合います。
ここでは、30歳で貯金ゼロの人が無理なく貯金体質へと変わるための5つのステップを紹介します。
ステップ1:家計の収支を把握する
まずは現在の収入と支出を正確に把握することから始めましょう。
貯金ができない人の多くは、自分が毎月いくら使っているかを把握できていません。
そこで、1ヶ月間すべての支出を記録してみます。
家計簿アプリやエクセル、ノートなど手段は何でも構いません。
家賃・食費・光熱費といった固定費から、日々の細かな買い物まで書き出すと、自分のお金の使い道が「見える化」されます。
「こんなことにこんなに使っていたのか」と気付きがあるはずです。
まずは現状を把握することで、貯蓄の出発点に立つことができます
ステップ2:貯金の目標額を決める
次に、貯金の目標を具体的に設定しましょう。
なんとなく「貯金しなきゃ」と思うだけではモチベーションが続きません。
「1年後に50万円貯める」「5年以内に貯金100万円を達成する」など、明確な目標額と期限を決めます。
目標を立てる際には、将来のライフイベントを考慮すると現実的な数字を導きやすくなります。
例えば「5年後に車を買うために○○万円必要」「結婚や出産に備えて○○万円」など、ライフプランに沿った貯蓄計画を立ててみましょう。
目標額が具体的になれば、「〇万円貯めるには毎月〇万円ずつ貯金しよう」と逆算して行動計画を立てることができます。
ステップ3:無駄な出費を減らす
目標が決まったら、支出の見直しです。
ステップ1で洗い出した支出の中から、「無くても困らない支出」「減らせそうな出費」がないかチェックしましょう。
例えば、毎日のコンビニでの買い物やカフェの利用が積み重なっていないでしょうか。
使っていないサブスクサービスにお金を払い続けていないか、スマホのプランが割高になっていないかなども確認します。
削れる無駄が見つかったら、できる範囲で少しずつ削減してみましょう。
いきなり全てを我慢するのは続かないので、「平日はお弁当を持参する」「飲み会は月1回までにする」など、小さな改善から始めるのがコツです。
また、高金利の借金(クレジットカードのリボ払いなど)がある場合は、繰り上げ返済や借り換えで利息負担を減らすことも検討しましょう。
無駄な利息支払いを減らせば、その分を貯蓄に回せるようになります。
ステップ4:先取り貯金を実行する
支出を見直しつつ、毎月の給料から一定額を確実に貯金に回す仕組みを作ります。
おすすめは「先取り貯金」です。
給料が振り込まれたら、使う前に貯金分を別口座に移してしまいます。
例えば、毎月の給料日の翌日に1万円を貯蓄用口座へ自動振替する設定にすれば、強制的にお金が貯まっていきます。
会社員の方で財形貯蓄制度が利用できる場合は、給与天引きで貯蓄するのも良いでしょう。
先取り貯金によって、「気付いたら使いすぎて今月も貯金できなかった…」という事態を防げます。
手元に残ったお金で生活する習慣が身に付けば、無理なく継続できます。
ステップ5:少額から資産運用に挑戦する
ある程度貯金ができて余裕資金が生まれてきたら、少額から資産運用にも挑戦してみましょう。
超低金利の下では、預金だけに頼っていてもお金は増えません。
むしろインフレで実質価値が目減りするリスクもあります。
毎月1万円でも良いので、投資信託などを積み立ててみると、「お金がお金を生む」感覚を体験できます。
資産運用と聞くと難しそうですが、まずはリスクを抑えたインデックスファンドなどから始めるのがおすすめです。
長期でコツコツ積み立てれば、時間を味方につけて資産を増やすことができます。
たとえば年利3~5%程度で運用できれば、10万円を投資して1年で3千~5千円の利益が出ます。
少額でも「お金が増える」経験を積むことで、貯蓄へのモチベーションも高まるでしょう。
以上のステップを踏めば、30歳からでも着実に貯金を増やし、将来への不安を減らすことが可能です。
ポイントは焦らず無理のない範囲で継続することです。
毎月少しずつでも貯金が増えていけば、自信にもつながり、さらなる資産形成の意欲が湧いてくるはずです。
年代別の貯金戦略:10代から70代以上まで
人生のステージによって、お金の使い方や貯金の目的は変化します。
ここでは10代から高齢世代まで、年代別に見た貯蓄のポイントと戦略を紹介します。
10代:お金の基礎知識を身につける
10代はまだ収入源が限られていますが、お金との付き合い方を学ぶ絶好の時期です。
アルバイトやお小遣いの範囲で構わないので、「収入の中から決まった額を貯金する」習慣を身につけてみましょう。
例えば、お小遣い月5000円の高校生なら毎月1000円だけ貯金する、といった小さな経験でOKです。
また、金融や経済の基礎知識を学ぶのも大切です。
銀行口座の仕組みやクレジットカードの使い方、利息とは何かといった基本をこの年代で理解しておくと、将来大きなお金を扱うようになってから役立ちます。
両親や学校の先生に相談したり、金融教育の本やサイトを読んだりして、お金についての教養を高めておきましょう。
20代:貯蓄体質づくりと自己投資の両立
社会人になりたての20代は、収入が増える一方で支出も増えがちな時期です。
まずは生活基盤を固め、緊急用の資金(生活費の3~6ヶ月分など)を目標に貯金してみましょう。
社会人生活のスタートで予想外の出費が発生しても、この緊急予備資金があれば借金せずに乗り切れます。
20代前半では「自己投資」も重要です。
資格取得や勉強、趣味、人脈作りなど将来の糧になることにもお金を使いましょう。
これらは直接の貯金ではありませんが、長い目で見れば収入アップや充実した人生につながり、結果的に経済的安定をもたらします。
とはいえ、無計画に浪費していては貯金はできません。
収入と支出のバランスを意識し、先取り貯金などで毎月少額でも貯蓄を積み上げる習慣をつけてください。
20代後半になったら、将来の結婚や住宅購入、車の購入など大きなイベントに向けた貯金も少しずつ始めておくと安心です。
時間を味方につけられるこの年代のうちに、積立投資など資産運用もスタートできればベストです。
30代:ライフイベントと貯蓄の両立
30代は結婚や出産、マイホーム購入などライフイベントが本格化する年代です。
これらのイベントにはまとまったお金が必要になるため、計画的な貯蓄が求められます。
結婚資金や出産費用は事前に大まかな相場を調べ、必要額を予測して準備しましょう。
子育てが始まれば、教育資金も重要です。
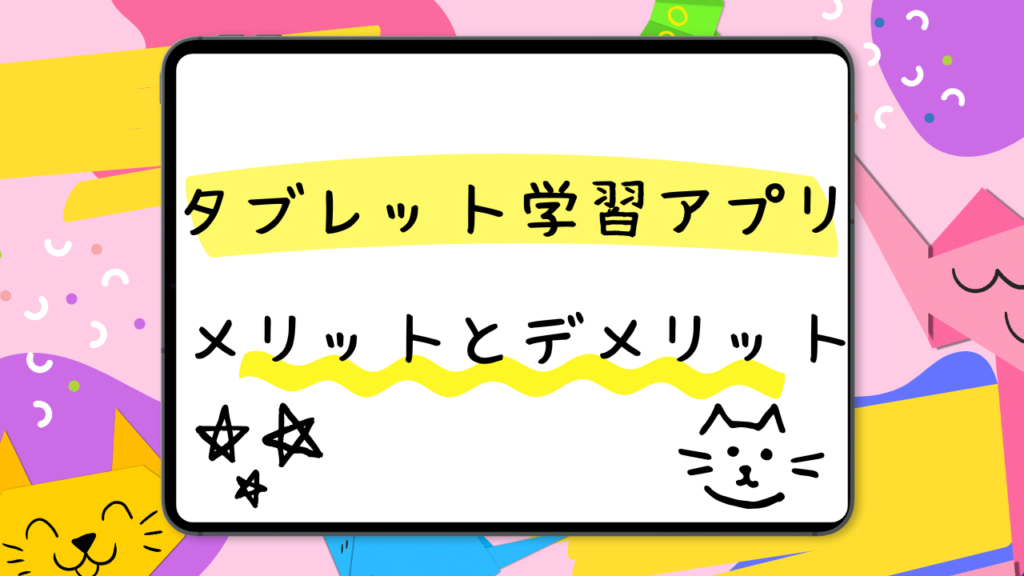
児童手当の貯蓄などを活用し、子どもが小さいうちから少しずつ教育費を蓄えておくと、後々慌てずに済みます。
一方で、30代は収入が増えて生活水準も上がりやすい時期です。
いわゆる「ライフスタイルインフレーション」に注意し、収入が増えた分をすべて消費に回すのではなく、貯蓄や運用にも振り向けるバランス感覚が大切です。
また、住宅ローンを組む場合は無理のない返済計画を立てましょう。
「年収の5~6倍以内の借入に抑える」「金利変動リスクに備える」など堅実な借入額に留め、繰り上げ返済も視野に入れておくと、将来の家計が安定します。
30代後半では老後資金についても少しずつ意識し始めると良いでしょう。
40代:資産形成の仕上げと教育費ピークへの対応
40代は働き盛りで収入も安定してくる一方、子どもの教育費や住宅ローン返済など支出もピークを迎える時期です。
この年代では、これまでの貯蓄状況を一度振り返り、必要に応じて軌道修正することが重要です。
もし貯蓄が目標より不足していると感じたら、収支改善や追加の資産運用を検討しましょう。
子どもが高校・大学に進学すれば教育費が大きく増加します。
奨学金や教育ローンの利用も含め、家計に過度な負担をかけない資金計画を立てます。
大学進学までに十分な貯金が用意できなければ、学費分を毎月積み立てたり、必要に応じて奨学金を検討するなど早め早めの対策を。
一方、40代は老後まで残り20年程度となり、退職後の生活を具体的にイメージし始める時期でもあります。
50代以降に向けて、住宅ローンの完済計画や老後資金の大枠をこの年代で描いておきましょう。
また、病気やケガへの備えとして、必要に応じて保険の見直しも検討します。
医療保険や就業不能保険など、自分や家族の状況に合った保障を確保しておけば、万一働けなくなっても貯蓄を大きく取り崩さずに済みます。
50代:老後資金の本格準備と負債の解消
50代に入ると、定年退職や子どもの独立が現実味を帯びてきます。
この年代は、老後資金の仕上げと負債の解消に注力すべき時期です。
まず、可能であれば子どもの教育費を卒業までに払い終え、住宅ローンも定年までに完済できる計画を立てます。
負債を減らしておくことで、定年後の支出負担を軽くできます。
次に、公的年金だけで不足しそうな老後資金を具体的に計算し、不足額を埋める貯蓄・運用計画を仕上げます。
一般に「老後資金2000万円問題」と言われるように、夫婦で老後30年を過ごすには毎月約5.5万円の赤字が発生し、不足額が総額で1,300~2,000万円に上るという試算があります。
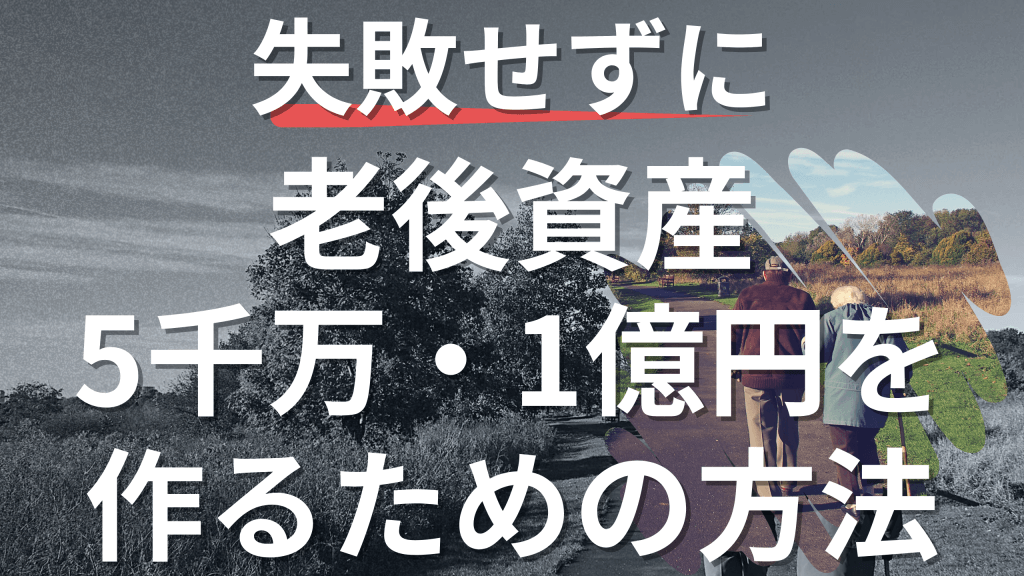
自分の生活スタイルに合った必要額を試算し、そのためにあと何年働くか、毎月いくら貯蓄・運用するかを検討しましょう。
幸い、50代はまだ働いて収入を得られる期間があります。
可能であれば現役のうちに貯蓄額を最大化する努力をします。
役職定年や早期退職制度などで収入が減るケースもあるので、収入減少に備えて支出を抑える練習も必要です。
また、この時期に資産運用のリスクを徐々に下げ始めることも検討します。
株式中心の運用をしていた人も、そろそろ債券や預金の比率を高め、暴落が起きても老後資金が大打撃を受けないようにポートフォリオを調整します。
60代:定年後の生活設計と資産の取り崩し計画
60代は多くの人が定年退職を迎え、仕事中心の生活からリタイア生活へと移行する年代です(近年は定年延長で65歳まで働くケースも増えています)。
この段階では、退職金や年金受給開始を見据えて、手持ち資産と今後の収支計画を再確認しましょう。
退職金が出た人は、一部をローン返済に充てたり、まとまった預金として確保した上で、残りを安全な金融商品で運用するなど計画的に管理します。
公的年金は65歳から支給開始となる場合が多いですが、60~64歳の間は年金だけでは収入が不足します。
その間の生活費は退職金や貯蓄で補う必要があるため、いつ・いくら資産を取り崩すか計画を立てておきます。
年金受給が始まった後も、毎月の年金だけで足りない分は貯蓄から取り崩すことになります。
この際、一気に使いすぎないよう「年間○万円まで取り崩す」といったルールを決め、資産が想定より早く尽きてしまわないよう管理が必要です。
また、60代はまだ比較的元気な方が多いので、人によっては継続雇用や再就職、アルバイトなどで収入を得続ける選択もあるかもしれません。
少しでも収入があれば、貯蓄の目減りを遅らせることができますし、生きがいにもなります。
70代以上:豊かな老後と資産管理
70代以降になると、多くの方は本格的な老後生活に入ります。
この年代では、これまで頑張って築いてきた資産を上手に使いながら、健康で豊かな生活を送ることが目標になります。
まず、毎月の年金収入と必要な生活費を照らし合わせ、無理のない範囲で趣味や旅行などにもお金を使って人生を楽しみましょう。
ある程度の年齢になったら、「貯める」より「上手に使う」ことにも目を向けたいものです。
一方で、長生きリスクや医療・介護費への備えも引き続き大切です。
80代、90代まで生きた場合に備えて資金が底をつかないよう、引き続き計画的に資産を管理します。
医療費や介護サービス費用がかさんでも対応できるよう、高額療養費制度や介護保険の制度も理解しておくと安心です。
必要に応じて、子どもや信頼できる親族に資産管理を相談することも検討しましょう。
認知症対策として家族信託や後見制度を活用するケースもあります。
自分の判断能力がしっかりしているうちに、財産の分配や相続について家族と話し合っておくことも円満な資産承継につながります。
まとめ:今日から始める小さな一歩が将来の安心につながる
貯金に関する様々な疑問や不安について、年代別・家族構成別・貯蓄額別に詳しく見てきました。
「うちは平均より貯金が少ないかも…」「もう〇歳だけど間に合うかな…」と感じていた方も、データや具体例を知ることで、自分なりの改善策が見えてきたのではないでしょうか。
貯金は多ければ多いほど安心材料にはなりますが、単に金額を追い求めるだけでは途中で息切れしてしまいます。
大切なのは、自分や家族の状況に合った現実的な目標を立て、無理のない範囲でコツコツ継続することです。
本記事で紹介したように、たとえ貯金ゼロの状態からでも、収支の把握→目標設定→支出見直し→先取り貯蓄→資産運用というステップを踏めば、少しずつ着実に貯蓄体質へと変わっていけます。
また、人生設計や価値観は人それぞれです。
「老後は質素でも子どもの教育に全力を注ぎたい」「趣味を楽しみつつマイペースに貯めたい」など、自分が納得できる貯金のスタイルを見つけることも長続きの秘訣です。
貯金習慣が身につけば、将来予期せぬ出費があっても慌てずに対処でき、精神的なゆとりが生まれます。
実際にお金が貯まってくると、経済的な安心感だけでなく、自分自身の自信にもつながっていくでしょう。
とはいえ、人生はお金だけが全てではありません。
必要な貯蓄を確保しつつ、時には適度にお金を使って人生を楽しむことも忘れずに。
貯金と日々の充実とのバランスを取りながら、「お金に振り回されない生き方」を目指したいものです。
ぜひ本記事の内容を参考に、自分なりの貯蓄プランを実践してみてください。





コメント