Masakiです。
あなたは「アッパーマス層」という言葉を正しく理解していますか。
純金融資産3,000万円という数字が持つ本当の意味をご存知でしょうか。
日本の約10世帯に1世帯が該当するとされる「アッパーマス層」ですが、その実態は意外なほど知られていません。
この階層に到達した人々の生活、悩み、そして次なる目標とは一体何なのでしょうか。
この記事は、アッパーマス層に関するあらゆる疑問に答える、日本で最も包括的なガイドです。
信頼性の高い野村総合研究所(NRI)の最新データを基に、その正確な定義から、世帯数や割合、年代、職業といった詳細な人物像までを徹底的に解き明かします。
さらに、彼らがどのような生活を送り、何に悩み、そしてどのようにしてその資産を築き上げたのか、そのリアルな姿に迫ります。
この記事を読み終える頃には、アッパーマス層という社会経済的な階層についての明確な理解が得られるだけでなく、ご自身の資産形成における現在地を客観的に把握し、未来に向けた具体的な目標設定を行うための確かな羅針盤を手にしていることでしょう。

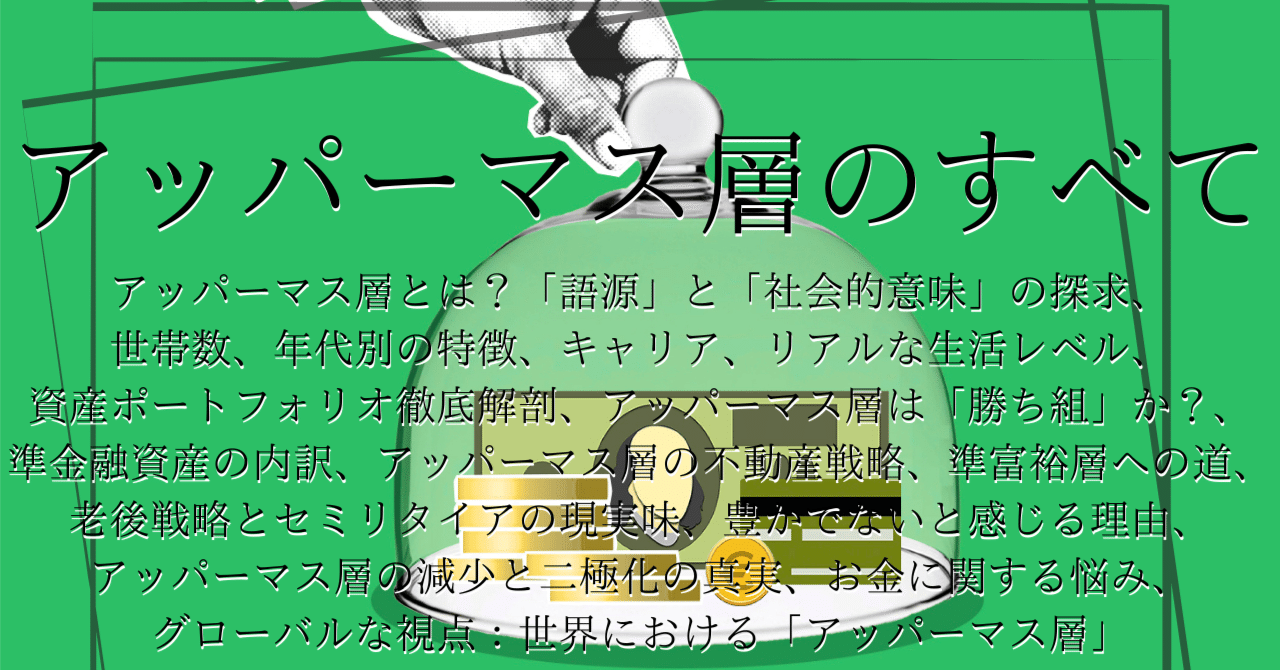
アッパーマス層とは?基本の定義を理解する
アッパーマス層という概念を正確に把握するためには、まずその定義の根幹をなすいくつかの重要なキーワードを理解する必要があります。
この言葉は、日本の資産階層を分析する上で最も権威ある指標の一つとなっており、その定義を学ぶことは、現代日本の経済構造を理解する第一歩と言えるでしょう。
野村総合研究所(NRI)による5つの階層ピラミッド
日本における資産階層の議論は、株式会社野村総合研究所(NRI)が定期的に発表する調査報告書が基盤となっています。
この調査では、日本全国の世帯をその保有する「純金融資産」の額に応じて5つの階層に分類しており、このピラミッド構造が資産状況を測る上でのデファクトスタンダードとして広く認知されています。
この分類方法は、単に年収の多寡で判断するのではなく、実際にどれだけの金融資産を蓄積できているかという「ストック」の観点から世帯の経済力を見るため、より実態に即した分析を可能にしています。
NRIによる5つの階層は、以下の通りです。
超富裕層(Ultra-High Net Worth):純金融資産5億円以上
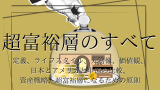
富裕層(High Net Worth):純金融資産1億円以上5億円未満
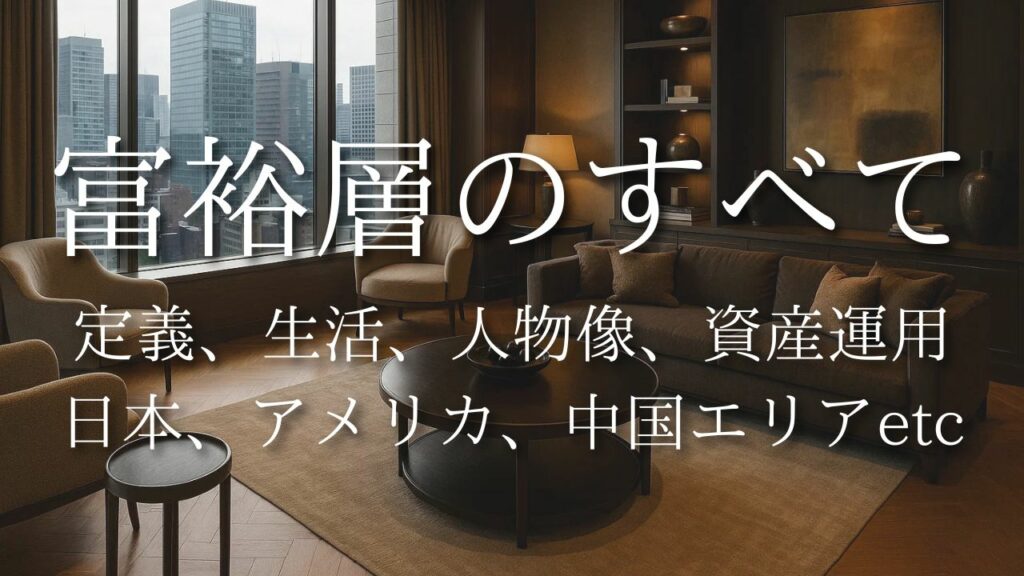
準富裕層(Quasi-Affluent):純金融資産5,000万円以上1億円未満

アッパーマス層(Upper Mass):純金融資産3,000万円以上5,000万円未満
マス層(Mass):純金融資産3,000万円未満
このピラミッドにおいて、アッパーマス層は下から2番目に位置し、大多数を占めるマス層のすぐ上に存在する階層です。
経済的な安定を確保し、本格的な資産形成のステージへと足を踏み入れた「お金持ちの入り口」とも言える重要なポジションを占めています。
「純金融資産」の正確な意味とは?
アッパーマス層の定義を理解する上で、最も重要な概念が「純金融資産」です。
これは、世帯が保有する金融資産の合計額から、住宅ローンや自動車ローンなどの負債を差し引いた金額を指します。
具体的に、金融資産に含まれるのは以下のようなものです。
・預貯金(普通預金、定期預金など)
・株式
・債券
・投資信託
・一時払い生命保険や年金保険など
一方で、この計算において極めて重要な注意点があります。
それは、自宅や投資用不動産といった「実物資産」の価値は、金融資産の合計には含まれないという点です。
しかし、それらを購入するために組んだ住宅ローンや不動産投資ローンは「負債」としてしっかりと差し引かれます。
この定義がもたらす意味は非常に大きいものです。
例えば、時価1億円のタワーマンションに住んでいても、8,000万円の住宅ローンが残っており、預貯金が2,000万円しかない場合を考えてみましょう。
この世帯の純金融資産は、金融資産2,000万円から負債8,000万円を引くとマイナス6,000万円となり、NRIの定義上は「マス層」に分類されます。
一方で、賃貸住宅に住みながらコツコツと4,000万円の株式や投資信託を築き上げ、負債がゼロの世帯は「アッパーマス層」となります。
つまり、このフレームワークは、単なる総資産の大きさではなく、その世帯が持つ「流動性」や「投資余力」を測る指標なのです。
純金融資産が多いということは、生活防衛資金を確保した上で、さらなる資産成長を目指して自由に動かせる資本をどれだけ持っているかを示しており、経済的な自由度や安定性をより正確に反映していると言えるでしょう。
アッパーマス層の資産額:いくらから該当するのか
改めて、アッパーマス層に該当する純金融資産の具体的な範囲を確認します。
その定義は、「純金融資産保有額が3,000万円以上5,000万円未満」の世帯です。
3,000万円という金額は、多くの人にとって退職後の生活資金や、人生の大きな目標として意識される一つの節目です。
この水準に到達するということは、日々の家計管理というフェーズを卒業し、自身の資産をどのように守り、育てていくかという戦略的な資産運用のステージに入ったことを意味します。
マス層が人口の大多数を占める中で、この3,000万円の壁を越えることは、経済的な自立に向けた大きな一歩であり、日本の経済社会において一定の成功を収めた層として認識されることになります。
最新データで見るアッパーマス層の実態
アッパーマス層の定義を理解したところで、次に最新のデータを用いて、彼らが日本社会においてどれほどの規模と影響力を持つ存在なのかを具体的に見ていきましょう。
客観的な数字は、この階層の姿をより鮮明に浮かび上がらせます。
日本におけるアッパーマス層の世帯数と割合
野村総合研究所が発表した推計(2023年時点)によると、日本におけるアッパーマス層の世帯数は576万5,000世帯です。
日本の総世帯数が約5,570万4,000世帯であるため、アッパーマス層が全体に占める割合は約10.35%となります。
この数字は、「およそ10世帯に1世帯」がアッパーマス層に該当することを意味しており、決して手の届かない存在ではなく、身近にも存在する比較的身近な「小金持ち」層であることがわかります。
一方で、近年の動向を見ると、富裕層や準富裕層の世帯数が増加傾向にあるのに対し、アッパーマス層の世帯数は微減しているという指摘もあります。
しかし、これは必ずしもネガティブな現象ではありません。
この背景には、株式市場の好調などを受けて資産価値が増加し、多くのアッパーマス層世帯が純金融資産5,000万円の壁を突破して、一つ上の階層である「準富裕層」へとステップアップしたことが大きな要因として考えられます。
この事実は、アッパーマス層が最終的なゴールではなく、さらなる富裕層へと至るための重要な「通過点」であり、経済的流動性の中で活発な動きを見せるダイナミックな階層であることを示唆しています。
資産ピラミッド全体像:各階層の分布と推移
アッパーマス層の位置づけをより明確に理解するためには、資産ピラミッドの全体像を把握することが不可欠です。
以下の表は、最新のデータに基づいた日本の純金融資産保有額別の階層構造をまとめたものです。
| 階層 | 純金融資産保有額 | 世帯数 | 割合 |
| 超富裕層 | 5億円以上 | 11万8,000世帯 | 0.21% |
| 富裕層 | 1億円以上5億円未満 | 153万5,000世帯 | 2.76% |
| 準富裕層 | 5,000万円以上1億円未満 | 403万9,000世帯 | 7.25% |
| アッパーマス層 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 576万5,000世帯 | 10.35% |
| マス層 | 3,000万円未満 | 4,424万7,000世帯 | 79.43% |
(出典:野村総合研究所の2023年推計データより作成)
この表から、いくつかの重要な点が読み取れます。
第一に、日本の世帯の約8割が純金融資産3,000万円未満のマス層に属しており、アッパーマス層は上位約20%の集団の一部であることがわかります。
第二に、アッパーマス層(10.35%)と準富裕層(7.25%)を合わせると、全体の約17.6%を占めます。
この層は、経済的な余裕を持ちつつも、超富裕層や富裕層のような絶対的な資産規模には至らない、いわば「広義の富裕層予備軍」と見ることができます。
長期的なトレンドとしては、2013年以降、富裕層と超富裕層の世帯数および資産総額は一貫して増加傾向にあります。
この背景には、アベノミクス以降の株価上昇による資産価値の増大や、団塊の世代からの相続による世代間の資産移転が本格化していることなどが要因として挙げられます。
アッパーマス層が保有する純金融資産の総額
アッパーマス層の世帯数だけでなく、彼らが保有する資産の総額もまた、その経済的な重要性を示しています。
過去のデータ(2017年時点)では、アッパーマス層全体で約320兆円の純金融資産を保有していました。
この数字は、日本の個人金融資産全体の中で決して小さくない割合を占めています。
しかし、富裕層と超富裕層(全世帯の約3%)が日本の純金融資産全体の26%以上を保有しているという事実と比較すると、富の集中が上位層でいかに進んでいるかが分かります。
アッパーマス層は、個々の世帯が経済的な安定を築いている一方で、マクロ経済全体を動かすほどの支配的な資産を持っているわけではありません。
彼らは、日本経済の分厚い中間層の上層部を形成し、安定した消費や投資活動を通じて経済を下支えする重要な役割を担っていると言えるでしょう。
アッパーマス層の人物像:どのような人たちなのか?
統計データで規模感を掴んだ後は、アッパーマス層を構成する人々の具体的な人物像、つまりデモグラフィックな側面に焦点を当てていきます。
どのような年齢、家族構成、そして職業の人々がこの階層に到達しているのでしょうか。
年代別の特徴と割合
純金融資産の蓄積は、収入から支出を引いた差額を、時間をかけて積み上げていくプロセスです。
そのため、アッパーマス層に到達する人々の割合は、年齢と強い相関関係があります。
年代別の金融資産保有状況を見ることで、資産形成の一般的な道のりが浮かび上がってきます。
| 年代 | 金融資産保有額(平均値) | 金融資産保有額(中央値) | アッパーマス層以上の割合 |
| 20代 | 382万円 | 84万円 | 0.1% |
| 30代 | 677万円 | 180万円 | 4.0% |
| 40代 | 944万円 | 250万円 | 6.0% |
| 50代 | 1,168万円 | 250万円 | 10.7% |
| 60代 | 2,033万円 | 650万円 | 19.0% |
(出典:金融広報中央委員会の調査データ等を基に作成(二人以上世帯))
この表で特に注目すべきは、「平均値」と「中央値」の大きな乖離です。
平均値は一部の極端に資産の多い世帯によって引き上げられるため、一般的な実感とは離れがちです。
一方で、データを小さい順に並べたときに真ん中に来る値である中央値は、より実態に近い「標準的な世帯」の姿を示しています。
例えば40代の二人以上世帯の中央値は250万円であり、アッパーマス層の下限である3,000万円がいかに高いハードルであるかが分かります。
20代・30代:若き達成者たちの実像
20代でアッパーマス層に到達する割合はわずか0.1%、30代でも4.0%と、この年代での達成は極めて稀です。
若くしてこの階層に属する人々は、いくつかの典型的なパターンに分類できます。
外資系の金融機関やコンサルティングファーム、急成長IT企業などで高額な報酬を得る専門職、あるいは自ら事業を立ち上げて成功した起業家などがその代表例です。
また、親からの大規模な生前贈与や相続によって資産を形成したケースも考えられます。
夫婦世帯の場合、共に高収入の専門職であるパワーカップルで、子供がいない(DINKs)ライフスタイルを選択し、収入の大部分を貯蓄や投資に回すことで、短期間での資産形成を可能にしている場合も多いでしょう。
40代・50代:キャリアと資産形成の中核世代
40代(6.0%)、50代(10.7%)は、アッパーマス層の割合が大きく増加する年代です。
この世代は、まさにキャリアの最盛期を迎えています。
大企業で管理職(部課長クラス)として活躍する人々、長年の経験を積んだ医師や弁護士などの専門家、事業を軌道に乗せた経営者などが中心となります。
20年以上にわたる継続的な貯蓄と投資の成果が実を結び、純金融資産が3,000万円の大台を超えるのです。
しかし、同時にこの年代は、子供の高等教育費(大学進学など)や住宅ローンの返済といった大きな支出が重なる時期でもあります。
高い収入を得ながらも、計画的な資金管理と規律ある生活を維持することが、アッパーマス層への到達、そしてその維持に不可欠となります。
60代以降:退職金と老後資金のリアル
60代は、アッパーマス層以上の割合が19.0%と、全年代で最も高くなります。
この背景には、定年退職時に受け取る「退職金」の存在が大きく影響しています。
長年勤め上げた企業から受け取るまとまった退職金によって、それまでマス層だった世帯が一気にアッパーマス層や準富裕層へと移行するケースが非常に多いのです。
実際に、60代の二人以上世帯の平均金融資産は2,000万円を超え、他の年代を大きく引き離しています。
ただし、この年代をピークとして、その後は年金生活に入り、蓄えた資産を取り崩しながら生活していく「資産活用期」に移行するため、純金融資産は徐々に減少していく傾向も見られます。
世帯構成から見る特徴:夫婦、独身、家族の姿
アッパーマス層への道のりは、世帯構成によっても大きく異なります。
特に、共働き夫婦、いわゆる「パワーカップル」は資産形成において圧倒的な優位性を持っています。
NRIは、世帯年収が高く、将来的には富裕層になる可能性を秘めた共働き世帯を「スーパーパワーファミリー」と定義しており、その増加が富裕層全体の拡大に寄与していると分析しています。
二つの収入源があることで、片方の収入で生活費を賄い、もう片方の収入をほぼ全額貯蓄や投資に回すといった戦略が可能になり、資産形成のスピードが飛躍的に加速します。
一方で、独身でアッパーマス層に到達する人々も少なくありません。
彼らは扶養家族がいない分、支出をコントロールしやすく、高収入の専門職であれば収入の多くを自己投資や資産形成に振り向けることができます。
子供のいるファミリー世帯にとっては、教育費が資産形成の大きな障壁となり得ます。
特に、私立学校への進学や塾、習い事など、子供一人当たりにかかる教育費は数千万円に上ることもあり、これが家計を圧迫し、貯蓄のペースを鈍化させる大きな要因となります。
職業と年収:アッパーマス層を形成するキャリアパス
アッパーマス層の定義は資産額に基づきますが、その資産を築くための源泉は、言うまでもなく高い年収です。
年収と資産階層の間には、明確な正の相関関係が見られます。
| 世帯年収 | 金融資産3,000万円以上の世帯割合 |
| 300万円未満 | 5.9% |
| 300~500万円未満 | 9.9% |
| 500~750万円未満 | 12.9% |
| 750~1,000万円未満 | 18.1% |
| 1,000~1,200万円未満 | 25.5% |
| 1,200万円以上 | 37.4% |
(出典:金融広報中央委員会の調査データより作成)
この表が示すように、世帯年収が1,000万円を超えるとアッパーマス層以上の割合は急増し、1,200万円以上では3分の1以上の世帯が該当します。
このことから、アッパーマス層を目指す上での一つの目安として、世帯年収1,000万円以上がターゲットになると言えるでしょう。
アッパーマス層に多い職業は、主に以下のようなタイプに分類されます。
・インカムリッチ・プロフェッショナル:医師、弁護士、公認会計士、税理士など、高度な専門知識と国家資格を要する職業。
・大手企業の管理職・専門職:商社、金融、IT、メーカーなどの大企業で部長・課長クラスの役職に就いている人々。
・外資系企業の社員:日系企業に比べて給与水準が高い傾向にある外資系の金融、IT、コンサルティング、製薬会社などに勤務する人々。
・成功した起業家・中小企業経営者:自ら事業を興し、安定した収益を上げている人々。
・公務員(夫婦共働き):夫婦共に公務員である場合、安定した収入と手厚い福利厚生により、着実な資産形成が可能です。
アッパーマス層のリアルな生活レベル
統計データや職業プロファイルから浮かび上がるアッパーマス層の姿。
では、彼らの実際の生活はどのようなものなのでしょうか。
ここでは、住まいや車といったライフスタイルから、お金に関するリアルな悩みまで、その実態に迫ります。
住まい:持ち家か賃貸か?住宅ローンの実情
アッパーマス層にとって、「持ち家か賃貸か」という選択は、単なるライフスタイルの問題だけでなく、純金融資産の定義に直結する戦略的な判断となります。
彼らは都心や郊外の人気エリアで質の高い住宅を購入する経済力を持っていますが、多額の住宅ローンを組むことは、定義上、純金融資産を大きく減少させ、一時的にマス層へと階層が下がってしまうことを意味します。
このため、アッパーマス層の中には、あえて質の高い賃貸物件を選び、自己資金を住宅という固定資産に縛り付けるのではなく、株式や投資信託といった流動性の高い金融資産として保有し続けることを選ぶ人々も少なくありません。
この選択は、資産の成長機会を最大化したいという、金融リテラシーの高い層に特有の考え方を反映しています。
一方で、家族の安定や社会的信用を重視し、持ち家を選択する層ももちろん多数存在します。
その場合でも、彼らはローンの管理に非常に戦略的です。
頭金を多く入れる、繰り上げ返済を積極的に行うなどして、負債であるローンを可能な限り早期に、かつ効率的に圧縮しようと努めます。
車:どのような車種を選ぶ傾向にあるのか
アッパーマス層の車の選び方は、彼らの価値観を象徴しています。
それは「実用性を伴った上質さ」あるいは「見栄を張らない本物志向」と言い換えることができるでしょう。
彼らは高級車を購入する十分な資力を持っていますが、必ずしも誰もがステータスシンボルとしての高級外車を選ぶわけではありません。
人気が高いのは、トヨタのレクサスやアルファード、あるいはメルセデス・ベンツ、BMW、アウディといったドイツのプレミアムブランドのエントリーからミドルクラスのモデルです。
これらの車は、品質、安全性、信頼性が高く、リセールバリューも期待できるため、コストパフォーマンスを重視する彼らの合理的な判断に適っています。
超富裕層が趣味性の高いスーパーカーや希少なクラシックカーを複数台所有するのとは対照的に、アッパーマス層の車選びは、あくまで日常生活の質を高めるための、堅実で賢明な消費の一環として位置づけられているのです。
「アッパーマス層は大したことない」は本当か?その理由を深掘り
インターネット上では、「アッパーマス層なんて大したことない」という趣旨の意見が見られます。
純金融資産が3,000万円から5,000万円と聞けば、多くの人にとっては十分に裕福に思えますが、なぜ当事者やその周辺からはこのような声が上がるのでしょうか。
その背景には、いくつかの構造的な理由が存在します。
第一に、この資産額では完全な経済的自立(FIRE:Financial Independence, Retire Early)を達成するには不十分であるという現実があります。
例えば、年間4%の運用益で生活費を賄う「4%ルール」を適用した場合、資産5,000万円でも年間の生活費は200万円となり、税金などを考慮すると、労働収入なしで家族を養っていくのは困難です。
彼らの資産は、あくまで万が一の事態に備えるための強力なセーフティネットであり、労働から解放されるための切符ではないのです。
第二に、「ライフスタイル・インフレーション」の問題があります。
収入が増えるにつれて、住居のグレード、子供の教育環境、外食や旅行の頻度など、生活水準も自然と上昇していきます。
これにより支出が増大し、高い年収を得ていても、手元に残るお金は思ったほど多くない、という感覚に陥りがちです。
第三に、税金や社会保険料の負担が重くのしかかる「中間層のジレンマ」です。
彼らは高所得者として累進課税の最高税率に近い税負担を強いられる一方で、超富裕層が活用するような高度なタックスプランニングの恩恵は受けにくいポジションにいます。
稼いでもその多くが税金で引かれてしまうという感覚が、「豊かさを実感しにくい」一因となっています。
最後に、心理的な要因も大きいでしょう。
3,000万円の目標を達成すると、次の目標は自然と5,000万円(準富裕層)、そして1億円(富裕層)へと移っていきます。
常に上には上がいることを知っているため、達成感よりも、次なる目標への道のりの長さを意識してしまうのです。
お金に関する悩み:税金、教育費、老後への備え
アッパーマス層は経済的に余裕があるからこそ、特有のお金の悩みを抱えています。
最大の悩みの一つは、前述の通り「税金」です。
所得税や住民税だけでなく、株式投資などで得た利益にかかる税金も無視できません。
そのため、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇制度を最大限に活用し、いかに手取りを最大化するかという点に高い関心を持っています。
次に、子供がいる世帯にとっては「教育費」が大きな負担となります。
より良い教育環境を求めて私立の学校に通わせたり、海外留学をさせたりする場合、その費用は数千万円単位に及びます。
この教育費を捻出しながら、さらに資産を増やしていくことは、彼らにとって大きな課題です。
そして、意外に思われるかもしれませんが、「老後への不安」も根強く存在します。
現在の資産額で、インフレが進む将来においても豊かな生活を維持できるのか、長寿化によって資産が枯渇するリスクはないか、といったことを常に考えています。
彼らの資産は安心材料ではありますが、決して楽観視しているわけではなく、常に将来を見据えた計画的な資産管理を続けているのです。
アッパーマス層への道筋:資産形成の原理原則
アッパーマス層という階層は、一部の天才や幸運な人々だけが到達できる場所ではありません。
その多くは、資産形成の普遍的な原理原則を、長期間にわたって地道に実践してきた結果としてその地位を築いています。
ここでは、特定の金融商品を推奨することなく、その根底にある考え方を探ります。
収入と貯蓄のバランス:資産形成の基盤
資産形成の最も基本的な方程式は、(収入 − 支出) × 運用利回り × 時間 で表されます。
アッパーマス層に到達する人々は、この方程式の各要素を最適化することに長けています。
まず、専門性を高めたり、キャリアアップを図ったりすることで「収入」を最大化する努力を惜しみません。
しかし、それ以上に重要なのが「支出」のコントロール、すなわち高い「貯蓄率」の維持です。
アッパーマス層の多くは、収入の20%、30%といった高い割合を、天引きや自動積立などの仕組みを利用して、半ば強制的に貯蓄や投資に回しています。
これは、前述した「ライフスタイル・インフレーション」を意識的に抑制し、収入が増えても生活レベルを過度に上げないという強い自制心の表れです。
この「収入を増やす努力」と「高い貯蓄率の維持」という両輪を回し続けることが、資産形成の揺るぎない土台となります。
アッパーマス層から準富裕層へ:次のステップへの課題
純金融資産3,000万円を達成しアッパーマス層に入った後、次の目標となるのが5,000万円の壁を越えて準富裕層になることです。
そして、最終的な大きな目標として多くの人が意識するのが、1億円の富裕層です。
実は、ゼロから3,000万円を築く道のりよりも、5,000万円から1億円への道のりの方が、性質的に難しい側面があります。
なぜなら、このステージからは、単に給与収入から貯蓄する「足し算の資産形成」だけでは、到達に非常に長い時間がかかるからです。
求められるのは、今ある資産そのものが新たな富を生み出す「掛け算の資産形成」、すなわち本格的な資産運用の世界です。
資産規模が大きくなるにつれて、適切なアセットアロケーション(資産配分)の重要性が増し、リスク管理もより複雑になります。
本業で多忙な彼らにとって、資産運用に十分な時間と知識を割くことが難しくなるという課題も生じます。
この段階になると、複利の効果が資産成長のメインエンジンとなるため、いかに効率的かつ合理的な運用を長期にわたって継続できるかが、次のステージに進むための鍵を握るのです。
まとめ
本稿では、「アッパーマス層」という概念について、その定義から最新の統計データ、具体的な人物像、リアルな生活実態、そして国際的な比較まで、多角的に掘り下げてきました。
最後に、この記事から得られる重要なポイントを再確認し、読者の皆様が自身の目標設定にどのように活かせるかを考えていきましょう。
改めて、アッパーマス層の核心を要約します。
それは、「純金融資産3,000万円以上5,000万円未満を保有する世帯」であり、日本の全世帯の約10.35%を占める、いわば「お金持ちへの入り口」に立つ人々です。
彼らの多くは、40代から60代の働き盛りの専門職や管理職であり、高い収入を得ながらも規律ある生活を送り、長年にわたる地道な努力の末にその資産を築き上げてきました。
しかし、その資産は完全な経済的自由を保証するものではなく、税金、教育費、老後の生活といった現実的な悩みを抱えながら、次なるステージを目指している、というのがその実像です。
本稿で提示した様々なデータや分析は、単なる知識としてだけでなく、皆様自身の経済的な立ち位置を客観的に見つめ直すための「鏡」として活用することができます。
ご自身の年代の金融資産の中央値と比べて、現在の資産状況はどうでしょうか。
目標とする階層に到達している人々の年収や職業は、自身のキャリアプランを考える上でどのような示唆を与えてくれるでしょうか。
アッパーマス層という存在は、多くの人にとって、漠然とした憧れではなく、具体的な数字で示された達成可能な目標となり得ます。
ここまでお読みいただき、アッパーマス層の「現在地」をご理解いただけたかと思います。
もし、この先に待ち受ける「5,000万円の壁」の正体や、多くの人が陥る心理的な罠、そして資産を次のステージへ進めるための思考法については、ぜひ完全版をご覧ください。
さらに深い世界へご案内します。

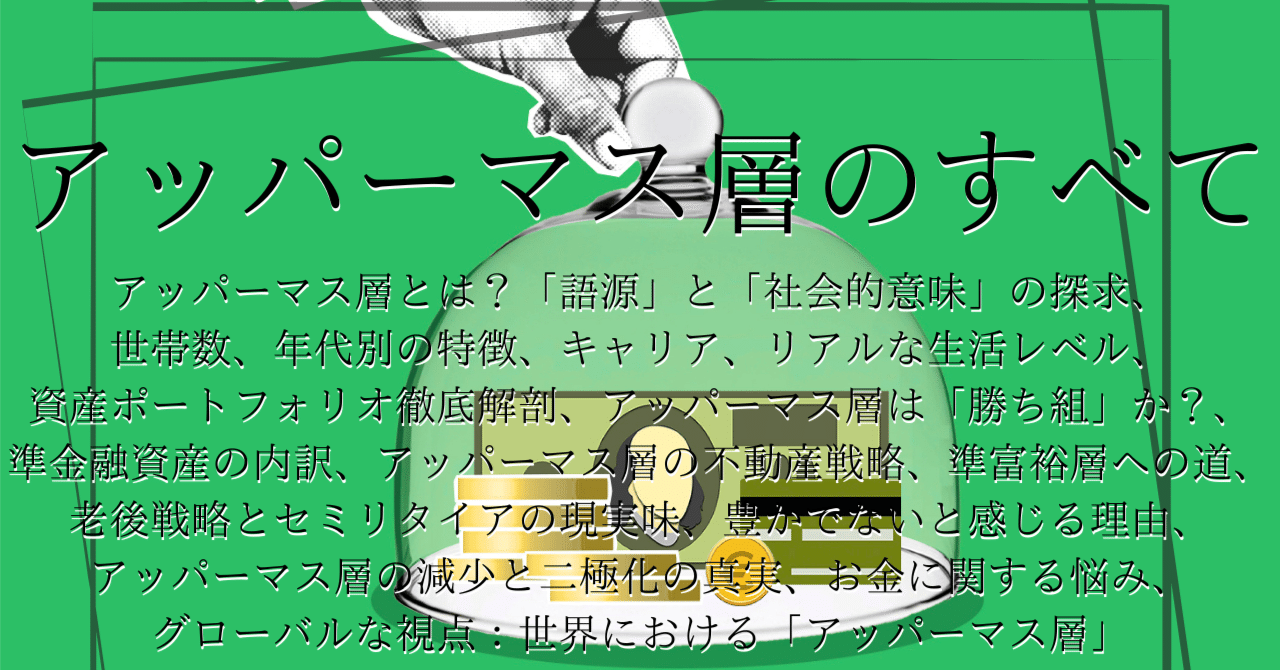
関連記事を読むことでさらに世界の有名投資家達の思考や人物像を深く知ることができます。

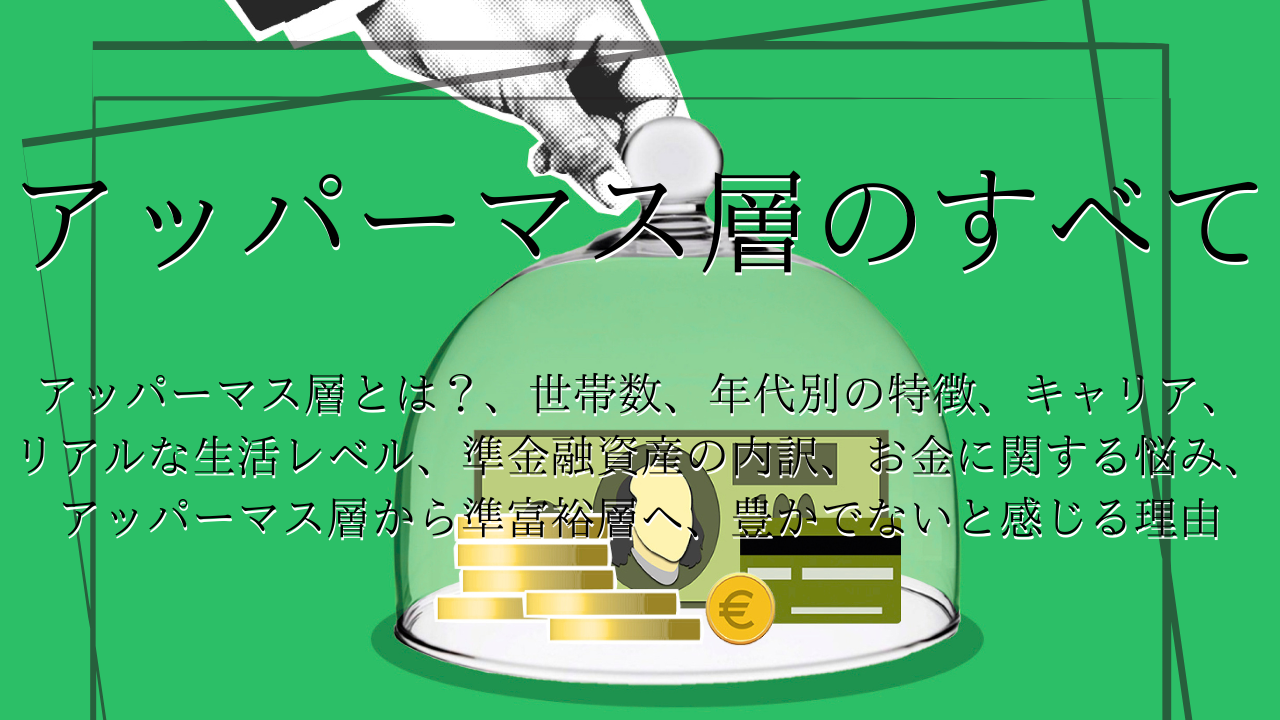




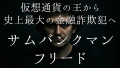

コメント