Masakiです。
「自分は日本のなかで、どのくらいの立ち位置にいるのだろうか」
そう考えたことはありませんか。
メディアでは「富裕層」や「FIRE」といった言葉が頻繁に登場し、華やかなライフスタイルが紹介される一方で、多くの人々は日々の生活費や将来への漠然とした不安を抱えています。
自分の年収や貯蓄額は、果たして「普通」なのでしょうか?
このままの生活を続けて、将来の資産形成は本当に大丈夫なのでしょうか?
この記事は、そうした疑問や不安を抱えるあなたのために書かれました。
私たちは、日本の全世帯の約8割を占める「マス層」という巨大なグループに焦点を当てます。
この記事を最後まで読めば、あなたは以下のことを明確に理解できるでしょう。
・マス層の正確な定義と、あなたがどの階層に属するのか。
・最新の公式データに基づいた、日本の資産ピラミッドの全体像と構造。
・マス層のリアルな年収、貯蓄、そして住宅ローンの実態。
・マス層の消費行動や価値観、そして将来に対する意識。
・マス層から抜け出し、一つ上の階層である「アッパーマス層」を目指すための具体的な戦略。
本記事は、野村総合研究所(NRI)の調査をはじめとする信頼性の高い国内外のレポートや公的統計を網羅的に分析し、日本の経済的な階層構造を徹底的に解剖します。
これは単なるデータの羅列ではありません。
あなたが自身の現在地を客観的に把握し、未来に向けた賢明な一歩を踏み出すための「羅針盤」となるはずです。
さあ、日本の大多数である「マス層」の真実を探る旅を始めましょう。

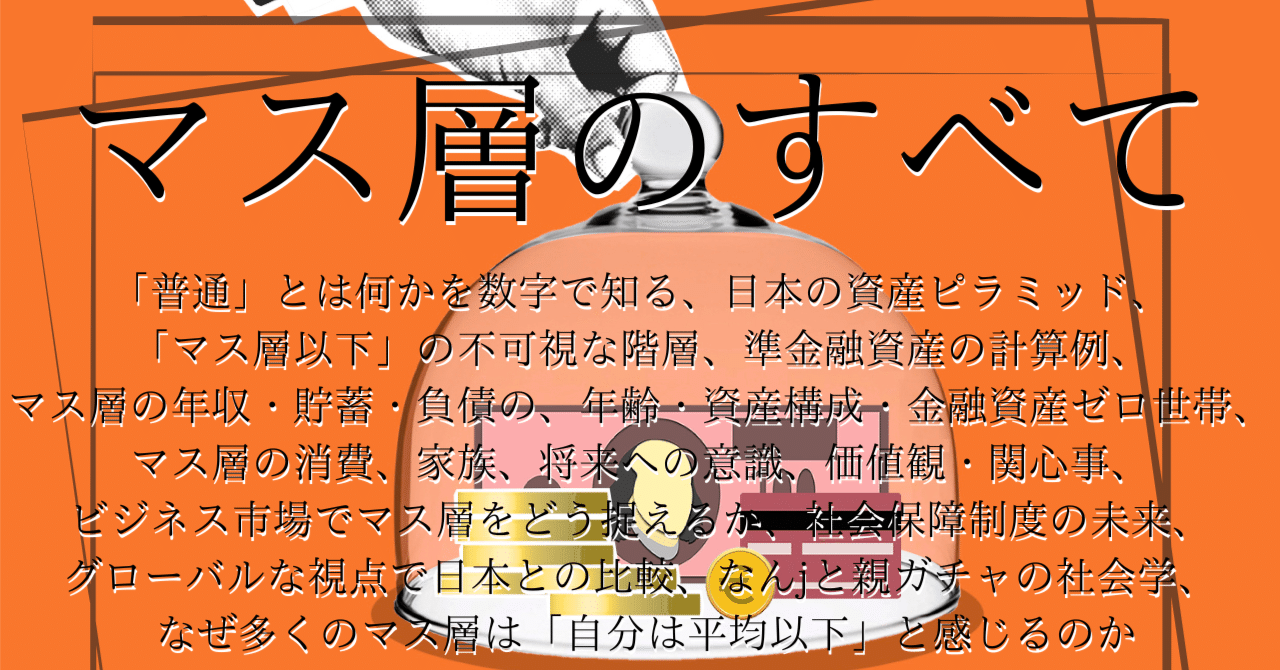
第1部:マス層の定義と全体像 ― 「普通」とは何かを数字で知る
日本の大多数を占めるとされる「マス層」。
この言葉を理解することが、日本の経済構造と自身の立ち位置を把握する第一歩となります。
この部では、マス層の明確な定義からその語源、そして対義語までを掘り下げ、「普通」という概念を客観的な数字で捉え直します。
「マス層」という言葉は、株式会社野村総合研究所(NRI)が定期的に発表している日本の富裕層に関する調査レポートの中で定義されています。
この調査では、世帯が保有する資産を基に、社会全体を5つの階層に分類しており、このフレームワークが日本の資産階層を語る上での事実上の標準となっています。
NRIの定義によれば、「マス層」とは、純金融資産保有額が3,000万円未満の世帯を指します。
そして、このマス層が日本の世帯の大多数を構成しているのです。
全体像を把握するために、NRIが定義する5つの階層すべてを見てみましょう。
・超富裕層:純金融資産5億円以上の世帯
・富裕層:純金融資産1億円以上5億円未満の世帯
・準富裕層:純金融資産5,000万円以上1億円未満の世帯
・アッパーマス層:純金融資産3,000万円以上5,000万円未満の世帯
・マス層:純金融資産3,000万円未満の世帯
このように、資産のピラミッドは頂点に位置する超富裕層から、最も広い基盤を形成するマス層まで、明確な金額によって区分されています。
アッパーマス層は、しばしば「お金持ちの入り口」と表現され、マス層から一つ抜け出した階層として認識されています。
NRIの階層分類を理解する上で、最も重要なキーワードが「純金融資産」です。
この言葉の意味を正確に把握しなければ、自身の資産状況を正しく評価することはできません。
純金融資産とは、世帯が保有する「金融資産の合計額」から「負債の合計額」を差し引いた金額を指します。
これは、すべての借金を返済した後に、手元に純粋に残る金融資産がいくらあるかを示す指標であり、家計の真の経済的な健全性や余力を測るものと言えます。
具体的に、計算に含まれる「金融資産」と「負債」は以下の通りです。
金融資産に含まれるもの:
・預貯金(普通預金、定期預金など)
・株式、債券、投資信託
・一時払い生命保険、個人年金保険など(解約返戻金があるもの)
・iDeCoや企業型DCなどの年金資産の現在評価額
負債に含まれるもの:
・住宅ローン
・自動車ローン
・カードローン、キャッシング
・奨学金など
ここで非常に重要なのが、「総資産」との違いです。
総資産は、金融資産に加えて、自宅(不動産)や自動車、貴金属といった「実物資産」も含めたすべての財産を指します。
一方で、純金融資産は、あくまで流動性(現金化のしやすさ)が高い金融資産のみを対象とし、そこから負債を引いたものです。
例えば、ある世帯が5,000万円の住宅を所有し、4,000万円の住宅ローンを組んでいるとします。
さらに、預貯金が500万円ある場合、この世帯の資産状況は以下のようになります。
総資産:5,500万円(不動産5,000万円 + 預貯金500万円)
純金融資産:マイナス3,500万円(預貯金500万円 – 住宅ローン4,000万円)
この例が示すように、高価なマイホームを持っていても、多額のローンがあれば純金融資産はマイナスになることがあります。
NRIが所得や総資産ではなく、純金融資産を基準にしているのは、それが個人の経済的な自由度や、投資や高額消費に向けられる「本当に使えるお金」を最も的確に表す指標だからです。
この指標を用いることで、高収入でも多額の負債を抱える世帯と、収入はそこそこでも着実に資産を築いている世帯とを、より実態に即して評価することが可能になるのです。
「マス層」の「マス」とは、一体どこから来た言葉なのでしょうか。
その語源は、英語の「mass」にあります。
「mass」は、ラテン語で「塊」や「固まり」を意味する「massa」に由来し、もともとは「多数」「大衆」「集団」といった意味を持つ言葉です。
この言葉は、特定の個人やグループではなく、不特定多数の広範な人々を指す際に用いられます。
例えば、テレビや新聞、ラジオといった媒体は、大衆に向けて情報を発信することから「マスメディア(mass media)」と呼ばれます。
同様に、特定の顧客層に絞らず、市場全体を対象として画一的なメッセージで商品を訴求するマーケティング手法は「マスマーケティング(mass marketing)」として知られています。
金融資産の階層分類における「マス層」も、この本来の意味に沿っています。
つまり、日本の人口構成において、統計的に最も多数を占める「大衆的な」階層であることを示しているのです。
マス層の反対の概念は何かを考えると、その立ち位置がより明確になります。
対義語は、二つの異なる視点から捉えることができます。
一つ目は、金融資産の階層における直接的な対義語です。
NRIの分類ピラミッドにおいて、マス層(純金融資産3,000万円未満)の対極に位置するのは、純金融資産1億円以上の「富裕層」および5億円以上の「超富裕層」です。
これらは、資産規模という明確な基準において、マス層とは対照的な存在と言えます。
二つ目は、マーケティングや社会学的な文脈での対義語です。
「マス(大衆)」の反対は、「ニッチ(隙間)」や「エリート(選良)」と考えることができます。
マスマーケティングが市場全体を狙うのに対し、「ニッチマーケティング」は特定の趣味やニーズを持つ小規模な顧客層に深く刺さるアプローチを取ります。
また、社会的な文脈では、「エリート層」が持つ専門性や影響力、文化的資本などが、「マス層」の持つ普遍性や平均性とは対照的な概念として扱われることがあります。
政治の世界で「ポピュリズム(大衆迎合主義)」という言葉が、既成の権力構造やエリート層を批判し、一般大衆(マス)に直接訴えかけるスタイルを指すのも、この「マス対エリート」という構造の表れと言えるでしょう。
これらの対義語を理解することで、マス層が単に資産が少ない層というだけでなく、社会や市場において「最大多数派」という役割を担っていることが見えてきます。
第2部:日本の資産ピラミッド:最新データで見る階層の割合と構造
マス層の定義を理解したところで、次はその実態を最新のデータで見ていきましょう。
野村総合研究所(NRI)が発表した最新の推計を基に、日本の資産ピラミッドがどのような構造になっているのか、そして時系列でどのように変化してきたのかを詳細に分析します。
このデータは、日本社会の富の分布と、私たち一人ひとりが置かれている経済的な現実を映し出す鏡です。
NRIが2025年に発表した最新のレポートによると、2023年時点での日本の総世帯数は約5,580万世帯と推計されています。
このうち、各階層に属する世帯数と、全体に占める割合は以下のようになっています。
・超富裕層(5億円以上):11.8万世帯(約0.2%)
・富裕層(1億円以上5億円未満):153.5万世帯(約2.8%)
・準富裕層(5,000万円以上1億円未満):403.9万世帯(約7.2%)
・アッパーマス層(3,000万円以上5,000万円未満):576.5万世帯(約10.3%)
・マス層(3,000万円未満):4,424.7万世帯(約79.3%)
この数字が示す最も重要な事実は、マス層が日本の全世帯の約8割を占める、圧倒的なマジョリティであるということです。
一方で、富裕層と超富裕層を合わせた、いわゆる「億り人」の世帯は合計で165.3万世帯となり、全体の約3.0%に過ぎません。
多くの人がメディアを通じて富裕層の存在を身近に感じるかもしれませんが、統計的にはごく一部の存在であることがわかります。
次に、各階層がどれだけの資産を保有しているのかを見てみましょう。
世帯数の割合と資産のシェアを比較することで、日本の富の集中度が明らかになります。
2023年時点での各階層が保有する純金融資産の総額は以下の通りです。
超富裕層:135兆円
富裕層:334兆円
準富裕層:333兆円
アッパーマス層:282兆円
マス層:711兆円
これらの数字を合計すると、日本の世帯が保有する純金融資産の総額は約1,795兆円となります。
ここから見えてくるのは、世帯数の割合と資産シェアの間に存在する大きなギャップです。
全世帯の約79.3%を占めるマス層が保有する資産は、全体の約39.6%にとどまっています。
一方で、全世帯のわずか3.0%に過ぎない富裕層と超富裕層は、合計で469兆円、全体の約26.1%もの資産を保有しているのです。
このデータは、日本の資産格差の構造を如実に示しています。
人口の大多数を占めるマス層と、ごく一部の富裕層との間には、保有する資産の規模において大きな隔たりが存在するのです。
この構造は、経済政策やマーケティング戦略を考える上で、極めて重要な意味を持ちます。
| 階層 | 純金融資産保有額 | 世帯数 | 全体に占める割合 | 純金融資産総額 | 全体に占めるシェア |
| 超富裕層 | 5億円以上 | 11.8万世帯 | 0.2% | 135兆円 | 7.5% |
| 富裕層 | 1億円以上5億円未満 | 153.5万世帯 | 2.8% | 334兆円 | 18.6% |
| 準富裕層 | 5,000万円以上1億円未満 | 403.9万世帯 | 7.2% | 333兆円 | 18.6% |
| アッパーマス層 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 576.5万世帯 | 10.3% | 282兆円 | 15.7% |
| マス層 | 3,000万円未満 | 4,424.7万世帯 | 79.3% | 711兆円 | 39.6% |
| 合計 | – | 5,570.4万世帯 | 100.0% | 1,795兆円 | 100.0% |
資産ピラミッドの構造は、常に一定ではありません。
経済状況や市場の動向によって、その形は変化します。
特に、直近のデータを見ると、興味深い動きが観察されます。
2021年から2023年にかけての2年間で、各階層の世帯数は以下のように変動しました。
準富裕層:325.4万世帯 → 403.9万世帯(+78.5万世帯)
アッパーマス層:726.3万世帯 → 576.5万世帯(-149.8万世帯)
マス層:4213.2万世帯 → 4424.7万世帯(+211.5万世帯)
このデータから読み取れる最も衝撃的な変化は、アッパーマス層の世帯数が約150万世帯も大幅に減少したことです。
では、その減少した世帯はどこへ移動したのでしょうか。
答えは、その上下の階層にあります。
準富裕層とマス層の世帯数が、それぞれ大きく増加しているのです。
この現象は、資産ピラミッドの中間部分が痩せ細る「中間層の空洞化」あるいは「富の二極化」を示唆しています。
アッパーマス層の一部は、株価上昇などの恩恵を受けて資産を増やし、準富裕層へとステップアップすることに成功しました。
NRIのレポートでも、富裕層・超富裕層の増加要因として、株式などのリスク性資産の価値上昇が挙げられています。
一方で、それ以上に多くの世帯が、物価上昇や経済的な不安定さの中で資産を維持できず、マス層へと転落してしまった可能性が考えられます。
このことは、かつて安定的とされた「中間層」が、上へ向かうか下へ向かうかの岐路に立たされており、その安定性が揺らいでいる現実を浮き彫りにしています。
資産運用に成功した者とそうでない者との間で、格差が拡大している構造が見て取れるのです。
キーワードとして頻繁に検索される「マス層の下」や「マス層 底辺」という言葉は、マス層の中でも特に経済的に厳しい状況にある人々への関心を示しています。
マス層の定義は「純金融資産3,000万円未満」であり、これには当然、純金融資産がゼロ、あるいはマイナスの世帯も含まれます。
純金融資産がマイナスとは、前述の通り、預貯金や株式といった金融資産の総額よりも、住宅ローンや奨学金などの負債総額の方が多い状態を指します。
これは決して珍しいことではありません。
総務省統計局の家計調査などの公的データを見ると、特に世帯主の年齢が50歳未満の階級では、純貯蓄額(純金融資産とほぼ同義)がマイナス、つまり「負債超過」となっていることがわかります。
例えば、40代の世帯では負債を抱えている割合が約69%と最も高くなっています。
これは、多くの30代、40代の世帯が、住宅購入のために多額のローンを組み、その返済を続けているためです。
彼らは安定した収入を得ていても、純金融資産の観点から見れば「マス層の下」に位置づけられることになります。
したがって、「マス層の下」とは、単に貯蓄が少ない人々だけでなく、将来のために大きな負債を抱えながら生活を築いている若い世代や働き盛りの世代も含む、非常に広範な層を指していると理解することができます。
第3部:グローバルな視点から見た日本のマス層
日本の資産ピラミッドの構造を理解した上で、次にその姿を世界の舞台に置いてみましょう。
国際的な比較を行うことで、日本のマス層が置かれている状況や、日本の富の構造が持つユニークな特徴がより鮮明になります。
スイスの金融大手UBSが発表する「グローバル・ウェルス・レポート」などの国際的な調査を基に、日本の立ち位置を客観的に分析します。
UBSの最新レポートは、世界の成人人口を資産額(米ドル建て)で4つの階層に分けた「グローバル・ウェルス・ピラミッド」を提示しています。
その構造は以下の通りです。
・資産100万ドル超:世界の成人人口の約1.6%を占め、世界の総資産の約48.1%を保有。
・資産10万ドル~100万ドル:世界の成人人口の約16.4%を占め、世界の総資産の約39.2%を保有。
・資産1万ドル~10万ドル:世界の成人人口の約40.7%を占め、世界の総資産の約12.1%を保有。
・資産1万ドル未満:世界の成人人口の約41.3%を占め、世界の総資産のわずか約0.6%を保有。
このピラミッドが示すのは、日本と同様に、世界レベルでも富がごく一部の人々に極端に集中しているという現実です。
成人人口の2%にも満たない富裕層が、世界の富の半分近くを独占しているのです。
日本のマス層の多くは、このグローバルな基準で言えば「1万ドル~10万ドル」の層に該当すると考えられます。
この層は世界的に見ても人口のボリュームゾーンであり、グローバルな中間層と見なすことができます。
ここで一つ、興味深い事実があります。
それは、日本国内で「富裕層」とされる人々の多くが、国際的な基準では必ずしも富裕層とは見なされない可能性があるということです。
この違いは、定義の基準に起因します。
日本の定義(NRI):
・富裕層:純金融資産1億円以上
・超富裕層:純金融資産5億円以上
グローバル基準(キャップジェミニなど):
・富裕層(HNWI):投資可能資産100万米ドル以上
・超富裕層(UHNWI):投資可能資産3000万米ドル以上
仮に1ドル=150円で換算すると、グローバル基準の富裕層(HNWI)は資産1億5,000万円以上、超富裕層(UHNWI)は資産45億円以上となります。
日本の基準と比較すると、特に超富裕層の定義には約9倍もの大きな隔たりがあることがわかります。
これは、日本で「超富裕層」と分類される資産5億円の人も、グローバルな文脈ではまだその下の階層に位置づけられることを意味します。
この定義の違いは、日本の富の構造を考える上で重要な示唆を与えます。
日本は、世界的な基準で見た超富裕層の数は相対的に少ない一方で、準富裕層や富裕層の下位層といった「アッパーミドル層」が厚い構造になっている可能性があります。
つまり、資産ピラミッドの頂点は他国ほど鋭く尖っていないものの、その少し下の層が比較的広がりを持っているという特徴が考えられるのです。
| 階層 | 日本の定義(NRI) | グローバル基準の目安 | 備考 |
| 富裕層 (HNWI) | 純金融資産1億円以上 | 投資可能資産100万ドル以上(約1.5億円) | 日本の基準はグローバル基準より低い |
| 超富裕層 (UHNWI) | 純金融資産5億円以上 | 投資可能資産3000万ドル以上(約45億円) | グローバル基準は日本の基準を大幅に上回る |
日本の資産格差は、世界的に見てどのようなレベルにあるのでしょうか。
この問いには、二つの側面から答える必要があります。
一つは「資産格差」、もう一つは「所得格差」です。
まず「資産格差」について見ると、日本は他の主要先進国と比較して、格差が比較的小さい国とされています。
資産の不平等度を示す「ジニ係数」という指標では、日本の値は北米などの地域よりも低く、富の分布がより平準的であることを示しています。
また、資産の「平均値」と「中央値」を比較すると、格差の大きい国では平均値が中央値を大きく上回る傾向がありますが、日本はこの差が比較的小さいことも、資産格差が相対的に小さいことの傍証となります。
これは、多くの高齢者世帯が持ち家や預貯金といった資産を保有していることが、全体の資産分布を平準化しているためと考えられます。
しかし、一方で「所得格差」に目を向けると、様相は一変します。
税金や社会保障による再分配後の可処分所得で見た場合、日本の所得格差はOECD(経済協力開発機構)加盟国の平均よりも大きく、相対的貧困率も高い水準にあります。
これは、日本の所得再分配機能が他の先進国に比べて弱いことを示唆しています。
ここに、日本のマス層が直面する大きな課題が隠されています。
つまり、日本は「資産は比較的平等だが、所得の格差は拡大しつつある」というパラドックスを抱えているのです。
親世代が築いた資産によって国全体の資産格差は小さく見えても、現役世代であるマス層は、非正規雇用の拡大や賃金の伸び悩みといった厳しい労働環境に直面し、所得面での格差と将来への不安を強く感じています。
この資産と所得のねじれこそが、現代日本のマス層のリアルな姿を映し出していると言えるでしょう。
第4部:マス層のリアルな経済状況:年収、貯蓄、負債の実態
日本の大多数を占めるマス層。
その定義や社会的な位置づけを理解した次は、彼らの懐事情、つまり日々の経済活動の現実に深く踏み込んでいきます。
年収はいくらで、どれくらいの貯蓄があり、どのような負債を抱えているのか。
公的な統計データを基に、マス層のリアルな経済状況を解き明かします。
マス層の経済状況を考える上で、まず押さえるべきは年収の実態です。
ここで重要なのは、「平均値」と「中央値」の違いを理解することです。
国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、日本の給与所得者の平均年収は約460万円です。
しかし、この数字には一部の高額所得者が平均値を引き上げているという「平均値の罠」が潜んでいます。
より実態に近いのは、所得の低い人から高い人までを順番に並べたときに、ちょうど真ん中にくる人の値を示す「中央値」です。
各種調査によると、日本の年収中央値は380万円から420万円程度とされており、平均値よりも数十万円低いことがわかります。
さらに所得の分布を見ると、最も多い所得層は「300万円超400万円以下」であり、平均所得である460万円以下の人が全体の6割以上を占めています。
つまり、年収400万円前後というのが、日本のマス層における一つの典型的な姿と言えるでしょう。
この年収水準で日々の生活を送り、将来のための貯蓄や投資、そして子どもの教育費などを賄っているのが、日本のマジョリティなのです。
マス層の資産状況は、ライフステージによって大きく異なります。
特に、住宅購入や子育てといった大きなライフイベントが集中する30代、40代の経済状況は、マス層の実態を理解する上で非常に重要です。
総務省の調査データは、この世代の厳しい現実を示しています。
世帯主が50歳未満の世帯では、貯蓄現在高から負債現在高を差し引いた「純貯蓄額」がマイナス、つまり「負債超過」の状態にあることが一般的です。
特に負債を保有している世帯の割合は40代で最も高く、約7割に達します。
この負債の大部分を占めるのが、住宅ローンです。
多くの30代、40代は、マイホームという大きな資産を手に入れるために、数千万円単位の負債を抱え、長期にわたる返済を続けています。
彼らは社会の中核を担う働き盛りの世代でありながら、純金融資産という観点から見れば、資産形成のスタートライン、あるいはそれ以前のマイナスの地点に立っているのです。
この「負債を抱えながら資産を築いていく」というプロセスこそが、マス層の典型的な経済的軌道と言えます。
マス層を構成するのは、どのような職業の人々なのでしょうか。
特定の職業と資産階層を直接結びつける詳細なデータは限られていますが、労働市場全体の統計からその姿を推測することができます。
日本の労働人口の大多数は、企業などに雇用されるサラリーマンです。
厚生労働省の調査によれば、正社員の割合が高い職種としては、「事務的な仕事」「専門的・技術的な仕事」「運輸・通信の仕事」などが挙げられます。
一方で、国税庁の調査から業種別の平均給与を見ると、大きなばらつきがあることがわかります。
例えば、「電気・ガス・熱供給・水道業」や「金融業・保険業」といった業種の平均給与は高い水準にありますが、「宿泊業・飲食サービス業」などは著しく低い水準にとどまっています。
マス層の多くは、こうした業種の中で、平均的、あるいはそれ以下の給与水準で働く人々によって構成されていると考えられます。
つまり、特定の専門職や管理職というよりは、社会を支える様々な職場で働く、ごく一般的な会社員や公務員、専門職従事者がマス層の中核をなしているのです。
マス層の家計に最も大きな影響を与える要素、それが住宅ローンです。
多くの世帯にとって、人生で最大の買い物であり、最大の負債となります。
住宅ローンを組む際に一つの目安となるのが、物件価格が年収の何倍にあたるかを示す「年収倍率」です。
住宅金融支援機構の最新調査によると、この年収倍率の全国平均は、物件の種類によって異なりますが、おおむね6倍から7.5倍となっています。
例えば、新築の土地付き注文住宅では7.5倍、新築マンションでは7.0倍です。
これは、年収500万円の世帯が、平均して3,500万円から3,750万円程度の物件を購入していることを意味します。
しかし、借りられる金額と、無理なく返せる金額は異なります。
金融機関の審査では、年収に占める年間返済額の割合である「返済負担率」が重視されます。
多くの金融機関では、この率の上限を30%から35%程度に設定していますが、家計に余裕を持って返済を続けるためには、20%から25%以内に抑えるのが望ましいとされています。
近年の不動産価格の高騰と、伸び悩む賃金という状況の中で、多くのマス層世帯は、高い年収倍率と35年という長期のローンを組むことで、マイホームの夢を実現しています。
しかし、それは同時に、数十年にわたって純金融資産が低い、あるいはマイナスの状態が続くことを意味します。
彼らの家計は、金利の変動や失業といったリスクに対して脆弱であり、この住宅ローンという大きな負債が、マス層からアッパーマス層への移行を困難にする最大の要因の一つとなっているのです。
| 年収 | 借入額の目安(年収の5倍) | 月々の返済額(返済負担率) | 借入額の目安(年収の7倍) | 月々の返済額(返済負担率) |
| 300万円 | 1,500万円 | 約4.2万円(16.7%) | 2,100万円 | 約5.8万円(23.3%) |
| 400万円 | 2,000万円 | 約5.6万円(16.7%) | 2,800万円 | 約7.8万円(23.3%) |
| 500万円 | 2,500万円 | 約6.9万円(16.7%) | 3,500万円 | 約9.7万円(23.3%) |
| 600万円 | 3,000万円 | 約8.3万円(16.7%) | 4,200万円 | 約11.7万円(23.3%) |
| 800万円 | 4,000万円 | 約11.1万円(16.7%) | 5,600万円 | 約15.5万円(23.3%) |
| 1,000万円 | 5,000万円 | 約13.9万円(16.7%) | 7,000万円 | 約19.4万円(23.3%) |
第5部:マス層のライフスタイルと価値観:消費、家族、将来への意識
経済的な側面からマス層の実態を明らかにしたところで、次はその内面、つまりライフスタイルや価値観に目を向けてみましょう。
彼らは何にお金を使い、何を大切にし、未来に対して何を思い描いているのでしょうか。
各種の生活者調査から、日本の「普通の人々」の意識の核心に迫ります。
マス層の消費行動を特徴づけるキーワードは「堅実」と「コストパフォーマンス」です。
将来への不安や可処分所得の伸び悩みから、衝動買いを避け、本当に価値のあるもの、長く使えるものを見極めて購入する傾向が強まっています。
ファッションやアパレルの分野では、この傾向が顕著に表れます。
高級ブランド品を追い求めるのではなく、ユニクロに代表されるような高品質なファストファッションや、スーパーマーケットの衣料品など、手頃な価格で実用的な商品が支持されています。
購入に至るプロセスも慎重です。
SNSや比較サイトで情報を入念に収集し、実際に店舗で試着してから購入を決めるなど、失敗を避けるための手間を惜しみません。
一方で、ただ節約志向なだけではありません。
近年注目される「界隈消費」という現象は、マス層の消費行動のもう一つの側面を示しています。
これは、アニメやアイドル、特定のファッションスタイルといった共通の趣味や価値観を持つ「界隈(コミュニティ)」の中で、帰属意識を高めるためにお金を使うという行動です。
マス層は、自分のアイデンティティを表現し、仲間との繋がりを確認できる対象には、惜しまず投資する傾向があるのです。
マス層が日々の消費を切り詰める一方で、比較的大きな支出を厭わない分野があります。
それが、子どもの教育です。
我が子に良い教育を受けさせ、より良い未来を歩んでほしいという願いは、多くの親に共通するものです。
しかし、その実現には大きな経済的負担が伴います。
特に、都市部で過熱する私立中学の「お受験」は、世帯の経済力と密接に結びついています。
文部科学省の調査によると、私立中学校に通う子どものいる世帯の約9割が、世帯年収600万円以上であり、さらにそのうちの4割以上は年収1,200万円以上の世帯で占められています。
この事実は、私立中学への進学が、マス層の平均的な年収の家庭にとっては極めてハードルが高いことを示しています。
高額な学費に加え、小学校中学年から通うことになる学習塾の費用も家計に重くのしかかります。
多くのマス層の家庭にとって、教育への投資は家計における最優先事項の一つでありながら、同時に他の消費を圧迫し、家計の柔軟性を奪う大きな要因となっています。
この「教育格差」は、親の経済力が子どもの将来を左右しかねないという、現代日本社会が抱える深刻な課題を象生しており、マス層の親たちの大きな悩みの一つとなっています。
マス層の価値観やライフスタイルを理解する上で避けて通れないのが、将来、特に老後に対する根強い不安です。
この不安を社会現象として可視化したのが、2019年に大きな話題となった「老後2000万円問題」でした。
これは、金融庁の審議会報告書がきっかけとなり、「公的年金だけに頼っていては、老後の生活資金が約2,000万円不足する」というメッセージとして社会に広まったものです。
この2,000万円という数字の妥当性については様々な議論がありますが、この問題が多くの人々の心に響いたのは、それがマス層が漠然と抱いていた不安を具体的な金額として突きつけたからです。
少子高齢化が進む中で公的年金の先行きは不透明であり、退職金制度もかつてほど手厚くはありません。
このような状況下で、多くのマス層は「自分たちの老後は、自分たちで備えなければならない」という強い意識を持つようになりました。
この不安が、彼らの堅実な消費行動や、節約志向の根底に流れています。
そして、この意識の変化は、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった、税制優遇のある資産形成制度への関心の高まりにも繋がっています。
マス層は、将来への不安を原動力に、少しずつでも資産形成へと歩みを進め始めているのです。
現代のマス層は、多様なチャネルを駆使して情報を収集しています。
特にZ世代などの若い層では、購買行動に至るまでの情報収集プロセスが複雑化しています。
彼らが商品やサービスに興味を持つきっかけは、テレビCMや雑誌といった従来のマスメディアだけでなく、SNS上の投稿やレビュー、インフルエンサーからの情報、そして友人や家族からの口コミなど、多岐にわたります。
特に、信頼性の高い情報源として重視されるのが、身近な人々からのリアルな評価です。
一方で、広告に対しては比較的冷静な視線を向けており、内容が誇張されていると感じたり、具体的なデータが不足している広告は信頼されにくい傾向にあります。
このことは、企業がマス層にアプローチする際には、一方的な情報発信ではなく、信頼できる第三者からの評価や、透明性の高い情報提供が重要であることを示唆しています。
マス層は、もはや受動的な情報の受け手ではなく、自ら能動的に情報を取捨選択し、比較検討する賢い消費者へと進化しているのです。
結論:マス層の理解を、自己の成長と社会の発展に繋げるために
本記事では、日本の全世帯の約8割を占める「マス層」について、その定義から資産構造、ライフスタイル、そして未来への道筋までを、国内外の膨大なデータを基に徹底的に解剖してきました。
この記事で、ご自身の立ち位置が客観的に見えてきたのではないでしょうか。
しかし、私たちが生きるこの社会の構造は、さらに複雑です。
もしあなたが「自分の生活実感と、世の中の『平均』がズレている」と感じるなら、その感覚は正しいのかもしれません。
完全版では、この無料記事では触れられなかった、さらに深い領域に踏み込みます。

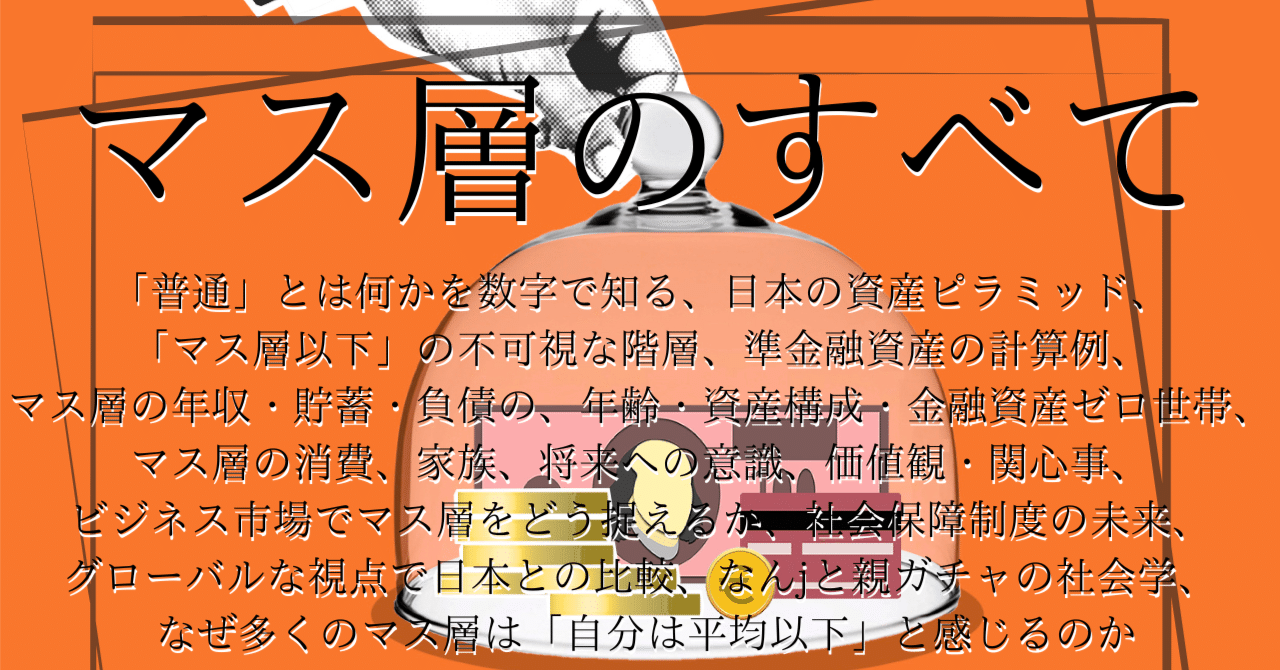
関連記事を読むことでさらに世界の有名投資家達の思考や人物像を深く知ることができます。

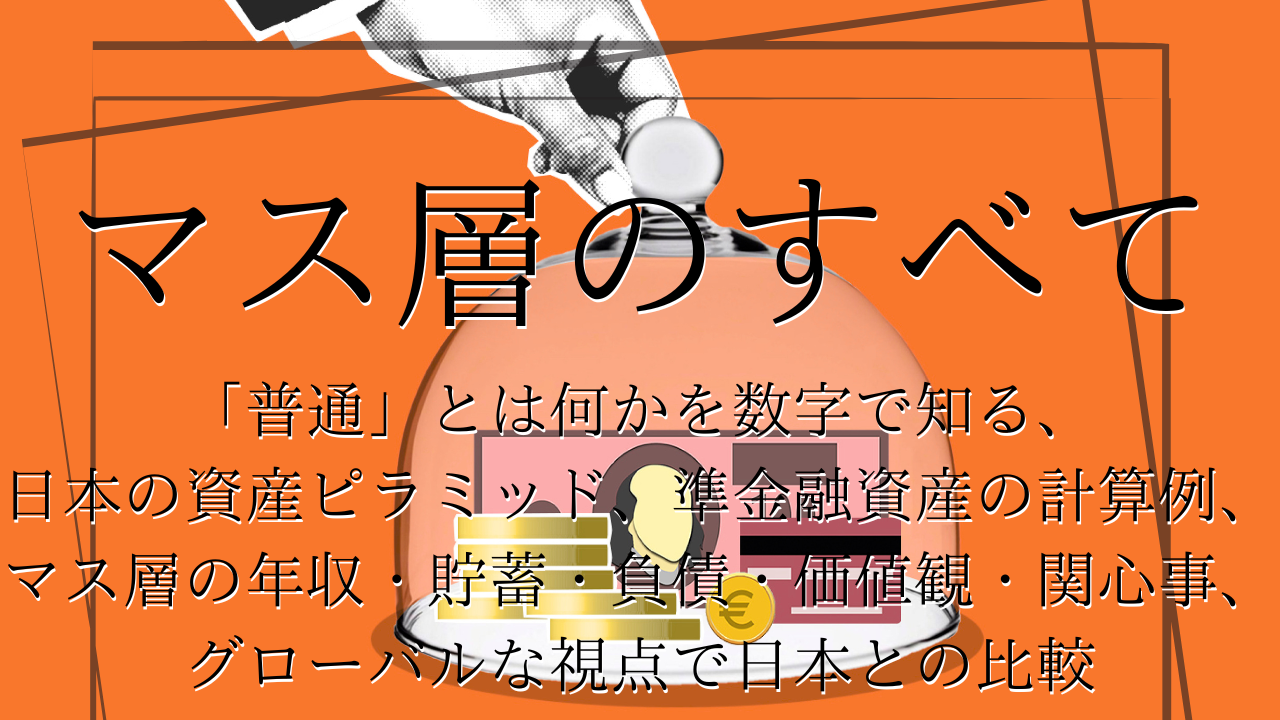





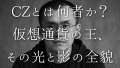
コメント