※本記事は投資助言を行うものではなく、参考情報としてご利用ください。
Masakiです。
インデックスファンドにも様々な種類がありますが、その中でもよく目にするのが「オルカン」でしょう。
オルカンとは何か?基本構造の理解
オルカン(オール・カントリー)は、世界中の株式市場に分散投資するインデックス型の投資信託です。
三菱UFJ国際投信が運用し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(MSCI ACWI)と呼ばれる世界株式指数に連動する成果を目指しています。
この1本のファンドで、日本を含む先進国23か国と新興国24か国、合計47か国の株式に幅広く投資できるのが特徴です。
ファンドの中身は株式約2,600~3,000銘柄におよび、時価総額加重型のインデックス運用により、実質的に「世界全体の株式市場」をほぼ丸ごと保有する形となります。
オルカンはアクティブ運用ではなく指数連動を目指すインデックスファンドであり、ファンドマネージャーが個別株を裁量で売買することなく、MSCI ACWIというベンチマーク通りにポートフォリオを構築・維持します。
具体的には、オルカンはファンド・オブ・ファンズ形式で運用されており、国内株式インデックス・マザーファンド、先進国株式(日本除く)インデックス・マザーファンド、新興国株式インデックス・マザーファンドの3つのマザーファンドを通じて世界株式に投資しています。
各マザーファンドの組入比率はMSCI ACWIの国別構成比に合わせて調整されており、指数の変化に応じて定期的にリバランス(比率調整)が行われます。
その結果、オルカンの基準価額の値動きはMSCI ACWI(円換算ベース、配当込み)とほぼ同じになるよう設計されています。
オルカンは2018年に設定されて以来、個人投資家から圧倒的な支持を集めており、純資産総額は5兆円を超えて国内でも最大級のファンドに成長しています。
「投信ブロガーが選ぶ Fund of the Year」では2019年から5年連続で第1位を獲得し、2024年には日経トレンディの「ヒット商品ベスト30」で“新NISA&『オルカン』投資”が1位として取り上げられるなど、その信頼性と人気が伺えます。
長期の資産形成を目指す投資家にとって、低コストで全世界に投資できるオルカンはコア(中核)資産として位置づけられることが多く、初心者から上級者まで幅広く利用されています。
MSCI ACWIとの関係
オルカンが連動を目指すMSCI ACWI(All Country World Index、オール・カントリー・ワールド・インデックス)は、世界の株式市場全体の動きを表す代表的な株価指数です。
MSCI社が算出するこの指数は、先進国23か国と新興国24か国の大型株・中型株で構成されており、世界時価総額の約85%をカバーしています(残り15%程度の小型株は含まれません)。
具体的な構成国としては、先進国では米国、日本、イギリス、ドイツなど主要マーケットが網羅され、新興国では中国、インド、ブラジルなど成長市場が含まれます。
銘柄数はおよそ2,900銘柄(2024年時点)に達し、グローバルな分散効果を発揮する指数です。
MSCI ACWIは、さらに内訳としてMSCI World(先進国株指数)とMSCI Emerging Markets(新興国株指数)を合わせたものです。
例えば、日本を含む先進国株式部分(MSCI World)と、新興国株式部分(MSCI EM)を合算することでACWIが構築されています。
この指数は時価総額比率で構成されるため、各国の株式市場規模や株価の動向に応じてウェイト(構成比)が日々変化します。
指数の定期的な見直し(構成銘柄の入れ替え)は年2回(5月と11月)実施され、浮上してきた企業が組み入れられたり、相対的に時価総額が小さくなった企業が除外されたりします。
オルカンはこの「生き物」として変化する指数に連動するため、ファンド自体も指数に合わせて常にポートフォリオを新陳代謝させていく仕組みです。
要するに、オルカンはMSCI ACWIという設計図に忠実に投資されており、世界全体の株式市場とほぼ同期した動きをします。
日本を含む全世界の株式市場が上昇すれば基準価額も上昇し、逆に世界同時株安となれば基準価額も下落します(円建ての場合は為替の影響も受けます)。
このように明確なベンチマークが存在することで、投資家はオルカンの運用成績を客観的な指標と比較して評価することができますし、運用の透明性も高く保たれます。
なお、MSCI ACWIは配当込み指数のため、オルカンも組入株式の配当相当額を再投資込みで運用成績に反映しています(後述の通りオルカン自体は分配金を原則出さず再投資)。
組入国と比率、セクター構成
オルカン(MSCI ACWI)の組入国・地域の内訳を見てみると、現在の世界株式市場では米国が突出しています。
2025年時点で米国株の比率は約60%(およそ6割)に達しており、オルカンの資産の過半は米国株式で占められています。
次いでウェイトが大きいのは日本(約5%前後)、イギリス(約3%)、カナダ(約2~3%)、フランス(2%強)、スイス(2%弱)などとなっており、単一国として米国が圧倒的に大きいものの、残り4割はその他の先進国や新興国が分散して占めています。
新興国市場の合計比率は全体の1割強程度で、中国が数%、次いで台湾、インド、韓国などが各1~2%程度ずつ占める構成です。
つまり、オルカンは米国中心ではありますが、米国以外に約40%の資産を投じており、日本や欧州、新興国など米国以外の成長も取り込めるポートフォリオになっています。
オルカンのセクター(業種)構成も多岐にわたります。
組入上位の業種は、まず情報技術セクターが約23%と最も大きく、次いで金融が約18%を占めます。
以下、一般消費財・サービス(約10%)、資本財・サービス(約10%)、ヘルスケア(医療)(約10%)がほぼ同程度のウェイトで並び、次いで通信サービス(約8%)、生活必需品(約6%)、エネルギー(約4%)、素材(約3%)、公益事業(約2%)と続きます。
このように業種面でもITから金融、消費、資源まで幅広い分野に分散されており、一国のみならず特定業種への偏りリスクもある程度抑えられています。
ただし現状では、世界的に時価総額の大きいIT企業群(いわゆるハイテク・グロース株)の比重が高く、オルカンでも情報技術セクターが最大となっています。
組入銘柄の上位を見ると、2024年時点では米国の巨大ハイテク企業が名を連ねています。
最も組入比率が高いのはApple(アップル)で個別銘柄として約4%強、次いでMicrosoft(マイクロソフト)が約4%、NVIDIA(エヌビディア)が約3%、Amazon.com(アマゾン)が2%台後半、Alphabet(グーグル)やMeta(メタ/Facebook)が約1~2%といった具合です。
上位10社ほどで全体の約15~20%を占めますが、その大半は米国企業です。
このようにトップ銘柄は米国のIT・通信大手が占めていますが、同時にオルカン全体では2,600銘柄以上を幅広く保有しているため、一部企業の動向にポートフォリオ全体が過度に左右されにくい構造にもなっています。
例えば、ある上位銘柄で不祥事や業績不振が発生して株価が大きく下落した場合でも、他の多数の銘柄で補われるため、個別株リスクの分散効果が期待できます。
オルカンとS&P500との違いと比較論点
オルカンとよく比較対象に挙げられるのが、米国株に特化したインデックスファンドであるS&P500(例えばeMAXIS Slim 米国株式)です。

両者の最大の違いは投資対象の範囲で、オルカンが「全世界(ワールドワイド)」であるのに対し、S&P500は「米国(アメリカ)」に限定されています。
言い換えると、オルカンは世界60か国近くの市場に投資する分散性がある一方、S&P500は米国1か国の株式500銘柄に集中的に投資するファンドです。
ただし前述のように、オルカンの構成比の約60%は米国株が占めます。
したがってオルカン ≒ S&P500(米国株) + その他40%(米国以外の世界株)ともいえ、両者のパフォーマンスの差は概ね「米国以外の株式部分の差」に起因します。
オルカンとS&P500の過去リターンと今後の展望
過去のリターン(成績)を見ると、近年は米国株式(S&P500)ファンドの方がオルカンより高いリターンを示してきました。
例えばオルカン設定来(2018年末~2025年初頃まで)の平均年率リターンはおよそ+17%前後と試算されますが、同期間のS&P500ファンドは平均+20%程度と年間で約2~3%上回る利回りを記録しています。
過去5年ほどをどの時点から区切って比較しても、概ね米国株中心のS&P500の方が全世界株式よりリターンが高い傾向が見られました。
この背景には、米国市場(特にハイテク株)の顕著な成長があり、世界株指数においても米国株が牽引役となったことが挙げられます。
一方、オルカンが含む日本や欧州、新興国市場は同時期に相対的に低調で、米国一強の状態が続いたため、分散したオルカンの方が「平均的な世界成長率」となりリターンが抑えられました。
しかし、将来の展望に関しては必ずしも過去と同じ結果になるとは限りません。
米国株式が今後も一貫して世界をアウトパフォーム(上回る)し続けるかは不確実であり、むしろ特定の国や地域だけに集中するリスクも指摘されています。
例えば、1990年代の日本株は世界最大の時価総額を占めていながらその後長期低迷しましたし、2000年代中頃には新興国株式が米国株を凌ぐ成長を見せた時期もありました。
こうした歴史を踏まえると、将来において米国以外の市場が相対的に高い成長を遂げれば、オルカンのリターンが米国株ファンドを上回る可能性も十分あります。
逆に引き続き米国企業が世界経済をリードする展開が続けば、今後もS&P500の方が高リターンになるかもしれません。
要するに、オルカンとS&P500のどちらが有利か(どっちがいいか)は将来の市場動向に依存し、一概に断言できない部分があります。
長期的な視点では、全世界株式も米国株式もいずれも株式市場の成長を享受できる資産クラスであり、どちらも時間の経過とともに資産価値の増大が期待される点は共通しています(もちろん保証はありませんが、世界経済が成長すれば企業利益も増え株価も上昇しやすいと考えられます)。
そのため、どちらを選ぶにせよ長期投資を前提としてじっくり資産を育てる戦略が重要です。
短期的なリターンの優劣に捉われすぎず、自身が納得できる運用方針(「より広く分散する安心感」を取るか、「米国集中による成長性」を取るか)に基づいて選択することが大切だと言えるでしょう。
オルカンとS&P500の為替リスクや信託報酬の違い
オルカンとS&P500ファンドの為替リスクとコスト面の違いも確認しておきます。
まず為替リスクについて、オルカンは為替ヘッジなしのファンドであり、組入資産の大半は外貨建て資産です。
日本を含む全世界株式とはいえ、日本株の比率は約5%程度しかなく、残り約95%は米ドル、ユーロ、その他各国通貨建ての外国株式です(例:米国株はドル建て、欧州株はユーロ建てなど)。
そのため円換算の基準価額は各国通貨と円との為替変動の影響を大きく受けます。
円安方向に振れれば外貨建て資産の円評価額が上昇するためオルカンの基準価額を押し上げ、逆に円高になれば基準価額の下押し要因となります。
例えば2022年は急激な円安(ドル高)が進行したため、世界の株価が下落局面でもオルカンの円建て基準価額の下落は緩和されました。
一方で仮に今後円高が進めば、たとえ現地通貨ベースで株価が横這いでも円建てでは基準価額が目減りする可能性があります。
このようにオルカンの投資では為替変動によるブレは避けられませんが、多通貨分散ゆえに特定通貨への偏りは低いとも言えます。
米国株ファンドの場合、実質的に対米ドルの為替リスク100%を負うのに対し、オルカンは米ドルが約6割・その他通貨が4割程度の比率です。
そのため、ドル円相場の影響はS&P500ファンドよりは分散されています(例えばドル安・ユーロ高のような局面では、ドル安で米国株部分は目減りする一方、ユーロ高で欧州株部分が相殺するといった効果も一部期待できます)。
もっとも、世界同時不況の場面では円が全面高(リスクオフの円高)となる傾向もあり、結局どちらのファンドも大きく下落するでしょう。
為替ヘッジを行わない限り為替リスクは付き纏いますが、長期では為替変動はプラスにもマイナスにも働き得て予測困難なため、多くのインデックス投資家は無ヘッジで保有するケースが一般的です。
オルカンも為替ヘッジ無しとすることでコストを抑え、長期では為替のプラスマイナス要因が平準化されることを想定した設計です。
オルカンとS&P500の信託報酬(運用管理費用)の違い
次に信託報酬(運用管理費用)の違いです。
オルカンの信託報酬率は年率0.0578%(税込)程度と、非常に低く抑えられています。
実はこの水準は米国株式ファンド(eMAXIS Slim S&P500等)の信託報酬0.0814%前後よりも低く、現在ではオルカンの方がわずかにコスト優位となっています。
当初、全世界株式ファンドは国際分散の手間などから米国株ファンドより高コストとされていましたが、近年の競争激化によりオルカンも大幅な信託報酬引き下げが行われました。
2023年9月には信託報酬が約半分に引き下げられ、さらに受益者還元型信託報酬(純資産残高が増えるほど段階的に料率が下がる仕組み)を採用しています。
そのため純資産総額が増大した現在では実質0.06%を切る水準まで低下しており、業界最低水準のコストを実現しています。
なお、S&P500ファンドも含めeMAXIS Slimシリーズはいずれも受益者還元型で低コスト競争に対応しているため、両者のコスト差はごくわずかです。
実際の運用上かかる経費(実質コスト)まで含めても、どちらも年率0.1%程度と非常に小さく、コスト面の優劣は投資成績に大勢へ影響しないレベルと言えます。
つまり、オルカンとS&P500のどちらを選ぶかにおいて、信託報酬の差は決定的な要因ではないでしょう。
投資家にとって重要なのはむしろ投資対象の中身(全世界か米国か)やリスク許容度の違いであり、コストはいずれを選んでも極めて良心的な水準に抑えられています。
投資対象としてのオルカンの特徴
オルカンには、長期の資産形成に適したいくつかの特徴があります。
極めて高い分散効果
先述の通りオルカンは全世界の株式を網羅しており、国際分散・業種分散が効いたポートフォリオです。
個別株や特定国に投資する場合と比べ、極端な値動きや局地的なリスクに晒されにくいメリットがあります。
世界経済全体の成長をまるごと取り込むアプローチであり、特定企業や特定地域の盛衰に運用成績が左右されにくい点が魅力です。
低コストと効率性
信託報酬わずか0.05~0.06%台という超低コストで運用されており、コスト面で投資家のリターンをほとんど目減りさせません。
同種の全世界株式インデックスファンドの中でも最安水準であり、また購入時手数料(販売手数料)も無料です(ノーロード)。
少額からの投資にも適しており、100円といった小口からコツコツ積み立てることができます。
投資効率と手軽さ
オルカン1本で世界中に投資できるため、投資初心者でもこれ一本で国際分散投資が完結します。
本来、世界の個別株を自分で揃えるのは不可能に近いですが、投資信託であるオルカンならワンクリックで全世界ポートフォリオを構築できます。
組み入れ比率の調整や定期的なリバランスも運用会社側で自動的に行われるため、投資家は煩雑な管理をせずに済みます。
「ほったらかし投資」に適した商品と言えるでしょう。
高い流動性と信頼感
純資産総額が数兆円規模に達し、多くの投資家に支持されているため、流動性リスクは極めて低いです。
解約(売却)しようとしても原則として毎営業日行うことができ、基準価額で解約代金が受け取れます。
また規模が大きい分、ファンド継続にも安定感があり、繰上償還(早期終了)などの心配も事実上ありません。
長期にわたり安心して積み立てていける土壌があります。
税効率の良い運用
後述するようにオルカンは無分配型(実質再投資型)で運用されます。そのため投資中に分配金(配当)が出て課税されることがなく、複利効果を最大化しやすいです。
NISA・積立投資に対応
オルカンは金融庁が認めるつみたてNISA適格商品でもありす。
楽天証券やSBI証券など主要証券会社では、オルカンの毎月積立やボーナス月増額設定、さらにクレジットカード決済による積立購入にも対応しています。
以上のように、オルカンは手軽さ・低コスト・広範な分散という点で非常に優れた商品ですが、一方で注意しておきたいポイントもあります。
次の節では、その運用上の注意点や誤解されやすい点について解説します。
オルカンの分配金や運用形態の注意点
分配金(配当)の扱いはオルカンを語る上で重要なポイントです。
オルカンは基本的に分配金を出さない方針で運用されています(実績としても設定以来一度も分配金は支払われていません)。
ファンドが受け取った株式配当や売却益はすべてファンド内で再投資され、そのぶん基準価額の上昇要因となります。
運用報告書にも
「信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する」
と明記されており、投資家に定期収入を配るよりも内部で複利運用する戦略です。
そのため、利回り(配当利回り)の面では0%ですが、再投資によってファンドのトータルリターンは高められます。
投資家としても分配金再投資の手間や再投資時の税金ロスが無いため、効率的に資産を増やせるメリットがあります。
ただし、もし投資途中で現金化したい場合は自分で一部解約(売却)して取り崩す必要があり、毎月分配などのように自動で現金収入は得られない点には注意しましょう。
運用形態の仕組みとしては、前述のとおりオルカンはファンド・オブ・ファンズ方式でマザーファンドを通じて各国株式に投資しています。
この構造上、一部で「他の投資信託に投資する二重構造なのでコストが二重にかかるのでは?」という疑問が出ることがあります。
しかし心配無用で、オルカンの信託報酬0.0578%の中にマザーファンドの運用コストも含まれており、投資家が別途余計な費用を負担することはありません(マザーファンドも同じ運用会社が運営しており、スケールメリットでコストが極小化されています)。
したがって、実質的には単体運用のファンドと変わらない低コスト体系になっています。
もう一点、信託期間と繰上償還について触れておくと、オルカンの信託期間は無期限(設定日:2018年10月31日、信託期限:無制限)です。
したがって、運用会社の判断で途中終了する可能性は極めて低く、基本的に投資家は長期間にわたり保有し続けられます。
純資産総額も大きく受益者も多数いるファンドのため、今後も安定的に運用が継続される見通しです。
ただし受益者が極端に減少したり法制度変更があった場合などは例外的に繰上償還されるリスクも理論上ゼロではありません(一般論として押さえておき、現実的なリスクは低いでしょう)。
以上のように、オルカンは分配金を出さず内部で増やす運用であり、ファンド構造も投資家に余計な負担を強いないよう工夫されています。
制度上もNISAやiDeCoなどで使いやすく、まさに「長期・積立・分散」を体現する商品です。
では、その積立投資の方法と、投資家がよく悩む「積立か一括か」について次で考察します。
インデックスファンドの投資積立と一括、どちらが選ばれているか
オルカンを含むインデックスファンドへの投資では、積立投資(ドルコスト平均法)を選ぶか、一括投資(まとまった資金を一度に投入)するかという点も論点になります。
結論から言えば、多くの個人投資家は積立投資(つみたて)を選んでおり、特にオルカンは積立NISAの定番商品として毎月定額買付されるケースが非常に多いです。
積立投資のメリットは、購入タイミングを分散することで価格変動リスクを平準化できることです。
毎月一定額ずつ買い付けることで、基準価額が高い時には少ない口数しか買わず、安い時には多くの口数を買うため、平均購入単価をならす効果があります。
これにより、将来大きな暴落(マーケットクラッシュ)があった場合でも、高値掴みのリスクを軽減し心理的な負担を和らげることができます。
実際、オルカンを2020年初から毎月積み立てていた投資家は、同年2~3月のコロナショックで市場が急落した際にも安値で買い増しでき、その後の回復局面で大きな利益を享受できました。
過去の統計的にも、長期の資産運用では時間分散した積立投資は約定価格のブレを抑える効果があり、特に相場急変時に有効と言われます。
一方、一括投資は運用開始時にまとめて投資資金を投入する方法です。
理論的には、市場が右肩上がりに成長する局面では早くまとめて投資した方が複利効果を最大限享受できるため、一括投資の方が最終リターンが高くなる可能性があります。
例えば、2010年代のように概ね上昇トレンドが続いた期間では、初期に一括投資して放置しておく方が積立より資産残高が大きくなりました。
また、積立では常に現金の待機部分があるため上昇相場では機会損失が発生し得ます。
しかし一括投資は、投資直後に暴落が来た場合のダメージが大きいというリスクも抱えます。
極端な例では、リーマンショック直前の2008年初に一括投資した場合、その後の下落で評価額が半分以下に落ち込んだ状態が数年続くなど、精神的なショックは大きなものになります。
実際、オルカンでも設定直後の2018年末にまとめて投資した直後、翌2019年は好調だったものの2020年2~3月には基準価額が1ヶ月で約▲31%暴落する局面がありました。
一括投資ではこの下落をまともに被ることになりますが、積立投資であれば下落中も買い付けを継続することで、その後の回復時に平均取得単価が下がっている分有利に働きました。
以上を踏まえ、「積立と一括、どっちがいいか」は一概に言えませんが、一般的には毎月の収入からコツコツ投資していく積立投資が再現性が高く心理的ハードルも低いため、選択する人が多い傾向です。
もっとも、一括投資が必ずしも悪いわけではなく、もし手元に大きな資金があって長期投資に回せるなら、早く市場に投入するほど期待リターンを享受する期間は長くなります。
理論研究では、株式市場が長期的に上昇する確率が高い以上、時間分散せず一括で投資した方がリターン期待値は高いとの結果もあります。
そのためまとまった資金があり値下がりリスクを許容できる場合は、一括で投資した後は放置するという戦略も合理的です。
要は、リスク許容度とメンタル面の安定を考えて、自分が続けやすい方法を選ぶのがよいでしょう。
不安が大きいなら積立で徐々に始め、問題なければ追加で一括投入する、といった柔軟なアプローチも可能です。
実際のところ多くの人は積立投資を基本としつつ、ボーナス時や相場急落時にスポットで追加投資(いわば部分的な一括投資)をするなど両者を組み合わせています。
重要なのは、どちらの方法であっても長期間継続することであり、自分に合ったやり方でオルカンへの投資を続けることが長期成績につながると考えられます。
オルカンのよくある誤解と中立的な見解
グローバルに分散された優れたファンドであるオルカンですが、投資家の間でいくつかよくある誤解や議論が存在します。
ここでは主な論点を取り上げ、それらに対する中立的な考え方を整理します。
暴落時の考え方
「暴落したらどうするか?」
は、株式100%のファンドであるオルカンに投資する上で避けて通れないテーマです。
オルカンは世界全体に分散しているとはいえ、リスク資産である株式に投資している以上、市場全体の暴落局面では逃れられず大きく下落します。
実際のケースとして、2020年2月中旬から3月中旬にかけてのコロナショックでは、オルカンの基準価額は約▲31%もの急落を記録しました。
これは1か月ほどで資産が3割減るインパクトであり、初心者にとっては極めてショッキングな状況だったと言えます。
しかし、その後わずか数ヶ月で基準価額は回復し、2021年にはコロナ前の高値を大きく上回る水準に上昇しました。
このように、暴落と急騰は表裏一体であり、長期で見れば一時的な暴落も大きな上昇局面の中の一コマである場合が多いです。
暴落時に取る行動としては、大きく分けて「売却して逃げる」か「耐えて持ち続ける(あるいは買い増す)」かになります。
どちらが正解かは結果論に左右されますが、一般に市場のタイミングを正確に予測することは困難であるため、長期投資の文脈では「暴落時にも慌てて売らず継続保有する」戦略が推奨される傾向があります。
実際、歴史的に見れば世界株式は幾度も暴落を経験しつつも、長い目で見れば成長してきました。
例えばITバブル崩壊やリーマンショックの時に世界株は半分以下になりましたが、その後数年から10年程度で回復し、さらに高値を更新しています。
暴落局面で売却してしまうと、安値で手放した後に来る反発上昇(いわゆる稲妻が輝く瞬間)を逃してしまうリスクがあります。
逆に持ち続けていれば含み損に耐える必要はありますが、やがて景気や企業利益が回復すれば評価額も戻ってくる可能性が高いです。
中立的な見解としては、暴落は長期投資家にとって避けられない通過点であり、事前に心構えを持っておくことが重要だと言えます。
オルカンのような全世界株式ファンドの場合、一国だけに集中するより暴落耐性は多少高いものの、世界同時不況では結局ほぼ同様の下落を覚悟する必要があります。
そのため普遍的な対策は、資産配分を自分のリスク許容度に合った範囲に抑えることです(例えば株式100%では不安が強いなら債券や現金を一部持つ等)。
また、いざ暴落が起きても感情的にパニックにならないよう、「株式市場では3割程度の下落は普通に起こり得る」ことを理解しておくと良いでしょう。
そうすれば、暴落時にも冷静さを保ち、適切な対応(必要以上の損切りをしない・むしろ積立を続け割安に買い増す等)が取りやすくなります。
要約すると、暴落時には慌てず騒がず、自分の長期計画に従って行動することが大切であり、オルカンもそのような長期投資に耐えうる商品設計がなされています。
「やめた方がいい」とされる論拠とは
インデックス投資界隈では、「オルカンよりS&P500に絞った方がいい」「全世界株式はやめておけ」といった意見が見られることもあります。
そう主張する論拠として、主に次のような点が挙げられます。
米国株に比べリターンが見劣りする
近年の実績では、全世界株式より米国株式(S&P500)の方が高リターンだったため、「わざわざ低リターンの国まで含める必要はない」という指摘があります。
オルカンには成長力の低い日本・欧州株や不透明な新興国株も含まれるため、米国株だけに投資した方が効率が良いのでは、という考えです。
米国と他国の重複や非効率
オルカンには日本株も含まれていますが、日本人投資家はすでに給与や年金など自国要素に露出しているため、敢えて投信で日本株を買い増す必要はないという見方があります(→代わりに「全世界株式(日本除く)」を選ぶべきだ等)。
また米国株はグローバル企業が多く他国の成長も取り込めるので、米国株だけで十分グローバル分散になっているとも言われます。
ファンド構成や銘柄に不満
一部細かな点では、ACWIは小型株を含まないため真の「全世界オールキャップ」ではないとか、新興国には政治リスクが高い国も含まれており投資したくない、といった声もあります。
あるいはオルカンはごく大型株に偏重しすぎでグローバルの中でも特定企業(GAFA等)依存度が高いからリスクではないか、といった指摘もあります。
以上のような論拠は一理あるものの、中立的に評価するとオルカンにも依然大きな意義があると言えます。
まずリターン比較については、確かにここ数年は米国株だけの方が良好でしたが、それは結果論に過ぎません。
将来も米国一強が続く保証はなく、特に評価額が既に高い米国株は今後10年で他地域より低リターンにとどまる可能性も否定できません。
全世界に投資するオルカンは、そうした将来の不確実性に備える保険のような役割があります。
つまり、「次の10年も米国がトップである」と確信できるならS&P500偏重も合理的ですが、それを断言できないからこそ市場全体に乗る(マーケットポートフォリオを持つ)戦略が支持されるのです。
日本株を含むか否かについても、オルカンの日本株比率は5%程度と小さいため、仮に日本株が低迷しても全体への影響は限定的です。
逆に日本も含めておくことで、万一日本株が見直されて上昇した際には恩恵を受けられます(日本人が自国市場を全く持たないのも一種の偏りです)。
米国株のみで十分との意見についても、確かに米国企業は多国籍化が進み世界利益を取り込んでいますが、それでも上場市場が米国だけという時点で通貨や政策リスクは米国に集中しています。
たとえば仮に将来ドルの基軸通貨体制に変化が生じたり、米国の競争力が相対低下した場合、米国株100%では代替が効きません。
全世界株であれば、仮に米国の比重が低下しても指数が自動的に新興国や他の先進国の比率を高めて対応します(実際に1990年代のACWIは日本が3割近くを占めていましたが、現在は米国が6割に変化しています)。
つまり、オルカンは世界経済の勢力図変化に合わせてダイナミックにポートフォリオを調整してくれるという利点があるのです。
小型株や特定国リスクの件については、たしかにACWIは大型・中型株のみで構成され時価総額上位企業への集中度が高いですが、それは裏を返せば「世界でもっとも影響力の大きい主要企業」に投資しているとも言えます。
小型株を含む全世界指数(例えばFTSEグローバル・オールキャップなど)を使ったファンドも存在しますが、過去の実績では大型株中心のACWIと極端な差は生んでいません。
また新興国も個別にはリスク要因がありますが、指数全体で見れば新興国比率は1割強に過ぎず、仮に一部の国が低迷しても他国で補われる仕組みです。
特定の国を自分で除外することも可能ですが、それはインデックス運用からアクティブ運用への転換を意味しますので、よほど明確な見通しや理由がない限り避けた方が無難でしょう。
総じて、オルカンに否定的な論拠は「米国株への信頼」が根底にあるケースが多いです。
確かに米国市場はこれまで素晴らしい成長を遂げており、今後も中心的存在でしょう。
しかし投資の世界では「絶対」ということはなく、むしろ楽観的な予測に反した局面に備えておくことが重要です。
全世界株式への投資は「世界全体の将来を信じる」という極めてオーソドックスな戦略であり、特定の地域に賭けない分、極端なハズレを引きにくい安心感があります。
各投資家がどこまでリスクを取れるかによってオルカン一本にするか他資産を組み合わせるかは異なりますが、「やめた方がいい」とまで言い切れるような大きな欠点はないと考えられます。
むしろ重要なのは、オルカンであれS&P500であれ継続して長期保有することであり、途中で投資を止めてしまえばどんな優れた商品でも成果は出せません。
惑わされやすい市況や周囲の声に左右されず、自分の納得した戦略に基づき腰を据えて運用を続けることが、長期投資の成功につながるという点は強調しておきたいポイントです。
まとめと今後に向けた考察(推奨なし)
以上、オルカンについて、その仕組みや構成、S&P500との比較、リスクやリターン、運用上のポイントまで幅広く解説しました。
オルカンは「低コストで世界丸ごと投資」を実現したインデックスファンドです。
米国株を中心に、日本・欧州・新興国まで含めた国際分散ポートフォリオを1本で構築でき、信託報酬も業界最低水準とコスト効率も抜群です。
オルカンに投資することは、世界全体の成長エンジンに長期間参加することを意味します。
もっとも、全世界株式だからといって魔法のようにリスクが消えるわけではありません。
株式100%のファンドである以上、短期的には大きな変動があり得ますし、ときには資産が数割減る局面も経験するでしょう。
しかし、どの国が台頭しどの企業が入れ替わろうとも、オルカンは常にその時々の世界市場に合わせて最適化されたポートフォリオであり続けます。
これは個人で真似しようにも到底できない芸当であり、インデックスファンドの強みです。
重要なのは、オルカンを自分の資産形成計画の中でどう位置付けるかです。
全世界株式を軸に据えることで、株式部分の投資配分について大きく迷う必要はなくなります。
あとは各自のリスク許容度に応じて債券や現金とのバランスを取ったり、あるいはオルカンと他を組み合わせ微調整することも考えられます。
最後に強調しておくと、本記事は投資助言を行うものではなく、事実に基づく参考情報を提供しました。
ご自身の目的や方針に沿った判断をしていただければ幸いです。




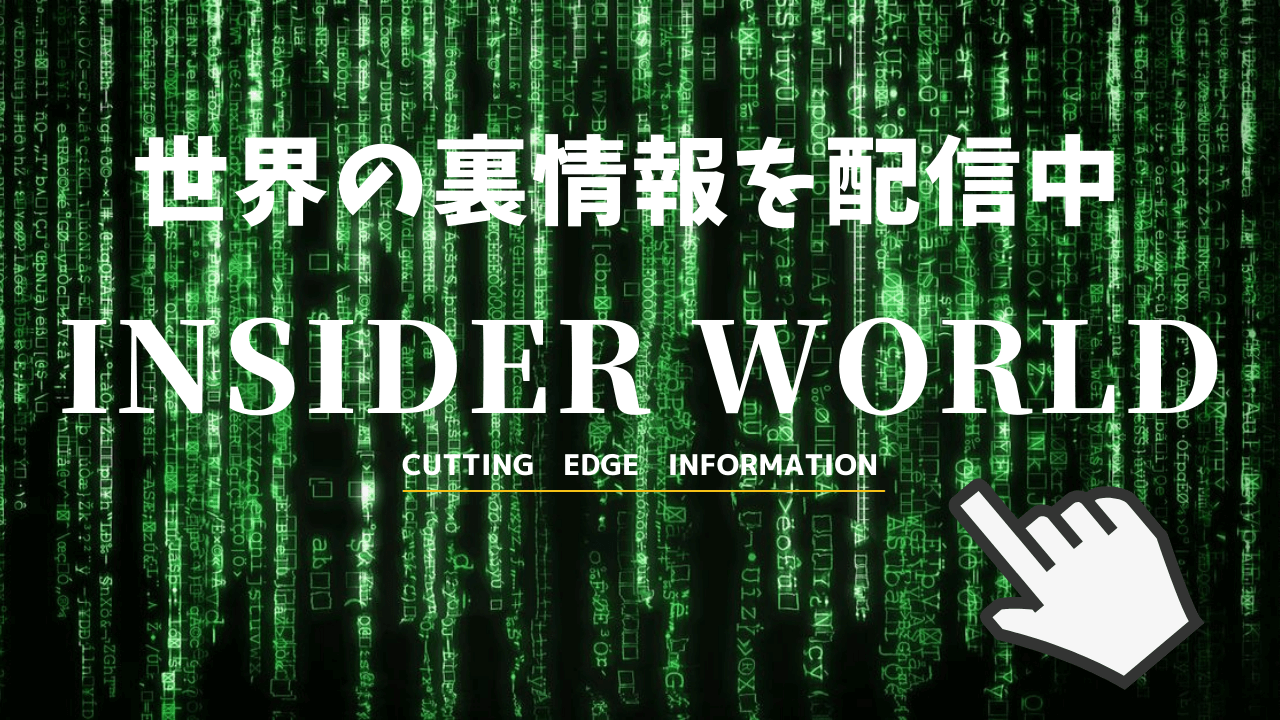

コメント