※本記事は投資助言を行うものではなく、参考情報としてご利用ください。
Masakiです。
「S&P500ってよく聞くけど、結局なに?」
「NASDAQやオルカンと比べてどっちが良いの?」
「長期投資すれば本当にFIREできる?」
そんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
S&P500は米国株式市場を代表する株価指数であり、初心者から上級者まで幅広い投資家に注目されています。
しかし、その歴史や仕組み、他の指数との違い、将来の見通しなど、意外と理解があいまいな点も多いものです。
本記事では、S&P500とは何かを基礎から丁寧に解説し、歴史・構成銘柄・配当(分配金)・PER(株価収益率)・利回りといった重要ポイントを網羅します。
さらに、NASDAQ100(ナスダック100)や全世界株式(オルカン)、VTI(全米株式)、レバナスなど主要な指数・ETFとの比較を行い、それぞれの特徴と違いを分かりやすくまとめます。
長期の積立投資との関係、著名投資家ウォーレン・バフェット氏のS&P500に対する見解にも触れ、読み終えれば、S&P500についての理解が深まることでしょう。
それでは、ステップ・バイ・ステップでS&P500について一緒に見ていきましょう。
S&P500とは?米国を代表する株価指数の基本 (Step1)
まずは「S&P500」とは何か?
その基本から。
S&P500(エス・アンド・ピー500)とは、アメリカの代表的な株価指数の一つで、米国株式市場に上場する大型企業500社の株価をもとに算出されています。
ダウ平均株価(30社)と並んで米国市場を象徴する指数であり、時価総額(株式の時価総額合計)で米国株式市場の約80%をカバーするとされています。
つまり、S&P500を見るだけで米国経済全体の株式動向を大まかに把握できるわけです。
S&P500の名称の由来
S&P500の「S&P」とはStandard & Poor’s(スタンダード・アンド・プアーズ)の略称です。
これは指数を算出・管理する会社名で、米格付け会社S&Pグローバルの一部門(S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社)が運営しています。
もともとは1923年に前身の会社が複数の株価指数を開発し、1957年に500銘柄の指数へ発展させた歴史があります。
算出方法
S&P500は時価総額加重型の指数です。
各企業の「株価 × 発行株数(浮動株ベース)」を合計し、基準時からの変動を指数化しています。
時価総額の大きい企業ほど指数に占める割合(ウエイト)が大きく、値動きへの影響力も大きくなります。
代表性
採用される500社は単に上位500社というわけではなく、選定委員会が基準に基づき選抜しています。
具体的な採用基準として、一定以上の時価総額、十分な流動性と売買高、継続的な利益計上(直近の四半期と過去4四半期合計で黒字であること)などがあります。
こうした基準により、指数は米国経済を牽引する代表企業で構成されるよう調整されています。
S&P500は米国株式市場全体の動きを映す“景気鏡”とも言える存在です。
「500社」と数は多いですが、時価総額上位の大型株に重み付けされているため、指数の動きは特に巨大企業の影響を強く受けます。
では、その500社には具体的にどんな企業が含まれているのでしょうか?
次のステップで構成銘柄やセクターを見てみましょう。
S&P500の構成銘柄とセクター内訳 (Step 2)
S&P500に採用されている企業は米国を代表する大企業500社です。
時価総額加重であるため、指数全体に対する寄与度は企業ごとに異なります。
現在、指数の上位にはテクノロジーを中心とした超大型企業が名を連ねています。
トップ構成銘柄と割合
2025年3月末時点のS&P500上位構成銘柄(上位10社)とその指数内シェアは以下の通りです。
Apple (AAPL) – 約7.0%(米国を代表するハイテク企業)
Microsoft (MSFT) – 約5.8%(ソフトウェア最大手)
Nvidia (NVDA) – 約5.5%(半導体・AI関連の大手)
Amazon.com (AMZN) – 約3.7%(EC・クラウドの世界最大手)
Alphabet (GOOGL) – 約3.4%(Googleの持株会社。クラスA&C株合計)
Meta (META) – 約2.6%(旧Facebook、SNS大手)
Berkshire Hathaway (BRK.B) – 約2.0%(バフェット率いる持株会社)
Broadcom (AVGO) – 約1.6%(半導体・通信チップ大手)
Tesla (TSLA) – 約1.5%(電気自動車メーカー)
JP Morgan Chase (JPM) – 約1.4%(米国最大手の銀行)
上位10社だけで指数全体の34.6%ものシェアを占めています。
特にAppleとMicrosoftの2社で約13%を占めるなど、一部の巨大企業の影響力が非常に大きいです。
これら上位はテクノロジー企業が多く、S&P500は近年ハイテク株偏重の傾向が強まっています。
一方、500社すべてに目を向けると、金融やヘルスケア、工業、エネルギーなど様々な業種の企業が含まれており、米国経済の多様なセクターを反映しています。
11のセクター割合
S&P500の全構成銘柄はGICS(世界産業分類基準)によって11のセクターに分類できます。
それぞれのセクター比率のイメージは以下の通りです。(2025年時点の概算)
情報技術(Information Technology):約30% (Apple、Microsoft、Nvidiaなど)
金融(Financials):約10% (JPMorgan、Bank of Americaなど)
ヘルスケア(Health Care):約13% (UnitedHealth、Johnson & Johnsonなど)
一般消費財(Consumer Discretionary):約10% (Amazon、Teslaなど)
通信サービス(Communication Services):約8% (Alphabet、Metaなど)
工業(Industrials):約8% (United Technologies、Boeingなど)
生活必需品(Consumer Staples):約7% (Procter & Gamble、Coca-Colaなど)
エネルギー(Energy):約5% (ExxonMobil、Chevronなど)
公益事業(Utilities):約3% (NextEra Energyなど)
不動産(Real Estate):約3% (American Towerなど)
素材(Materials):約3% (Dow、DuPontなど)
※上記割合は時期により変動するため目安です
情報技術セクターが約3割と突出していますが、それ以外にも多様な業種を含んでいるため、セクター分散はある程度効いています。
例えばエネルギー株が低迷しても他のセクターが補う、といった具合です。
ただし昨今の米国市場ではITやハイテク企業が相対的に巨大化しているため、その動向に指数全体が大きく左右される点には注意が必要です。
S&P500は500社の集合体ですが、「GAFA」に代表される一部大型ハイテク企業への偏りがあることを理解しましょう。
とはいえ金融・ヘルスケア・工業など他のセクターも含まれるため、個別株を一つ買うよりは遥かに分散投資効果があります。
採用銘柄の入れ替え
S&P500の採用銘柄は固定ではなく、定期的に見直し・入替が行われます。
例えば業績悪化や他社との合併などで指数の代表性にそぐわなくなった企業は除外され、新たに台頭した企業が追加されます。
選定は前述の通り委員会の裁量が入るため、「必ずしも単純な時価総額順位ではない」点も特徴です。
近年ではテスラが2020年末に採用されるまで長らく除外されていたケースなどが話題となりました。(要件となる黒字化達成まで待たされた)
以上がS&P500の構成イメージです。
それでは、この指数のパフォーマンスや投資指標について見ていきましょう。
S&P500の過去の実績:リターン・配当・PERを読み解く (Step 3)
次に、S&P500のこれまでの実績や投資指標を確認します。
長期投資を考える上で、「どれくらいの利回りが期待できるのか」「配当金は出るのか」「現在の株価水準(PER)は割高か」など気になる点ですよね。
それぞれ順を追って解説します。
過去の長期リターン
S&P500は長い歴史の中で右肩上がりの成長を遂げてきました。
1926年から現在に至るまでの年平均リターンは約9.8%(配当込み、名目)とされています。
インフレ調整後でも約6%の年平均成長です。
つまり、仮に1926年にS&P500にまとめて投資して放置していた場合、およそ10%弱の年複利で資産が増えてきた計算になります。
もっと直近の数字では、1957年の指数算出開始以降で平均約7%〜10%程度とも言われます。
特に直近10年間(2013〜2022年)は年率14%台の高いリターンを記録したという試算もあります。
こうした高成長が語られる一方で、重要なのは変動(ボラティリティ)も大きいという点です。
S&P500の年次リターン(1928–2022年)では、長期的には上昇傾向だが、年ごとの変動は大きく、特に金融危機やバブル崩壊時には-30〜-40%超の下落も発生している。
70%以上の年でプラス成長となっている点にも注目。
S&P500は年間で見れば3割以上の下落を経験することもある(例:2008年 -37%、1931年 -47%など)一方で、プラスの年も多く全期間の約70%は年間上昇となっています。
このように短期的には上下を繰り返しながら、長期では成長してきたのがS&P500の実力です。
好調期
1980年代後半~1990年代(ITバブル前)や直近の2010年代は強気相場で、S&P500は年率10%超の伸びを示しました。
特に2019年 +28.9%、2021年 +26.9%(配当除く)など大きな上昇もありました。
不調期
2000年代初頭(ITバブル崩壊と金融危機が続いた時期)は「失われた10年」とも言え、2000年から2009年まで見ると年率マイナスという結果もあります。
しかしその後の回復で長期平均に戻っています。
暴落と回復
ブラックマンデー(1987年)やITバブル崩壊(2000-2002年)、リーマンショック(2008年)、コロナショック(2020年3月)では急落しましたが、多くの場合数年以内に過去最高値を更新する回復を遂げています。
S&P500の長期リターンは魅力的ですが、「一年間でも-30%以上下がるリスクがある」ことを忘れてはいけません。
逆に言えば、そのような暴落期に慌てて売らずに持ち続け、あるいは積立を続けることで、その後の上昇による恩恵を享受できたのが歴史の示すところです。
配当金と配当利回り
S&P500は配当込みの総合リターンで語られることが多いですが、指数そのものも配当を生み出す点は重要です。
500社のうち多くの企業が株主配当を出しており、指数としての配当利回りは概ね1%台です。
現在の配当利回り
2025年4月時点で、S&P500の配当利回りは約1.4〜1.5%程度となっています。
例えば2025年4月4日時点のデータでは1.48%と報告されています。
直近では株価上昇やハイテク企業比率増加により、利回りはやや低めです。
歴史的な利回り
長期的に見ると、S&P500の配当利回りは2〜4%程度で推移してきました。
1980年代には5%前後の時期もありましたが、近年は自社株買いの増加やハイテクグロース企業の比率拡大もあり、最低水準の1%台前半となっています。
実際、過去最低は1.1%前後(2021年前後)で、過去最高は6〜7%(1970年代など)の水準でした。
配当の重要性
配当金は四半期ごとに企業から支払われます。
S&P500としての配当は年率換算で約1.5%でも、長期では雪だるま式に資産を増やす原動力となります。
再投資すれば複利で増えますし、FIRE達成後に取り崩す際には安定収入源にもなりえます。
例えば、「S&P500トータルリターン指数」(配当再投資込み)と通常の価格指数を比較すると、長期では大きな差がつきます。
配当再投資の効果は絶大で、歴史的リターン9.8%のうち約2〜3ポイントは配当によるものでした。
S&P500採用銘柄の中には、25年以上連続増配を続けている企業もあります。
これらは「配当貴族(Dividend Aristocrats)」と呼ばれ、インカムゲイン(配当収入)目的の投資家にも注目されています。
株価収益率(PER)とバリュエーション
株価水準の割安・割高感を見る指標としてPER(株価収益率, Price Earnings Ratio)があります。
これは「株価 / 1株当たり利益」で計算され、S&P500全体のPERもしばしば市場の割高感を測る指標として用いられます。
現在のPER
2025年4月時点でのS&P500の予想PERは約20倍、直近12ヶ月の実績ベースPERは21〜22倍程度です。
例えばウォールストリートジャーナルのデータでは、4月4日時点でトレーリングPER(過去12ヶ月実績)が21.85倍、フォワードPER(予想)が19.98倍と報じられています。
過去との比較
近年のPERは歴史平均より高めです。
過去5年平均は19〜20倍程度、過去10年平均は18倍程度との分析もあります。
2021年末には一時30倍近い水準に達し、2022年の株価調整で現在は20倍前後まで低下しました。
それでも歴史的には上位7%程度の高さ(93パーセンタイル)との指摘もあります。
一般に、PERが高い=株価が割高と言われますが、低金利環境や成長期待の違いもあり一概には判断できません。
CAPEレシオ
より長期のバリュエーション指標としてCAPE(シラーPER)も注目されます。
これは10年平均実績利益で調整したPERですが、2025年のS&P500のCAPEは30〜35倍程度とも言われ、歴史平均(20倍弱)よりかなり高めです。
将来リターンの低下を示唆するとの見方もあります。
以上をまとめると、S&P500は近年やや割高感のある水準にあります。
PERが高い時期には過度な期待は禁物です。
ただし、短期的なPERの上下で売買タイミングを計るのは難しく、長期投資では「時間の分散」でリスク緩和することが王道です。
また、PERだけでなく金利動向や企業の成長性も考慮に入れる必要があります。
以上、S&P500の過去実績や指標を見てきました。
次は実践編として、どうやってS&P500に投資できるのか、具体的な手段を見ていきましょう。
S&P500への投資方法:ETF・投資信託の選び方 (Step 4)
S&P500に投資しようと思ったとき、個別の500銘柄を自分で買い集めるのは非現実的です。
そこで一般的なのが、S&P500に連動する金融商品(インデックスファンドやETF)を利用する方法です。
ここでは主要な選択肢とその比較ポイントを解説します。
投資信託 vs ETF:どちらを選ぶ?
投資信託(インデックスファンド)とETF(上場投資信託)はいずれもS&P500指数に連動する商品が多数存在します。
それぞれ以下の特徴があります。
投資信託(Mutual Fund型)
証券会社や銀行経由で購入でき、主に円建てで少額から積立投資しやすいです。
販売手数料は無料(ノーロード)が主流で、信託報酬(年率の運用管理費用)は0.1%前後と非常に低水準です。
ETF(Exchange Traded Fund)
株式と同様に市場で売買できる投資信託です。
米国市場上場のETF(VOO, SPY, IVVなど)は米ドル建てで購入する必要がありますが、経費率が0.03〜0.09%程度と安いです。
ETFはリアルタイム価格で売買でき、機動的な取引に向きますが、積立設定や少額投資は投信より手間がかかる場合があります。
どちらを選ぶか?
一般的に、初心者や長期積立を考える場合は投資信託型が手軽。
特に近年はネット証券で積立NISA対象商品として低コストのS&P500投信が提供されており、毎月100円からでも自動積立可能です。
一方、ある程度まとまった資金を一括で投じる場合や、米国ETFに直接投資したい場合はETFも選択肢になります。
米国ETFは為替コスト等を考慮しても経費率がわずかに安く、また米ドルで資産を持てるメリットもあります。
投信会社各社からS&P500連動ファンドが出ていますが、内容はどれも「S&P500に連動し、配当込みのトータルリターンを目指す」という点で共通し、大きな違いは信託報酬の差程度です。
現在は最安クラスのファンドで信託報酬年0.06%未満(税抜)というものもあり、費用競争が激化しています。
手順:初心者がS&P500投資を始めるには
初心者がS&P500への投資を始めるステップを簡単にまとめます。
1. 証券会社の口座を開設する – ネット証券(例:SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)がおすすめ。
2. 商品を選ぶ – 上記のような低コストのS&P500連動投資信託を1つ選択します。
3. 購入または積立設定 – 初回にまとまった金額を購入してもいいですし、毎月コツコツ積立設定することもできます。
4. 長期保有する – 一度買ったら日々の値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で保有し続けましょう。必要に応じて追加投資し、配当は再投資することで複利効果を高めます。
これで米国株500社にまとめて投資できたことになります。
個別株投資と違い、1社の倒産リスク等は極めて低く(500社全部が同時にゼロになる事態は考えにくい)、初心者にも安心感があります。
ただし注意点として為替リスクだけは頭に入れておきましょう。
S&P500への投資は実質的に米ドル資産への投資でもあります。
円から見たときにドル高円安が進めば利益が増え、逆に円高になると目減りします。
ここまででS&P500そのものについて詳しく見てきました。
次に、他の指数や投資対象との比較を行い、S&P500の特徴をさらに浮き彫りにします。
S&P500と他の主要指数・ETFの比較 (Step 5)
投資対象はS&P500だけではありません。
全世界株式(オルカン)やNASDAQ100(ナスダック100)、VTI(米国総合株式)、さらにはレバレッジ型NASDAQ100(いわゆるレバナス)など様々な指数・ETFがあります。
それぞれ何が違い、どんな投資戦略に向いているのかを比較してみましょう。
以下に主な指数とS&P500の比較を表にまとめます。
| 指数・ETF(愛称) | 投資対象 | 特徴・性質 | リスクとリターン傾向 |
| S&P500 | 米国の大型株500社 | 米国市場を代表する指数。時価総額加重でセクター分散あり。米国経済の成長を享受できる。 |
長期安定成長が期待できる。年率7-10%程度の実績(配当込)景気循環で変動。 |
| NASDAQ100 (ナスダック100、QQQ) |
ナスダック市場の |
ハイテク・グロース株中心(AppleやMicrosoftも含む)。 IT比率高く、近年S&P500以上に上昇。 |
リターン大だが変動も大。ハイテク偏重リスクあり。 |
| 全世界株式 (オルカン、ACWI等) |
全世界の株式: 約3000社 (米国60%+先進国30%+新興国10%) |
世界中に分散投資。米国偏重だが他国も含むため地政学リスク分散。 | 米国以外の成長が低迷するとリターンはS&P500下回る。 実際近年はS&P500の方が高。リターンリスクはやや低減。 |
| 全米株式 (VTIなど) |
米国の大型〜小型株 約4000社 | 米国市場ほぼ全体をカバー。S&P500に含まれない中小型株も組入。VTIは代表的ETF。 | S&P500と非常に高い相関。小型株分、リターンは僅かに上振れもボラティリティ増。差は年0.x%程度。 |
| レバレッジNASDAQ100 (レバナス) |
ナスダック100の 2倍の値動き |
ハイリスク・ハイリターン。短期で2倍を狙う投機的商品。 長期積立の議論もあるが賛否両論。 |
上昇期は利益2倍、暴落時は損失2倍以上。 2022年は基指数-33%に対し本指数約-60%以上の下落。 長期では元本割れリスク大。 |
それでは、それぞれの比較ポイントをもう少し解説します。
S&P500 vs NASDAQ100(QQQ)
NASDAQ100(ナスダック100)はニューヨークのナスダック市場に上場する時価総額上位100社からなる指数です(金融業は除外)。
AppleやMicrosoft、Amazon、Alphabet、Metaといった主力ハイテク企業はS&P500と重複しますが、NASDAQ100はそれに加えて半導体(Nvidia等)やネット企業、バイオなどグロース株が多く含まれます。
一方、伝統的な金融やエネルギー企業は含まれません。
リターン比較
近年、NASDAQ100の方がS&P500を上回る成長を見せています。
例えば2023年はNASDAQ100が約+49%と大幅上昇したのに対し、S&P500は+21.9%でした。
しかし2022年はNASDAQ100が-28%と暴落し、S&P500の-13%より下落率が大きかった。
このようにハイテク集中ゆえの値動きの大きさが特徴です。
リスク
NASDAQ100は構成企業数も100と少なく(しかも上位10社で半分以上)、セクター偏りも強いです。
そのため指数自体のボラティリティ(変動率)が高いです。
ITバブル崩壊時(2000-2002年)には-80%近い大暴落を経験しました。
一方S&P500は同期間で-40%程度で済んでいます。
どちらを選ぶ?
長期の安定性ではS&P500に軍配が上がりますが、より高成長を狙いたいならNASDAQ100という選択肢もあります。
ただしNASDAQ100偏重はハイテクバブル崩壊のリスクも孕むため、資産の一部として持つくらいが無難でしょう。
S&P500とNASDAQ100を組み合わせることで、米国株のコア・サテライト戦略をとる投資家もいます(コア=S&P500、サテライト=NASDAQ100など)。
NASDAQ100連動のETFとして有名なのがQQQ(キューキューキュー)です。
よく比較に挙がる「QQQ vs S&P500」という話題は、すなわちNASDAQ100指数 vs S&P500という意味になります。
S&P500 vs 全世界株式(オルカン)
全世界株式、通称「オルカン」(オール・カントリーの略)は世界中の株式市場に投資する指数です。
代表例がMSCI ACWI(All Country World Index)で、先進国23か国+新興国24か国の大型中型株を網羅し、約3000社が含まれます。
その中で米国株は約60%強を占めるため、全世界指数とS&P500の動きはかなり相関します。
しかし残り40%弱に他の国(日本5%、英国3.5%、フランス3%、中国など新興国合計約10% etc)が含まれる点で差異があります。
リターン比較
直近10年ほどは米国株が他国をアウトパフォームしたため、全世界株式のリターンはS&P500より低めでした。
例えば2021年はS&P500が約+28%の上昇だったのに対し、全世界株式(オルカン)は米国以外の伸び悩みもあり約+22%に留まりました。
長期的にも米国の優位が続いた結果、過去15年でS&P500が全世界株式を年率換算で2%以上上回るというデータもあります(SNS等で話題になる「S&P500 vs オルカン論争」の根拠です)。
分散効果
とはいえ将来も米国がずっと一番とは限りません。
全世界株式は地域分散によって、仮に米国市場が低迷しても他の地域の成長でカバーできる可能性があります。
特に新興国株やヨーロッパ株がこれから伸びれば、全世界株式の優位になる場面もありえます。(例:1990年代は日本株が世界時価総額の30%以上でしたが、その後日本停滞で米国が台頭した歴史があります。)
コスト面
全世界株式とS&P500の投資信託コスト差はごくわずかです。
例えば、ある全世界株式だと年0.113%, S&P500が0.0938%で、その差0.02%ほど。
長期には僅かな差ですが、分散のメリットと費用差をどう考えるかです。
どちらを選ぶ?
迷う場合、両者の違いは米国以外に投資するか否かです。
普遍性を重視するなら全世界株式(どの国が成長しても取りこぼさない)、効率を重視するならS&P500(過去実績が良く今後も米国中心と見る)と言えるでしょう。
S&P500 vs 全米株式(VTIなど)
全米株式とは、米国市場の大型〜小型株をすべて含むよう設計された指数です。
構成銘柄数は約4000〜5000に及びます。
S&P500との違いは、中小型株(約20%程度の比率)も含まれることです。
リターン・リスク
大型株500社だけのS&P500に対し、全米株式には残りの中小型約3500社が含まれます。
小型株は一般にリスクは高いものの期待リターンもやや高めとされています。
しかし米国市場では大型ハイテクの伸びが大きかったため、過去10年ではS&P500と全米株式の差はごくわずか(年率で+0.1〜0.2%程度全米株が上回るくらい)でした。
ただ時期によっては小型株が大きく寄与し、例えば1970-80年代には小型株効果で全米株指数がS&P500をアウトパフォームしたこともあります。
ETFの例
VTI(バンガード・トータルストックマーケットETF)が有名で、経費率0.03%。
どちらを選ぶ?
米国株オンリーと決めた場合、S&P500でも全米株式でも正直どちらでも大きな差は出ないでしょう。
強いて言えば「今後小型株が飛躍すると信じるなら全米株式」「シンプルに大型優良企業中心でいいならS&P500」となります。
コストもほぼ同等。
S&P500 vs レバレッジNASDAQ100(レバナス)
SNSやYouTubeで話題になった「レバナス」とは、NASDAQ100指数の2倍の値動きを目指すレバレッジ型投資信託の俗称です。
S&P500とは性格が大きく異なるため、本来単純比較すべきものではありませんが、FIRE志向の一部で「レバナスで資産倍増を狙う」といった熱狂もあったため取り上げます。
爆発的リターンとリスク
レバナスはNASDAQ100の日々の変動幅を2倍にする設計です。
実際、2020年〜2021年でレバナス投信は基準価額が数倍になる急騰を見せました。
しかし下落局面では壊滅的です。
2022年にNASDAQ100が約-33%下がった際、レバナスは-60%以上の大幅下落となり、多くの積立投資家が評価額半減以上の痛手を被りました。
長期投資に不向き
理論上、指数が上下するときレバレッジ商品のほうが複利効果で不利になります(ボラティリティ・ドラッグ)。
つまり長期間持ち続けると指数が戻ってもレバレッジ商品は元本割れしている可能性があります。
そのためレバナスは短期勝負に向き、積立長期には不向きとの意見が大勢です。
位置づけ
S&P500のようなコア資産とは全く性質が違い、FIREを急ぐあまりレバナス一本に全力投資するのは極めて危険で、実際2022年の下落で「FIRE達成目前から振り出しに戻った」人も散見されました。
以上、主要な指数との比較をしました。
それぞれメリット・デメリットがありますが、自分の信念に合ったものを選び、納得感のあるポートフォリオを組んでみてください。
S&P500と長期投資:FIREや積立との相性 (Step 6)
ここまでS&P500の特徴を見てきましたが、それを踏まえて長期投資における位置づけについて考えてみます。
長期投資の王道としてのS&P500
S&P500は、以下のような長期投資におけるの強みがあります。
経済成長への参加
米国経済は長期的に成長を続け、イノベーションを生み出してきました。
S&P500に投資することは、その米国経済の成長果実を享受し続けることです。
個別企業は盛衰がありますが、入替を行う指数ゆえ常に「今」のトップ企業群に投資され続けます。
複利の力
前述したように長期リターンは年7~10%ありました。
この水準で複利運用すれば20〜30年で資産は数倍以上になります。
過去には$100を1957年に投資して放置したら2025年末には約9万ドル以上になったという試算もあるほどです。
手間いらずで合理的
個別株を調べ選ぶ労力をかけずとも、市場平均に乗るだけでプロの大半を上回る成績となることが証明されています(アクティブファンドの多くは長期でS&P500に負ける。
手間いらずで勝率が高いのは大きな魅力です。
積立投資との組み合わせ
積立投資(ドルコスト平均法)でS&P500ファンドを買い続ける手法は、多くの投資本や専門家が薦めています。
その利点は、市場の高値づかみリスクを減らし、暴落時にはたくさん買えるという点です。
例えば毎月一定額をS&P500に積み立てていくと、価格が安いときには口数を多く買い、高いときには少なく買うことになり、平均購入単価を平滑化できます。
長い目で見れば、タイミングを気にせず心理的にも楽に投資を続けられるでしょう。
著名投資家の見解:ウォーレン・バフェットはS&P500をどう見ているか?
最後に、著名投資家のコメントも確認しておきましょう。
中でも有名な投資家でもあるウォーレン・バフェット氏はS&P500をどう見ているのでしょうか?
彼の過去のインタビューなどの発言をいくつかまとめると
「平均的な投資家にとって最も賢明なのは、S&P500に連動する超低コストのインデックスファンドに継続的に投資することだ」
「嵐にも負けず愚直にS&P500ファンドを買い続けなさい」 – 2017年のインタビューで「暴落相場でも継続的にS&P500を買い増せ」
「死後、妻には現金の10%を短期国債、90%をS&P500に投資せよ」
というメッセージが残されています。
ところが…..
知っておきたいのは、S&P500 ETFがバークシャーのポートフォリオに占める割合が非常に小さかった点です。
具体的には、2024年9月末時点でこれらのETFの時価総額は約4500万ドル(約67億円)で、バークシャーの総資産(約3600億ドル)から見るとわずか0.02%程度に過ぎませんでした。
つまりS&P500に対する過去の発言は「投資の専門知識がない個人投資家」向けのアドバイスであり、彼自身の投資戦略とは必ずしも一致しません。
ですので投資の神様ウォーレンバフェットがあんなこと言っていたからと過信しすぎには注意が必要です。
まとめ
長大な記事となりましたが、最後に要点を振り返りましょう。
S&P500とは米国の大型株500社から成る株価指数。1957年算出開始。
米国株式市場の約80%をカバーし、市場全体の動きを代表。時価総額加重で構成。
特徴としてハイテク企業を中心に上位銘柄が偏重(Apple等上位10社で約35%)。
11セクターに分散するがIT比率高め。委員会が銘柄選定し、定期的に入替あり。
歴史的実績としては長期年平均リターン約7〜10%(配当込)。配当利回りは現在1.4%前後 と低めだが過去には3%程度。
年によって+30%超から-30%超まで変動するが、過去70%の年でプラス成長。
S&P500は派手さはないものの、過去のデータや専門家の意見が裏付けるように、米国経済の力強さを背に時間を味方につけた長期投資に適したものと言えるかもしれません。
※本記事は投資助言を行うものではなく、参考情報としてご利用ください。




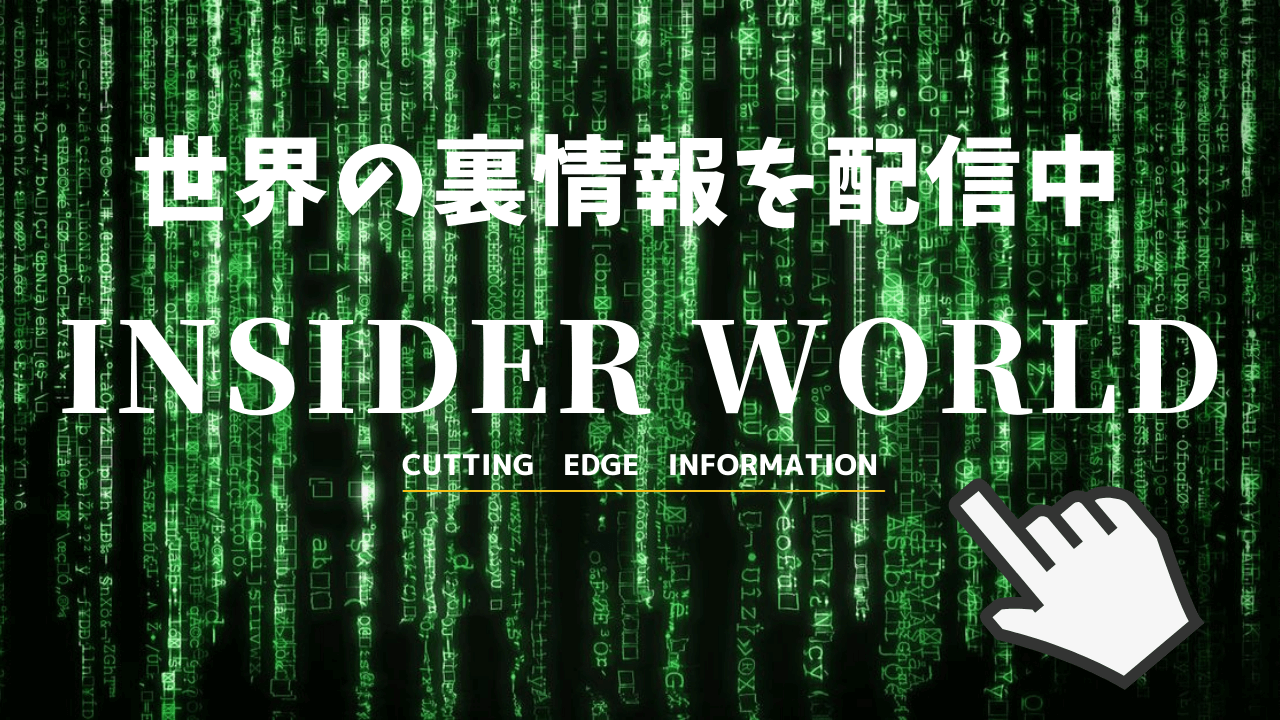

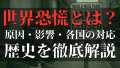
コメント