※本記事は投資助言を行うものではなく、参考情報としてご利用ください。
Masakiです。
この記事では、世界史上最も深刻な経済危機の一つ「世界恐慌」について詳しく解説します。
この一連の出来事を知ることで、投資家やビジネスマンの皆さんは現代の経済危機への備えやリスク管理の知恵を得ることができます。
また歴史に関心のある方にとっても、世界規模の不況が社会や政治にどんな影響を及ぼしたのかを学ぶことで、現代社会を読み解くヒントが得られるでしょう。
たとえば、もし突然の株価暴落や世界的な不況が再び起きたら自分の資産やビジネスはどうなってしまうのか?
本記事を読み進めれば、そうした不安への答えや対策のヒントがきっと見つかるはずです。
世界恐慌前夜:1920年代の繁栄と隠れた不安
世界恐慌を理解するためには、その直前の時代、すなわち1920年代(いわゆる「狂騒の20年代」)の状況を見ておく必要があります。
第一次世界大戦が1918年に終結した後、欧米諸国は戦後復興と新しい技術革新の波に乗り、1920年代を通じて大きな経済成長を遂げました。
特にアメリカは世界経済の牽引役となり、自動車(フォードのT型など)の普及や家電製品(ラジオ、冷蔵庫など)の生産増加に支えられて前例のない好景気に沸いていました。
フォードの流れ作業方式に代表される生産性向上により、工業製品の大量生産・大量消費が可能となり、都市の中産階級は車や電化製品を手に入れ、郊外生活を楽しむようになります。
株式市場も右肩上がりで、ニューヨーク株式取引所(ウォール街)では株価が上昇を続け、人々はこぞって株式投資に熱狂しました。

一般市民も証券会社から借金(信用取引)をしてまで株を買う状況となり、新聞やラジオで株式情報が日々報じられるなど、投機ブームが社会現象となりました。
また、不動産市場でもフロリダの土地バブルに見られるように、投機的な熱狂が広がりました(もっとも1926年のハリケーン被害でこの土地バブルは崩壊しています)。
しかし、この表面的な繁栄の陰で、いくつかの不安要素が存在していました。
一つは農業分野の不振です。
戦時中に需要が旺盛だった農産物は、戦後に価格が下落し、多くの農家は借金を返済できずに苦しんでいました(1920年代を通じた農業不況)。
また、新しい工業製品の普及に伴い経済構造が変化し、石炭産業や繊維産業など旧来の産業は過剰生産と競争激化で不況に陥る部分もありました。
所得格差も広がっており、大企業の利益は増大していた一方で労働者や農民の生活はそれほど豊かになっていませんでした。
さらに、株価の上昇自体が実体経済の成長を超えて加速しており、少しでも楽観が崩れればバブルがはじけかねない危うさも指摘されていました。
1920年代後半には、利上げ局面に入っていたこともあり、市場には微かな緊張感が漂い始めていました。
このように、1920年代の繁栄の中に潜んでいた過剰投機や所得格差、産業間の不均衡といった問題が、1929年の株価暴落によって一気に表面化することになるのです。
世界恐慌とは何か?いつ起きた出来事なのか
世界恐慌(せかいきょうこう)とは、1929年に始まり1930年代を通じて世界を襲った前例のない規模の経済危機のことです(英語ではGreat Depression(グレート・デプレッション)、日本では単に「大恐慌」とも呼ばれます)。
アメリカ・ニューヨークの株式市場で1929年10月24日に株価の大暴落(いわゆる「暗黒の木曜日」)が起こったことをきっかけに世界中へ波及しました。

この未曾有の不況は各国で長引き、一般に1930年代後半(国によっては第二次世界大戦勃発頃)まで影響が及んだとされています。
世界恐慌の期間中、世界全体の国内総生産(GDP)は約15%も減少し、国際貿易は半分以下に落ち込むなど経済活動が大幅に縮小しました。
失業率も急上昇し、アメリカでは約4人に1人が失業し、一部の国では30%以上という深刻な失業に見舞われました。
このような経済崩壊は社会の混乱や政治の変動も引き起こし、多くの国で政権交代や社会不安をもたらすとともに、後の世界戦争への伏線ともなったのです。
世界恐慌の原因:なぜこれほど深刻な不況になったのか
ではいったい世界恐慌となった原因は何だったのか?
株価バブルの崩壊と金融システムの危機
世界恐慌の直接的な引き金となったのは、1920年代後半の株式市場バブルの崩壊でした。
アメリカでは「狂騒の20年代」と呼ばれる好景気の中で株価が急騰し、多くの人々が借金をしてまで株式投資を行う過熱状態に陥っていました。
しかし1929年秋に株価が暴落すると、信用取引で投資していた人々は莫大な借金を抱え、一夜にして破産する者も続出しました。
当時、著名な経済学者ですら「株価は恒久的に高い水準に到達した」と発言するほど楽観的で(経済学者アーヴィング・フィッシャーによる1929年10月の有名な言葉)、それだけ人々はバブルの危うさに気付いていなかったのです。
株価大暴落は投資家の信頼を失わせただけでなく、金融機関にも深刻な打撃を与えました。
多くの銀行が株式市場に融資をしていたため、顧客から預かった資金の回収が困難になり、取り付け騒ぎ(銀行から預金を引き出そうとするパニック)が各地で発生しました。
結果として1930年代初頭にはアメリカだけで数千もの銀行が倒産し、人々の預金が消失してしまいました。
銀行の連鎖破綻により企業への貸し出しも滞り、資金繰りが悪化した企業の倒産や生産縮小が相次ぎました。
この金融システムの崩壊が、株価暴落のショックを実体経済全体の長期的な大不況へと変えていく要因となったのです。
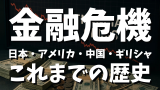
経済構造の問題:過剰生産と所得格差
世界恐慌を深刻化させた背景には、当時の経済構造上の問題、特に供給過剰と需要不足のミスマッチがありました。
1920年代、技術革新と大量生産によって工業製品や農産物の生産量は飛躍的に増大しましたが、それに見合うだけの購買力が人々に備わっていませんでした。
第一次世界大戦後、戦時需要の反動で農産物価格が下落し、農家は慢性的な不況(農業不況)に苦しんでいました。
一方、工業製品に関しても生産能力の拡大に比べ賃金など労働者の所得の伸びが追いつかず、富裕層と一般大衆の所得格差が広がっていたため、世間全体の消費需要はそれほど伸びていませんでした。
好景気の間は自動車や家電などを割賦販売(ローン)で購入する動きが支えとなっていましたが、不況の兆しとともに人々は支出を切り詰め、売れ残りの在庫が積み上がりました。
在庫過剰となった企業は生産を減らし、労働者の解雇や賃下げを行ったため、所得減少によってさらに消費が落ち込むという悪循環が生まれました。
つまり、世界恐慌前夜には経済の基盤に需要不足という脆弱性が存在しており、これがひとたびショックが起きた際に不況を一層深刻化させる一因となったのです。
金本位制とデフレ連鎖の影響
世界恐慌の拡大要因としては、当時ほとんどの主要国が採用していた金本位制という通貨制度の存在も見逃せません。
金本位制では各国通貨の価値が金との兌換(交換)によって保証され、為替レートが固定されていましたが、この体制下では各国が自由に金融緩和を行うことが難しくなります。
株価暴落後、人々が銀行から預金を引き出して金(ゴールド)に換えようとすると、各国の中央銀行は金準備を守るために金利を引き上げ、通貨供給を絞る対応を取らざるを得ませんでした。
その結果、不況にもかかわらず金融引き締めが行われるという悪循環が生まれ、各国で物価が下落するデフレが進行しました。
特に金準備の少なかったドイツやオーストリアなどは早々に金が流出し、銀行の休業や通貨危機に陥りました。
イギリスも1931年に金本位制を維持できなくなり金との兌換を停止(事実上の金本位制離脱)しますが、これは世界的な金本位制崩壊の引き金となりました。
一方、アメリカやフランスは自国に金が流入しているにもかかわらず通貨供給を増やさなかったため、世界的に貨幣不足(信用収縮)が深刻化しました。
金本位制を放棄せずデフレ政策を続けた国(フランスなど「金ブロック」と呼ばれる国々)は景気回復が大幅に遅れ、一方でいち早く金本位制から離脱した国(イギリスや日本など)は通貨安による輸出促進もあって比較的早期に不況から脱することができました。
このように国際金本位制の制約は各国の柔軟な経済対策を妨げ、不況を世界全体に連鎖させた要因となったのです。
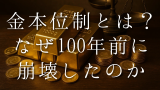
保護主義的政策と世界貿易の縮小
世界恐慌に対して各国が初期に取った対応策の一つとして、保護主義的な貿易政策の強化が挙げられます。
自国の産業や雇用を守ろうと考えた各国政府は、輸入品に高関税を課すなど他国との貿易を制限する措置を相次いで実施しました。
アメリカでは1930年にスムート=ホーリー関税法が成立し、歴史的な高関税率で幅広い輸入品に課税した結果、カナダやヨーロッパ諸国も報復的に関税引き上げを行いました。
この関税戦争によって国際貿易は急激に縮小し、世界全体の貿易額は数年間で半分以下に落ち込んでしまいました。
輸出に依存していた国や農産物・原材料の輸出で生計を立てていた地域(ラテンアメリカや東南アジアの植民地など)は、国際市場の需要喪失によって深刻な打撃を受けました。
また、イギリスやフランスなどは植民地(帝国)の内部で経済圏を形成するブロック経済へと舵を切り、域内の貿易は維持する一方で域外からの輸入品には高関税を課すようになりました。
例えば1932年のイギリス連邦経済会議(オタワ会議)では、イギリスと自治領・植民地間で互いに関税を低減し、域外の国には高い関税を課す「帝国特恵」政策が打ち出されました。
これにより、世界経済は複数のブロックに分断され、各ブロック間の貿易はさらに滞ることになりました。
保護主義政策の連鎖は、各国が協調して不況対策を行う機会を失わせ、結果的に世界恐慌の長期化・深刻化を招いたと評価されています。
危機対応の遅れ:中央銀行と政府の失策
世界恐慌がここまで深刻化した背景には、各国政府および中央銀行の初動対応の遅れや誤りもありました。
なお、フーヴァー大統領は危機当初「景気回復はすぐそこまで来ている」(Prosperity is just around the corner)と楽観的な声明を繰り返し、迅速な対策の遅れを招いたとも評されます。
当時のアメリカ政府(フーヴァー大統領)は、経済への政府介入を極力避ける立場をとり、大規模な財政出動による景気対策を行わなかったため、不況の悪化に歯止めをかけられませんでした。
失業保険制度もなく、社会救済は慈善事業に任されていたため、失業者の生活は放置され、一層消費が冷え込む結果となりました。
中央銀行の金融政策の面でも問題が指摘されています。
アメリカの連邦準備制度(FRB)は、株価暴落後も市中銀行への貸出(最後の貸し手としての役割)や積極的な国債買い入れによる資金供給を十分に行いませんでした。
そのためマネーサプライ(通貨供給量)はむしろ縮小し、デフレ圧力が強まりました。
F・ルーズベルト大統領自身も後に、就任前のFRBの対応について「まるで臆病風に吹かれたようだった」と批判しています。
イギリスやフランスでも、金本位制維持に固執するあまり金融緩和が遅れ、不況を深刻化させたとの反省が残りました。
実際、1933年のロンドン世界経済会議では米欧間の政策対立から協調が得られず、通貨安競争を止める国際合意は失敗に終わりました。
このように、政策当局の対応の遅れと誤りもまた、大恐慌を単なる景気循環の後退ではなく未曾有の危機へと押し上げた一因だったのです。
世界恐慌の影響:経済・社会・政治への余波
世界恐慌は単なる経済指標の上での数字の下落に留まらず、人々の暮らしや社会の在り方、さらには各国の政治体制にまで深刻な影響を及ぼしました。
ここでは、世界恐慌がもたらした経済面・社会面・政治面での影響について概観します。
経済への影響:記録的な失業と貧困の拡大
世界恐慌によって各国経済は崩壊的な打撃を受け、失業率は記録的な高さに達しました。
アメリカでは1933年頃に労働力人口の4人に1人が職を失い、ドイツでも1932年には約600万人(労働力人口の30〜40%)が失業したとされています。
イギリスやカナダなど他の先進国でも失業率は20%前後に上昇し、都市には職を求めてさまよう失業者が溢れかえりました。
収入を絶たれた人々は貯金を取り崩すか慈善事業に頼るしかなく、多くの家庭が極度の貧困に陥りました。
銀行の倒産によって預金が引き出せなくなり、一夜にして全財産を失った人々もいました。
住宅ローンの支払いができずに家を失う家族も相次ぎ、都市郊外には失業者が集まってバラック小屋やテントで暮らす仮住宅地(スラム)が出現しました。
農村部でも農産物価格の暴落で農家の収入が激減し、多くの農場が借金を返せずに差し押さえられました。
アメリカの中西部では追い打ちをかけるように深刻な干ばつ(ダストボウル)も発生し、農民が土地を離れて他地域へ流出する事態も起きました。
世界全体で見ても、1930年代前半には何千万人もの人々が失業と貧困に苦しんだと推計されます。
さらに物価下落(デフレ)により企業の利益が減少し賃金も引き下げられ、働いている人々の生活も窮屈になりました。
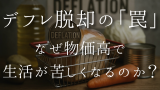
税収が落ち込んだ各国政府は財政難に陥り、社会保障や救済措置の拡充にも限界がありました。
大恐慌の影響の深刻さを数値で見るために、主要国の工業生産指数(1929年=100)の推移を示します。特に不況が底を打った1932年頃には、アメリカやドイツで生産水準が半分以下に落ち込んでいたことがわかります。
| 国 | 工業生産指数(1929年=100) |
|---|---|
| アメリカ | 100 → 54(1932年) |
| イギリス | 100 → 84(1932年) |
| フランス | 100 → 69(1932年) |
| ドイツ | 100 → 53(1932年) |
| 日本 | 100 → 98(1932年) |
| ソ連 | 100 → 183(1932年) |
このように世界恐慌は人々の生活基盤を直撃し、大半の国民を経済的苦境に追い込みました。
社会への影響:生活の困窮と社会不安の増大
経済的な苦境は社会にも暗い影を落としました。
仕事や家を失った人々の間では将来への希望を失い、自暴自棄になる者も現れました。
各地でホームレスや浮浪者が増加し、慈善団体による炊き出し(スープキッチン)の列に並ぶ姿が日常的に見られるようになりました。
栄養不足や医療費の負担から体調を崩す人も多く、幼い子供が十分な食事をとれずに空腹のまま学校に通う(欠食児童)といった事例も各国で報告されています。
家計を助けるために子供が学校を中退して労働に出たり、遠く他の地域へ出稼ぎに行く人も増え、家族やコミュニティの形態にも変化が生じました。
失業者によるデモ行進や抗議集会も頻発し、治安当局との衝突に発展するケースもありました。
1932年のアメリカでは、第一次大戦の退役軍人がボーナス支給を求めてワシントンD.C.に集結する「ボーナスアーミー」の抗議が起こり、政府が軍を投入して強制排除する事件も起きています。
また、人々の不満は社会の弱者や少数派に向けられることもあり、移民や特定の民族・人種がスケープゴート(責任転嫁)の対象となる場面も見られました。
たとえばアメリカでは不法移民の取り締まりが強化され、メキシコ系労働者が大量に送還されました。
ドイツでもユダヤ人などに経済不振の責任をなすりつける反ユダヤ主義が台頭しました。
一方で、この苦難の時代において家族や地域社会の助け合いの精神が生まれ、相互扶助で困難を乗り切ろうとする動きも各地に見られました。
アメリカ各地では公園や空き地に失業者やホームレスがバラックを建てて集団で寝起きするいわゆる「フーヴァービル」(当時のフーヴァー大統領への皮肉を込めた呼称)が生まれ、都市の景観も一変しました。
職を求めて国内を渡り歩く人々も増え、貨物列車に無賃乗車して移動するホーボー(浮浪労働者)の存在もこの時代の象徴となりました。
総じて、世界恐慌は社会全体に大きな不安と混乱をもたらし、人々の価値観や生活様式にも深い爪痕を残したといえます。
政治への影響:政権の変動と国際情勢の悪化
経済と社会の混乱は各国の政治にも大きな変動をもたらしました。
従来の政党や指導者は深刻な不況を解決できないことで国民の信頼を失い、多くの国で政権交代や政治体制の変化が起こりました。
アメリカでは1932年の大統領選挙でフーヴァー大統領が大敗し、積極的な経済介入を訴えたフランクリン・ルーズベルトが当選してニューディール政策を開始しました。
イギリスでは労働党政権が財政悪化に対応できず崩壊し、保守党を中心とする挙国一致内閣(マクドナルド内閣)が成立しました。
フランスでも慢性的な不況から政治が不安定化し、1936年には左派連合の人民戦線内閣(レオン・ブルム首班)が誕生して社会改革を試みました。
ドイツでは経済危機によって民主的なヴァイマル共和国政府への支持が崩壊し、国民は過激な解決策を掲げるナチス(ヒトラー)を支持するようになりました。
1933年にヒトラー政権が成立すると、議会制民主主義は瞬く間に解体され、一党独裁と軍備拡張による失業対策が進められました。
イタリアでは既にムッソリーニのファシスト政権下にありましたが、世界恐慌の影響は相対的に小さいながらも経済の統制と軍事優先の傾向が強まりました。
日本でも、昭和恐慌による社会不安の中で政党政治への失望が広がり、軍部が台頭する下地が作られました。
1932年には犬養毅首相が暗殺され(五・一五事件)、以降は軍人や強硬派の政治家が実権を握る体制に移行していきました。
このように世界恐慌は各国で政治的急転換をもたらし、民主主義が後退して独裁や権威主義体制が広がる契機となりました。
ただし、すべての国が独裁化したわけではありません。
例えば北欧諸国(スウェーデンやデンマークなど)では、恐慌の影響は受けたものの民主主義体制を維持し、いち早く金本位制から離脱して積極的な公共事業や社会福祉政策を採用することで社会の安定を図りました。
こうした国々では、社会民主主義政党が政権を握り、経済危機に際して弱者救済を重視する政策を実施したため、極端な政治勢力の台頭を防ぐことに成功しています。
国際関係においても、不況下で各国は自国優先の姿勢を強め、協調よりも対立が目立つようになりました。
経済問題に追われた英仏などの大国は国際協調による平和維持より内政を優先し、ドイツ・日本・イタリアなどは侵略的な外交に乗り出していきます。
その結果、1930年代後半には第二次世界大戦へと繋がる国際緊張の高まりが現実のものとなっていきました。
主要国の対応策:それぞれの国は恐慌にどう立ち向かったか
それではこの世界恐慌時に各国はどう立ち向かったのかを見ていきましょう。
アメリカ合衆国:ニューディール政策による経済再建

世界恐慌の震源地となったアメリカでは、当初フーヴァー大統領が市場原理に委ねた消極的対応を取っていたため、不況は悪化の一途を辿りました。
銀行や企業への政府支援策は限定的で、ボランティアによる救済を促すに留まり、失業者やホームレスは増大するばかりでした。
1932年には景気底打ちの気配が見えない中、フーヴァー政権もようやく復興金融公社(RFC)を設立して銀行や鉄道会社などへの融資を開始しましたが、時既に遅く劇的な効果は上げられませんでした。
1933年に就任したフランクリン・ルーズベルト大統領は、新たな経済政策「ニューディール政策」を打ち出し、政府が経済に積極介入する路線へと転換しました。
ルーズベルト大統領は就任演説で「我々が恐れなければならない唯一のものは、恐怖そのものである」と国民に呼びかけ、人々に希望を取り戻させようとしました。
ニューディール政策では、まず銀行システムの立て直しが図られました。
就任直後に銀行休業令(バンクホリデー)を発し、健全な銀行以外は営業を再開させずに整理し、連邦預金保険公社(FDIC)を設立して預金の保護を開始しました。
また証券取引委員会(SEC)を創設して株式市場を規制するなど、金融システムの改革を進めました。
さらに、公共事業を大規模に実施して雇用創出を図りました。
代表例としては、失業した若者を農林業関連の作業に従事させた市民保全部隊(CCC)や、ダム・道路建設などインフラ整備を担った公共事業促進局(WPA)などが挙げられます。
テネシー川流域開発公社(TVA)のように地域開発と雇用創出を兼ねた大型プロジェクトも行われました。
農業分野では農業調整法(AAA)により生産調整と農民支援が図られ、工業分野では全国産業復興法(NRA)によって価格・生産調整や労働者保護(労働時間短縮や最低賃金設定)が試みられました。
ただしNRAは違憲判決で失効し、ニューディール政策にも修正を迫られますが、その後も社会保障法の制定(年金制度の創設)など福祉政策の整備が進められました。
ニューディール政策の結果、経済は徐々に下げ止まり、最悪期を脱することに成功しました。
失業率は一時的に大幅に改善し(1937年には14%程度まで低下)、労働者の労働組合組織率が上昇するなど社会の安定化にも寄与しました。
しかし景気回復は決して順調一途ではなく、1937年には財政引き締めの失策から再び不況(ルーズベルト不況)が訪れるなど、ニューディールにも限界がありました。
それでも、ニューディール政策は大恐慌への対処として政府が経済に介入し国民を救済するという前例を作り、アメリカ社会に安定と希望をある程度取り戻した点で大きな意味がありました。
最終的にアメリカ経済が完全に活力を取り戻すのは第二次世界大戦による軍需景気を待つことになりますが、ニューディールはその繋ぎとして重要な役割を果たしたと言えるでしょう。
日本:昭和恐慌と高橋是清による積極財政
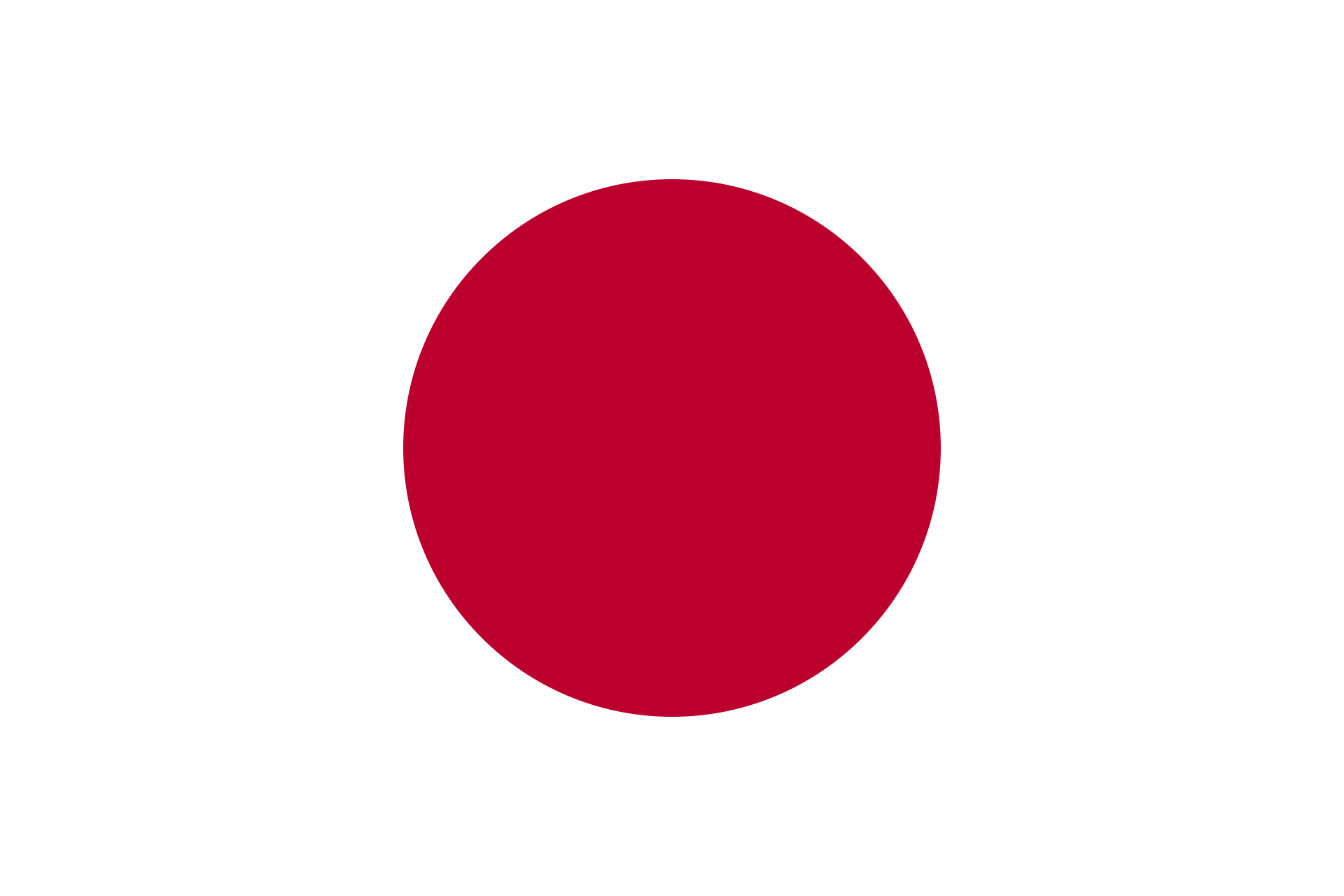
日本では、アメリカ発の世界恐慌の波が押し寄せた上に、ちょうど同じ時期の1930年に金本位制復帰(いわゆる金解禁)を行ったことが重なり、「昭和恐慌」と呼ばれる深刻な不況に陥りました。
1929年以前から日本経済は震災恐慌(1923年)や金融恐慌(1927年)で弱っており、金解禁によるデフレ政策は打撃に追い打ちをかける形となりました。
最大の輸出品であった生糸の価格が暴落し、農村は未曾有の不況に見舞われました。
農家は繭や米が売れず現金収入が途絶え、娘の身売りや欠食児童が急増する悲惨な状況となりました。
都市部でも企業の倒産や失業が広がり、日本全体が深刻な不景気に陥りました。
この危機に対し、1931年末から就任した大蔵大臣・高橋是清が果断な経済政策を実施します。
高橋蔵相は「今は非常時である」として異例の積極財政に踏み切り、軍備拡充を含む政府支出の拡大でデフレ不況の克服を図りました。
まず金解禁を撤回して金本位制を離脱し、通貨(円)の平価を切り下げることで輸出競争力を回復させました。
同時に日銀引受による国債発行(事実上の赤字財政)で大規模な財政出動を行い、軍事費や公共土木事業に資金を投入して景気刺激を図りました。
さらに農村救済のための農山漁村経済更生運動を推進し、疲弊した農家の再建支援にも乗り出しました。
その結果、日本経済は欧米諸国に先駆けて急速に回復し、1933年頃から生産・雇用が持ち直しました。
実際、1935年までに日本の鉱工業生産は恐慌前の水準を大きく上回るまで増加し、世界でも最も早い景気回復を遂げました。
ただしこの回復は財政赤字と軍拡に依存した面が強く、1930年代半ばにはインフレの兆候も現れ始めます。
高橋蔵相は1936年度予算で軍事費の抑制と公債整理に転じようとしましたが、軍部の強い反発を招きました。
結局1936年2月、高橋是清は青年将校によるクーデター未遂事件(二・二六事件)で殺害され、以後は軍部がさらに発言力を強めて軍事費拡大路線が継続されることになります。
高橋財政による積極策は短期的には昭和恐慌を克服する上で大きな成功を収めましたが、その後の軍国主義への傾斜を助長した側面も否めません。
なお、日本はイギリス連邦のブロック経済によって伝統的な輸出市場(インドなど)を閉ざされたため、満州国や中国華北、台湾などの「円ブロック」内で原料確保と市場拡大を進めていくことになりました。
こうした独自の経済圏の構築は、のちの大陸侵略と一体となった経済政策でもあり、日本の戦時経済への移行と表裏一体の関係にありました。
世界恐慌に早期対応して不況を脱した例として、高橋是清の政策は世界的にも注目され、「大恐慌を克服した唯一の財務大臣」と評価されることもあります。
ドイツ:ナチス政権の公共事業と軍備拡大による急速な回復

世界恐慌で最大級の打撃を受けたドイツでは、当初ブリューニング内閣(1930-1932年)が財政緊縮と賃金引下げによるデフレ政策で危機に対処しようとしました。
しかしこの政策は需要をさらに冷え込ませ失業を悪化させたため、国民の支持を失い政権は崩壊しました。
後を受けたパーペン内閣・シュライヒャー内閣も有効な手立てを打てないまま短命に終わり、政治的混乱の中で1933年1月にヒトラー率いるナチ党が政権の座に就きました。
ヒトラー政権はただちに独裁体制を固め、経済面では従来の緊縮路線を転換して国家による積極的な景気刺激策を講じました。
まず失業対策として大規模な公共事業が開始され、アウトバーン(高速道路)建設をはじめ住宅建設やインフラ整備に多くの失業者が動員されました。
また国家労働奉仕団(RAD)を組織して若年層に労働と訓練の場を与え、徴兵制の復活によって軍に人員を吸収するなど、多方面から失業解消に取り組みました。
財政面では、軍需生産に必要な支出を公然と増やし、支払いを後回しにできる政府手形(メフォ手形)を活用して事実上の借金財政を展開しました。
1936年には四カ年計画を打ち出し、原料や食料の自給体制(経済のブロック化・自給自足化)を築きつつさらなる軍備拡張を進めました。
これらナチスの経済政策により、ドイツ経済は短期間で劇的な回復を遂げます。
失業者数はヒトラー政権成立時の600万人超から、1936年には1万人台にまで急減し、事実上ほぼ完全雇用が実現しました。
公共事業と軍需生産の拡大によって工業生産も急伸し、1930年代後半にはドイツは世界で最も経済成長率の高い国の一つとなりました。
ただし、この回復は自由競争によるものではなく国家統制と軍事目的による特異なものであり、持続可能性にも疑問がありました。
実際、軍拡に伴う財政負担は巨額となり、1938年には2度にわたり政府支払いの延期(事実上のデフォルト)を余儀なくされる事態も生じています。
さらにナチスの繁栄は他国への侵略と密接に結びついており、その「成功」は第二次世界大戦の勃発へと直結することになりました。
それでも当時の人々にとって、ナチス政権下で失業が解消し生活が安定した事実は大きく、世界恐慌下で苦しむ他国からもドイツの急速な経済再建は驚きをもって見られました。
ヒトラーは国民に「仕事とパン」を約束し、巨額の公共事業と軍備拡張によって実際に失業者に職を与えたことで熱狂的な支持を得ました。
イギリス:金本位制からの離脱とブロック経済への転換
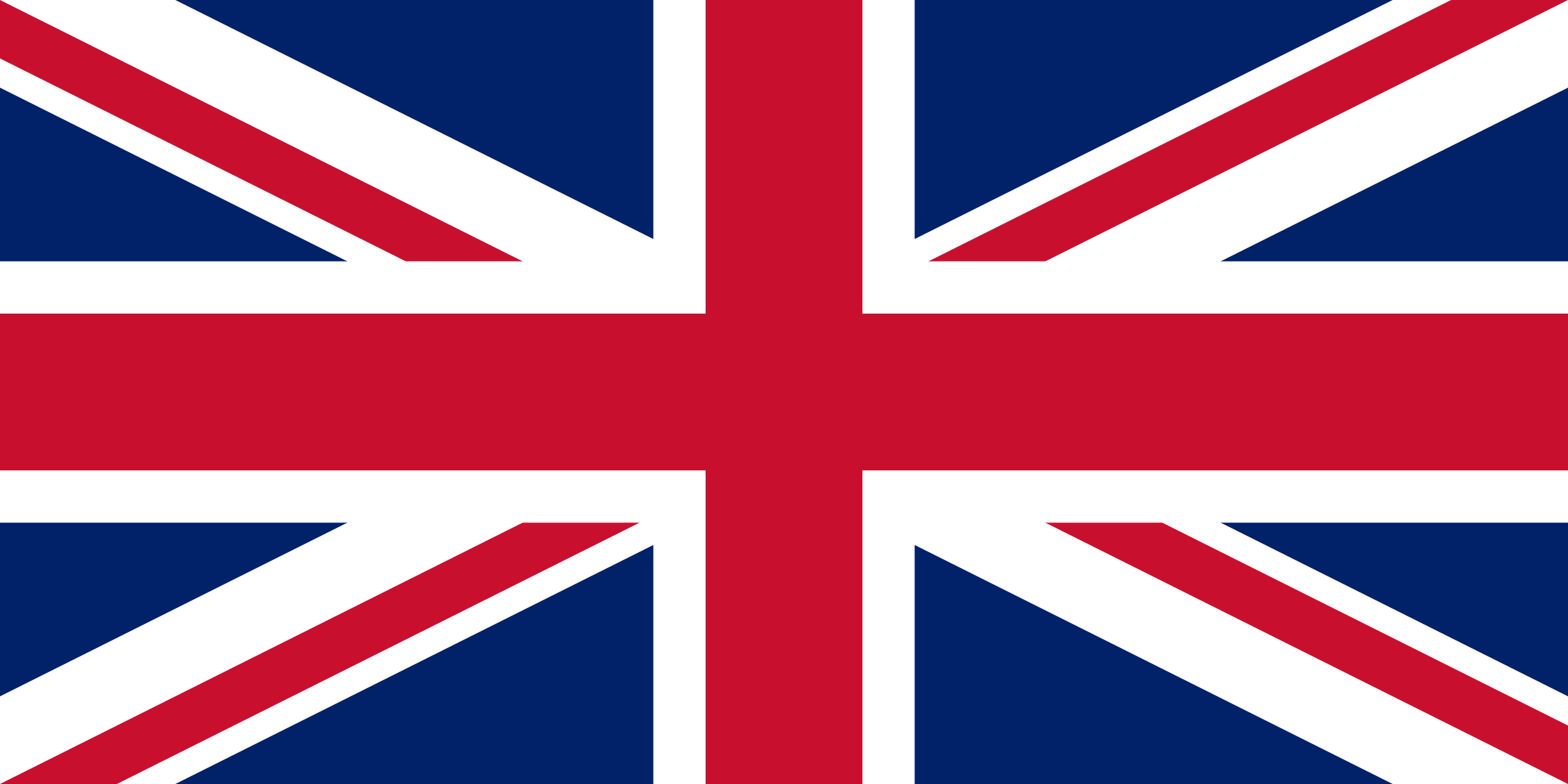
イギリスでは、恐慌当初は高失業に苦しみながらも、議会制民主主義の枠組みは維持されました。
1929年に始まった不況に対し、当初は従来の自由放任的な方針で対応しましたが、状況は悪化し、失業率は1932年に20%を超えるまで上昇しました。
深刻化する恐慌の中で、1931年には労働党のマクドナルド政権が瓦解し、挙国一致内閣(ナショナル・グヴァメント)が成立します。
同年9月、イギリスはついに金本位制の維持を断念し、ポンドと金との兌換停止(ポンド平価の約30%切下げ)に踏み切りました。
この決断によってポンド安となり、イギリス製品の輸出競争力は回復しました。
また、金本位制離脱により国内の金融政策に自由度が生まれ、イングランド銀行は金利を史上最低水準まで引き下げる「チープマネー政策」を導入しました。
低金利は住宅建設ブームを呼び起こし、イングランド南部を中心に景気を下支えしました。
一方で、イギリスは1932年のオタワ連邦経済会議で、自国と自治領・植民地との間で特恵関税によるブロック経済を形成する方針を打ち出しました。
それまで自由貿易の旗手だったイギリスが初めて保護関税政策に踏み切った出来事であり、海外からの輸入品には一律10%の関税(翌年さらに引き上げ)を課しました。
この帝国ブロック経済により、イギリスは大英帝国域内の貿易を活発化させて域外の需要減少を補おうと図りました。
こうした政策転換の結果、イギリス経済は徐々に安定を取り戻し、GDP成長率は1934年以降プラスに転じました。
ただし、地域間の格差は残り、ロンドンなど南部は住宅建設や新興産業で潤った一方、重工業地帯のある北部・スコットランド・ウェールズでは高失業が慢性化しました。
政府は1934年に特定地域法(Special Areas Act)を制定して失業の激しい地域への支援を試みましたが、効果は限定的でした。
1936年には高失業に苦しむ北東部ジャローの住民がおよそ450km離れたロンドンまで徒歩で陳情に向かう「ジャローマーチ」を行い、政府に仕事を要求しました。この出来事は当時の深刻な失業問題を象徴するものとして語り継がれています。
それでも第二次世界大戦前夜までに失業率は一桁台に低下し、イギリスは議会政の枠内で恐慌の最悪期を脱することに成功しました。
大規模な政府支出で景気回復を図ったアメリカやドイツと比べると穏健な対策ではありましたが、ポンド切下げと金利引下げ、帝国内市場の活用という方針が一定の成果を収めたといえます。
フランス:金ブロックに留まり遅れた景気回復
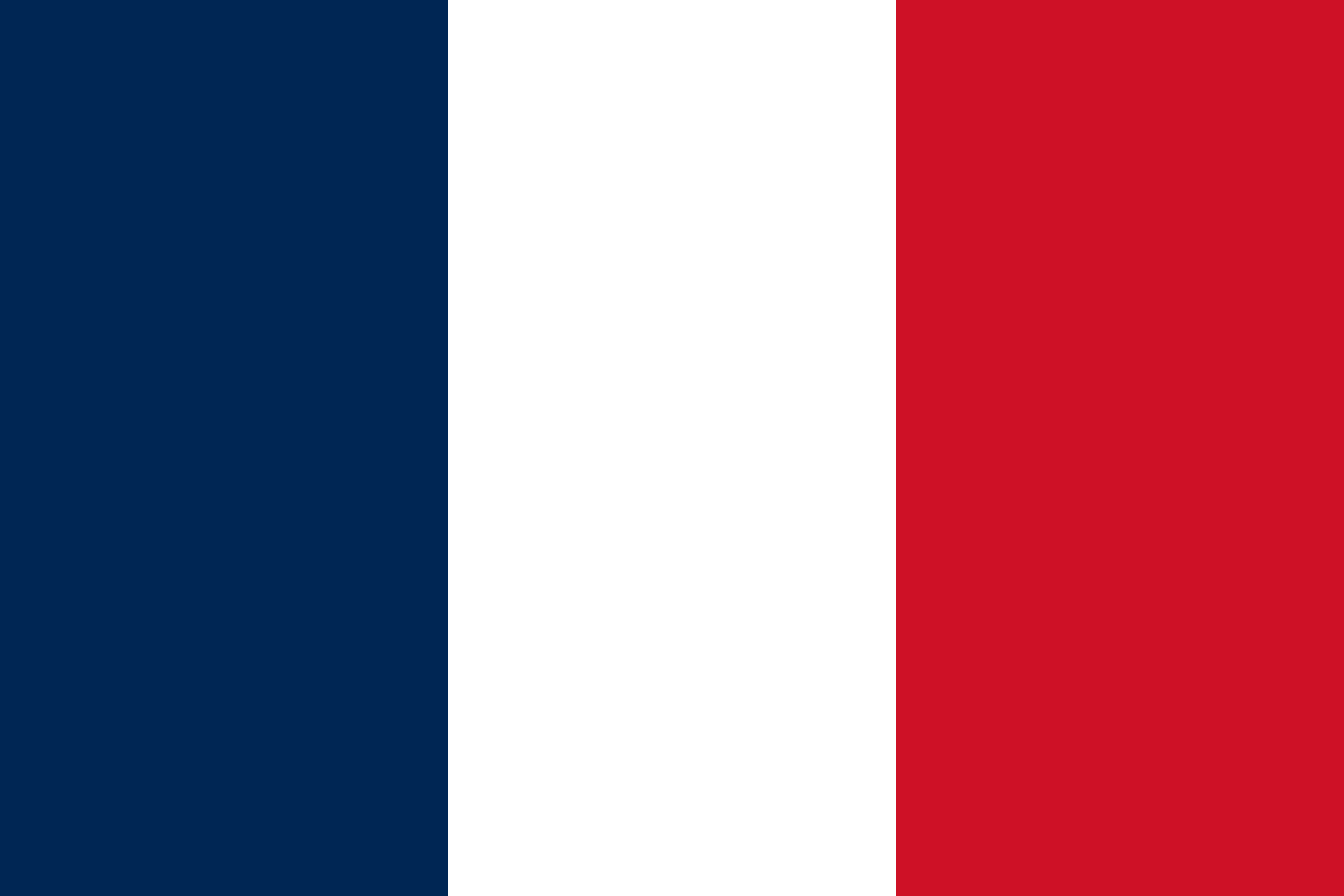
フランスは第一次世界大戦後、通貨フランの価値を大幅に切り下げて1928年に金本位制に復帰しており、世界恐慌初期には他国ほど早く不況の打撃を受けませんでした。
むしろ金本位制離脱をしなかった数少ない主要国(「金ブロック」)として、イギリスなどから金が流入し、一時は資本がパリ市場に向かう状況も生まれました。
しかし、周辺国が続々と通貨切り下げを行う中で、フランス製品の競争力は低下し、フランス経済も次第にデフレと高失業に苦しむようになります。
政府は財政均衡に固執して有効な景気刺激策を打てず、1935年頃には工業生産が急落し失業も増大しました。
政治的にも右派・左派の対立が深まり、1934年には右翼団体がパリで暴動を起こし議会に突入するなど社会不安が高まります(2月6日危機)。
この混乱の中、1936年に人民戦線(左派連合)が選挙に勝利してレオン・ブルムが首相となり、恐慌対策と社会改革に乗り出しました。
ブルム政権は労働者の購買力向上を図るため、週40時間労働制と有給2週間のバカンス(休日)を導入し、賃金引き上げを実施しました(マチニョン協定)。
また、フランの平価切り下げ(約30%の切り下げ)を行い、ようやく金本位制から離脱して通貨安政策に転換しました。
国営鉄道会社の創設や軍備拡張の加速など、公共支出も増加させました。
これらにより景気には一定の刺激が加わり、経済成長率はわずかながらプラスに戻りましたが、同時にインフレ懸念や資本逃避も生じ、ブルム内閣は十分な成果を出す前に政権を手放すことになります。
1938年には保守系のダラディエ内閣の下で再び財政緊縮が志向され、フランスの本格的な経済復活は結局ドイツの脅威に対応した軍需生産によるところが大きくなりました。
総じてフランスは、金本位制への固執により景気回復が遅れ、世界恐慌から立ち直るのに最も時間がかかった国の一つでした。
ソ連:世界恐慌と無縁だった計画経済

当時社会主義体制を築いていたソ連(ソビエト連邦)は、資本主義圏からほぼ孤立した計画経済を採っていたため、世界恐慌の影響を直接には受けませんでした。
1928年から開始されたスターリンの第一次五カ年計画によって、ソ連経済は1930年代を通じて年平均10%前後という非常に高い成長率を記録しました。
重工業分野を中心に急速な工業化が進み、1930年頃にはGDP規模でイギリスを追い抜きアメリカに次ぐ経済大国になったとの推計もあります。
このようなソ連の独自路線の成功は、資本主義諸国で苦境にあえぐ人々に「計画経済には恐慌がない」と映り、一部の知識人や政治家が社会主義に希望を見出すきっかけともなりました。
実際、イギリスではケンブリッジ大学の出身者がソ連の思想に共鳴しスパイとなるなど(ケンブリッジ・ファイブ事件)、社会的ショックも与えています。
もっとも、ソ連の経済成長は市場の自発的成長ではなく、国家権力による農業集団化や強制労働を含む人命軽視の手段で達成されたもので、国内ではウクライナの大飢饉(ホロドモール)など悲劇も起きていました。
いずれにせよ、ソ連は大恐慌下でも失業や需要不足に悩まされることなく、独自の工業化と軍備増強を推し進めたのです。
その結果、1930年代後半にはソ連は世界有数の工業国となり、第二次世界大戦においても対独戦で工業力が勝敗を左右する要因となりました。
イタリア:ファシスト政権下での経済統制と侵略路線

イタリアは1920年代初頭にムッソリーニ政権(ファシスト党の一党独裁)が成立しており、世界恐慌期にもその体制が継続していました。
イタリア経済は第一次大戦直後から不安定で、世界恐慌が直接与えた影響は比較的限定的だったと言われます。
実際、1929年のニューヨーク株価暴落のニュースを聞いても、多くのイタリア国民は「自分たちには関係ない」と受け止めたという逸話もあります。
しかし恐慌期においてもイタリアの失業や経済停滞が解消していたわけではなく、政府は国家主導での経済統制を一層強める方向に進みました。
主要銀行を国有化し大企業と政府高官が協議するコーポラティズム(統制経済)体制を構築し、物価や賃金の調整を図りました。
また公共土木事業にも力を入れ、ポンティーネ湿原の干拓や道路網の整備などを行って失業対策を進めました。
さらに、人口増強を目指して独身税や多産奨励策を導入するなど社会政策も取り入れました。
1935年にはエチオピア侵略を強行し、国際連盟から経済制裁を受けますが、それを契機に自給自足的な経済運営(輸入代替や植民地からの資源調達)をいっそう推し進めました。
対外的にはドイツとの接近を深め、スペイン内戦への軍事介入(1936年~)や枢軸陣営の形成へ動き出します。
こうしてイタリア経済は、恐慌からの回復というよりは戦時体制への準備という性格を帯びていきました。
1930年代後半には公務員を含めた政府部門の雇用が増大し、総労働人口の5%以上が公的部門で働くまでになりました。
イタリアは世界恐慌そのものによる政変こそ起きませんでしたが、経済的には他国同様に政府頼みの需要創出と対外侵略によってしか活路を見出せない状況となり、ファシズム体制はますます軍事に依存することになりました。
その他の地域:植民地・新興国への影響
世界恐慌の影響は上記の主要国以外にも、世界中の植民地や新興国に及びました。
ラテンアメリカでは、ブラジルのコーヒーやアルゼンチンの小麦・牛肉など一次産品の価格が暴落したため輸出収入が激減し、多くの国で債務不履行(デフォルト)や政変が起きました。
ブラジルでは余剰となったコーヒー豆を政府が買い上げて焚火で焼却処分するなどの極端な策も講じられましたが、価格下落を食い止めるには至らず財政負担がかさんだだけでした。
1930年にブラジルでヴァルガスがクーデターで政権を握ったのを皮切りに、南米各国で権威主義政権や軍部政権が相次いで成立するなど、政治的にも大きな変動が生じました。
アジアでは中国が銀本位制を採用していましたが、アメリカの銀買い占め政策(1934年)により銀が海外流出して通貨量が激減し、物価下落と金融混乱に見舞われました。
これに対処するため、中国は1935年に法幣改革を行い銀本位制を放棄しましたが、同時期に日本軍の侵略が拡大し、国内は抗日戦争(1937年〜)の時代に突入しました。
東南アジアやアフリカの欧米植民地でも、ゴムや錫、綿花など輸出資源価格の下落で農村貧困が深刻化し、それが反植民地運動の高まりに繋がった地域もありました。
オーストラリアやニュージーランドなどイギリス自治領でも、農産物価格の暴落で深刻な不況に陥り、オーストラリア政府は対英債務の利払いを一時停止する措置まで取りました。
このように世界恐慌は地球上のほぼあらゆる経済圏に影響を及ぼし、従来の社会秩序や国際関係を根底から揺るがす出来事となったのです。
世界恐慌と第二次世界大戦へのつながり
世界恐慌は単なる経済危機にとどまらず、結果的に第二次世界大戦への道筋を作る大きな要因となりました。
各国が不況から抜け出すために取った行動が国際協調を損ない、相互不信と軍拡競争を招いたからです。
まず、経済的困窮に苦しむ中でドイツや日本・イタリアでは強硬な独裁政権が台頭し、領土拡張や軍事力による打開を目指す外向きの政策を採るようになりました。
ドイツのナチス政権はヴェルサイユ条約の軍備制限を無視して急速な再軍備を行い、1936年にラインラントに進駐、さらにオーストリア併合やチェコスロバキア解体へと踏み出しました。
日本も、1931年の満州事変を発端に中国大陸での侵略を拡大させ、国際連盟を脱退して独自路線を進みました(1937年には日中戦争勃発)。
イタリアも1935年にエチオピア侵略を強行し、国際連盟からの制裁を受けるとドイツに接近していきます。
一方、イギリスやフランス、アメリカなどの民主主義国は恐慌後も自国経済の立て直しに追われ、国際問題に積極的に関与する余裕を失っていました。
特にイギリスとフランスは、自国の景気回復と社会安定を優先するあまり、ファシスト諸国の侵略行動に対して有効な阻止策を取れず、宥和政策(譲歩による和平維持)に傾いていきました。
その結果、侵略側の野心を増長させてしまい、1939年9月にドイツがポーランドに侵攻するとついに第二次世界大戦が勃発することになります。
また、経済的ブロック化により世界は複数の経済圏・勢力圏に分裂し、資源や市場を巡る対立が深まったことも戦争の背景要因となりました。
つまり、世界恐慌がもたらした経済の混乱と政治の急激な過激化は、国際秩序の崩壊とグローバルな戦争への直接的な引き金の一つとなったのです。
第二次世界大戦そのものが、各国に巨大な軍需需要をもたらすことでようやく世界恐慌を終息させる結果となったのは、歴史の皮肉と言えるでしょう。
なお、1936年から始まったスペイン内戦では、恐慌後に対立を深めたファシズム勢力(ドイツ・イタリアが支援)と社会主義勢力(ソ連が支援)が代理戦争的に激突し、この戦いは第二次世界大戦の前哨戦ともなりました。
世界恐慌と投資:資産価格の変動と現代への比較
世界恐慌は金融市場にも大混乱を引き起こし、様々な資産の価格が急激に変動しました。
まず株式市場では、ニューヨークのダウ平均株価がピーク時(1929年9月)から約3年間で実に8割以上も下落し、多数の投資家が巨額の損失を抱えました。
株式だけでなく、商品市況も総崩れとなり、工業原材料や農産物などの価格指数も軒並み半値以下に暴落しました。
不動産価格も下落し、アメリカでは住宅の差し押さえ件数が急増するなど、不動産投資にも大きな痛手となりました。
一方、相対的に安全と見なされた資産に資金が集中する動きも見られました。
当時の安全資産とは金(ゴールド)や信用力の高い国債などです。
金本位制下では各国通貨は金との交換が保証されていたため、人々は銀行預金を引き出して金地金に換えることで資産保全を図ろうとしました。
これが各国の金準備流出と銀行破綻を招いたわけですが、逆に金そのものは価値の維持に成功し、アメリカでは1934年に政府が金の公定価格を大幅に引き上げたため(金1オンス=20.67ドル→35ドル)、金保有者は名目上約7割の評価益を得る形となりました。
ただしアメリカでは1933年に一般国民の金保有が禁止されたため、恩恵を享受できたのは一部の投資家や他国の中央銀行などに限られました。
アメリカ国債など政府の信用が高い債券はデフォルトの心配が低いため、株式から債券への資金シフトも起こりました。
実際、連邦政府が元本と利払いを保証する債券(トレジャリー)は不況期でも信頼され続け、下落する物価の中で実質利回りが向上する結果となりました。
このように、恐慌時にはリスク資産から安全資産へ資金が移動し、資産価格の明暗が分かれることが起きました。
現代の金融危機でも基本的な構図は似ています。
例えば2008年のリーマンショック時や2020年のコロナショック時にも、株価の急落と同時に投資家はこぞって国債や金などの安全資産を買い求め、各国の長期金利が低下し金価格が上昇するといった動きが見られました。
もっとも各国政府・中央銀行は世界恐慌の教訓から、危機時には迅速に大量の流動性供給や金融緩和を行うようになっており、資産価格の下落も一定期間で食い止められるケースが増えています。
世界恐慌当時には存在しなかった預金保険制度や中央銀行の大胆な市場介入(量的緩和など)によって、金融システム崩壊のリスクは低減され、結果として株式市場も大恐慌ほどの長期低迷には至っていません。
それでも、どんな時代でも過度の楽観によるバブルと悲観によるパニックは繰り返されるため、投資家は歴史に学んで適切なリスク管理を行う必要があります。
不況下でも成長した企業・産業の例
世界恐慌の中で大半のビジネスが苦境に立たされる中、それでも成長を遂げたり好調さを維持した企業・産業もありました。
例えば自動車業界では、需要全体は激減したものの、当時新興のクライスラー社が他社の凋落に乗じてシェアを拡大し、1929年に9%程度だったアメリカ国内の市場占有率を1933年には約24%にまで伸ばしました。
また日用品・食品などの生活必需品を扱う企業は比較的底堅く、代表的な消費財メーカーであるP&G(プロクター・アンド・ギャンブル)は不況期でも広告費を削らずに積極的にラジオ番組の提供(いわゆる「ソープオペラ」の語源となった連続ドラマ)を行い、売上を伸ばしたと言われています。
タバコなど嗜好品産業も不況に強い傾向があり、米国のラッキーストライク(たばこブランド)は1930年代に販売を伸ばし業界トップに立ちました。
エンターテインメント分野も人々に安価な娯楽を提供することで支持を集めました。
ハリウッドの映画産業は1930年代に黄金時代を迎え、多くの人々が失業や貧困の現実を忘れるために映画館に足を運びました。
実際、チャップリンの『モダン・タイムス』(1936年)やディズニーの長編アニメーション第1作『白雪姫』(1937年)など、不況下でも名作が次々と生まれ、映画会社は相応の利益を上げています。
このような例から、不況期には人々の生活に不可欠な商品や心の安らぎを与える娯楽が強さを発揮することがわかります。
反対に、高額な贅沢品や耐久消費財(高級車、高級家具など)は真っ先に需要が冷え込み、多くの企業が倒産に追い込まれました。
高級百貨店が閉店したり、一部の高所得者向けブランドが姿を消す一方で、低価格帯の商品を扱う企業は生き残るといった現象も見られました。
つまり、経済危機時には何が売れるか/売れなくなるかが大きく変わり、ビジネスにおいては消費者のニーズの変化を見極めることが生き残りのカギとなるのです。
世界恐慌から得られる教訓:再び危機に備えるために
世界恐慌の経験は、現代に生きる私たちに多くの教訓を与えてくれます。
まず、経済政策の面では、不況時に政府と中央銀行が適切な介入を行うことの重要性が明らかになりました。
当時は財政支出や金融緩和を躊躇した結果、不況が深刻化・長期化しましたが、その反省から現在では危機時に積極的な景気刺激策(減税・公共投資や金融緩和策)を講じることが一般化しています。
また、銀行の破綻が人々の貯蓄を一瞬で奪った反省から、預金保険制度が整備され、中央銀行が最後の貸し手として金融システムを支える枠組みが構築されています。
国際協調の重要性も痛感されました。
世界恐慌期には各国が自国優先の保護主義に走り協調が崩れましたが、その反省から第二次大戦後にはIMF・世界銀行の設立やGATT(関税と貿易に関する一般協定)を経てWTOの創設など、国際的な経済協調の枠組みが作られました。
実際、1944年にはブレトンウッズ会議で固定為替相場制の下、IMF(国際通貨基金)や世界銀行が創設され、戦後の国際通貨体制の礎が築かれました。
今日でも、世界的な不況や金融危機に際して各国が協調して対策を打つこと(国際協調の政策対応)が、世界恐慌の二の舞を防ぐ鍵となっています。
次に、企業や投資家の視点では、リスク管理と分散の重要性を再認識させられます。
世界恐慌下では、一夜にして資産や仕事を失った人が多数出ましたが、それは特定の資産や収入源に過度に依存していた脆弱性が露呈した面もあります。
投資家であれば、株式だけでなく債券や現金、あるいは不動産や金など複数の資産クラスに分散投資しておくことで、一種類の資産が暴落した際のダメージを軽減できます。
また借入金(レバレッジ)に頼った過度な投機は破滅を招きかねないことも肝に銘じるべきです。
ビジネスにおいても、市場の楽観に乗じて無理な拡大をするのではなく、十分な自己資本や手元流動性を確保しておくことが危機耐性に繋がります。
さらに、環境変化に柔軟に適応する企業姿勢も重要です。
世界恐慌期にも、低価格の商品を提供して成長した企業(例:アイスクリームや映画など娯楽産業)や、新技術への投資を継続した企業は、景気回復後に大きく飛躍しました。
つまり、長期的な視野に立ち、好況時にも慎重さを忘れず、不況時にも将来への投資を怠らないことが、生き残りと成功の鍵といえます。
最後に、社会・政治の面での教訓も見逃せません。
経済的苦境が深まると、人々は極端な思想やポピュリズムに惹かれやすくなるため、政府は速やかに雇用対策やセーフティネット(生活保護や失業給付)を講じて社会不安を和らげる必要があります。
民主主義社会を守るためにも、経済的弱者を放置せず、公正な分配と機会提供を行うことが大切だという教訓が世界恐慌から得られます。
総じて、世界恐慌の悲劇を繰り返さないためには、政府・企業・個人それぞれが歴史から学び、バブルの兆候には警戒を怠らず、危機が起きた際には協力して適切な対応を取ることが不可欠です。
今日の私たちも、平時から最悪の事態を想定した備え(例えば分散投資や十分な貯蓄、危機対応計画の策定など)をしておくことで、たとえ「100年に一度」のような経済危機が訪れても冷静に乗り越えられるでしょう。
歴史に学び備えを怠らないことこそが、世界恐慌を経験した先人たちからの最大のメッセージなのです。
世界恐慌から学ぶポイントまとめ
- 金融危機時には政府・中央銀行が迅速かつ大胆に介入し、信用収縮を防ぐことが必要(消極策は不況を悪化させる)。
- 保護主義的な対応は世界全体の貿易を縮小させ、結果的に自国経済も更なる打撃を受けるため避けるべき。
- 日頃からのリスク管理と資産分散が重要(株式だけに頼らず債券・現金・金などにも分散し、レバレッジ投資は控える)。
- 好況期にも過度な楽観を戒め、バブルの兆候には注意する(「木は天まで成長しない」ことを肝に銘じる)。
- 不況期には悲観に囚われすぎず、将来に備えた投資(人材育成や技術開発)を継続することが長期的な成長に繋がる。
- 社会の安定を保つため、セーフティネットの整備や雇用対策を適切に行い、極端な政治勢力の台頭を防ぐことが重要。
世界恐慌の主な出来事(タイムライン)
- 1929年9月: ニューヨーク株価が高値から下落し始める(株価バブルのピークアウト)。
- 1929年10月24日: 暗黒の木曜日 – ニューヨーク株式市場で株価が大暴落。
- 1929年10月29日: 暗黒の火曜日 – 大暴落の連鎖が続き、投資家がパニックに陥る。
- 1930年6月: アメリカでスムート=ホーリー関税法成立(高関税政策の開始)。
- 1931年5月: オーストリアのクレジット・アンシュタルト銀行が破綻(欧州金融恐慌の引き金)。
- 1931年9月: イギリスが金本位制を離脱(ポンド平価切下げ、チープマネー政策へ)。
- 1932年: 世界貿易額が1929年の半分以下に縮小(保護主義の影響)。
- 1932年11月: アメリカ大統領選挙でルーズベルト当選(ニューディール政策へ転換)。
- 1933年1月: ドイツでヒトラー内閣成立(ナチ党政権が発足)。
- 1933年3月: ルーズベルト米大統領就任、銀行休業令を発して金融システムを安定化。
- 1933年3月: ナチス・ドイツで全権委任法成立、独裁体制へ移行。
- 1933年5月: アメリカでテネシー川流域開発公社(TVA)設立(ニューディール政策の一環)。
- 1933年12月: 日本で高橋是清蔵相が金輸出再禁止(円平価切下げ)を実施。
- 1934年6月: ドイツで「長いナイフの夜」事件(SA指導部粛清)。
- 1935年: イタリアがエチオピア侵攻開始、国際連盟が制裁決議(集団安全保障の挫折)。
- 1936年: 日独防共協定締結(枢軸陣営の形成)。
- 1936年: フランスで人民戦線内閣成立、ブルム首相が社会政策とフラン切下げを実施。
- 1937年7月: 日中戦争勃発(盧溝橋事件)、日本の中国侵略が本格化。
- 1937年: アメリカでルーズベルト不況(一時的な景気後退)、その後軍需景気で回復。
- 1939年9月: ドイツがポーランド侵攻、第二次世界大戦勃発。
まとめ:歴史の教訓を未来に活かす
以上、世界恐慌の発生から各国の対応、影響や教訓に至るまで詳しく見てきました。
世界的な大不況がいかに人々の暮らしと社会を揺るがし、その後の歴史を変えたのかがお分かりいただけたと思います。
歴史は繰り返さないまでも韻を踏む(同じような事象が形を変えて起こる)と言われます。
なお、現代においても世界的な大不況の再来が危惧される局面はあります。
例えば2008年の金融危機(リーマンショック)時や2020年の新型コロナ危機時には「第二の世界恐慌になるのでは」との声も上がりました。
しかし各国政府と中央銀行は世界恐慌の教訓から迅速な金融支援策や財政出動を行い、未然に最悪の事態を食い止めました。
とはいえ、油断すれば同様の危機がいつ起きてもおかしくないとも言われます。
だからこそ、歴史を学び備えることが今後も重要なのです。
21世紀の現代に生きる私たちも、この世界恐慌の教訓を他人事とせず自分事として捉え、日頃から備えを怠らないことが大切です。
具体的には、個人としては資産運用の分散や非常時の貯蓄、企業経営者であれば財務健全性の確保と危機管理計画の策定、そして政府の立場であれば迅速な政策対応と国際協調の姿勢が求められます。
本記事をきっかけに、ぜひご自身の周りの経済状況やリスクについて改めて考えてみてください。
そして歴史が示す知恵を活かし、将来起こり得る危機に備える行動を今日から始めてみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
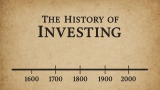
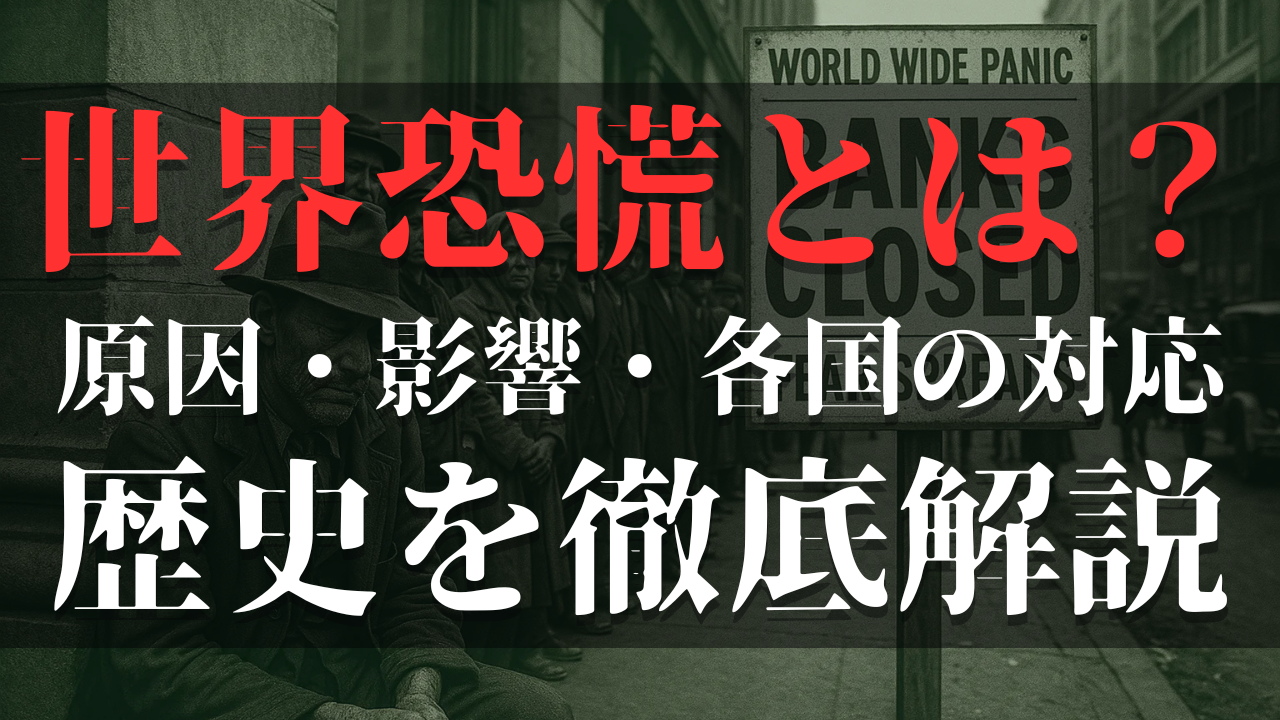




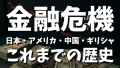
コメント